
ゲリラ的美少女野球団うぇんでぃずはただいま夏季合宿中です。

(注;いつの間にやら志穂美の髪型が変ってる。というか、元々こうだったのが弥生ちゃんの髪型とバッティングする所があったので変形させられてたのを元に戻しただけで、これでウエンディズは黒髪のキャラばっかりになるのであった。問題あるな。)
「情けない! 7人も女の子が居て誰も御飯作れないなんて!」
と、明美は言った。
ウエンディズ合宿の炊事当番を決める会議での事である。
誰か料理が得意な者を、という常識的な結論に達したのだが、では誰が料理に自信があるかというので手を挙げさせてみると、結局山中明美だけだったのである。ちなみに明美二号は一年生の体験学習とやらで今日はまだウェンディズ合宿には参加出来ていない。鳴海は後でやってくる事になっている。中学生もなかなか忙しい。
弥生「いや、作れと言うのなら作るわよ。ただ出来たものに責任は持てないといってるだけでね。」
まゆ子「そうそう。レシピ通りにつくるだけならね。それを食べて他人がどう思うかまでは知らないってだけであって、自分が食べるだけならどうにでもするわよ。」
じゅえる「私はお菓子なら作るよ。クッキー焼けというのならいくらでも焼くけど、でもねえ。」
ふぁ「酒のつまみなら結構自信ある。酒屋の娘だもん。そんなもの朝から食いたくはないだろ。」
しるく「ごめんなさい!衣川の娘が厨房に立つなって言いつけられてるの。」
聖「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
明美「でもやってもらうわよ。私ひとりで8人分も10人分も作りたくないもん。」
まゆ子「そりゃ手伝うわよ。手伝う。だけどね、誰か責任者を決めておこうっていうのよ。誰の味に統一するかってのはこれは重要な事だからね。」
明美「そんな事言ったって結局最期はわたしに全部押しつけるんだから、いっつもそうなんだから。」
じゅえる「しかたないじゃない。日常的にお炊事してるのってあなたしかいないんだから、あなたが責任者になるわよ。当然。」
ふぁ「そうそう。」
明美「でもつかれるのよ。しんどいんだよ。練習とかやった後で自分たちで作るんだから。」
弥生「だから手伝うって言ってるじゃない。だれも明美だけにやらせようって言ってるんじゃないんだから。」
明美「信用できない。」
まゆ子「それはそうか。ほら弥生ちゃん。」
弥生「なによお。まるであたしが明美をこき使ってるみたいな言い方じゃない。」
ふぁ「そおそお。」
弥生「なに?」
しるく「ごめんなさい、明美さん。でもやっぱりおいしい御飯が食べたいのよ。」
まゆ子「詰まる所はそういう事。誰もまずい料理を我慢して食べたくないから、こういう事決めるんじゃない。だからあ、いつも家で御飯作ってる明美が責任者になるべきだって言ってるのよ。」
明美「信用できない。もおおー、だまされないもん。いっつもいっつもそうやってヒトを言いくるめて、で、いっつも貧乏くじ引かされるのは私なんだから。」
弥生「だからあ、・・・どうしよ。」
じゅえる「どうしよったってねえ。」
「まったく!」
と、おもむろに志穂美が立った。
志穂美「要するに明美じゃない人間が調理の責任者になればいいだけの話じゃない。やるわ、私。」
弥生まゆ子じゅえるふぁ「え!」
明美「で、出来るの?」
志穂美「当然。」
じゅえる「人間が食べるのよ?」
志穂美「馬鹿な事を聞くな。」
明美「じゃあー決まりだ。志穂美が責任者であたしはお手伝い。」
弥生「どう?」
まゆ子「わかんない。」
じゅえる「やらせてみようか。だめだったらまた考え直すって事で。」
弥生「よーし決定!カレーがいい!」
まゆ子「カツカレーだ!」
じゅえる「エビかつカレーだ!」
ふぁ「エビかつカレー南蛮だ!」
明美「あのね、そんなもの急に出来る訳ないでしょ。」
志穂美「作るわよ。できるよ。」
明美「ホントに?」
志穂美「どうせ材料を買ってくるのはこいつらだ。私達はその間ごろごろしていよう。」
明美「おおおー。さすがだ。ほらみてよ、もし私が責任者だったら足りない材料も自分で買いに行かされるトコなんだから。」
弥生「ちちち。」
じゅえる「手ごわい。」
しるく「あのね、皆さん。実はお出入りのお魚屋さんにウエンディズ合宿の話をしたらお魚を人数分届けて下さったの。ですから今日の晩ご飯はそれを頂くべきだと思うの。」
志穂美「なに?」
しるく「鯛よ。あんまり大きくなくて赤い。」
志穂美「キンメダイか。」
明美「おお、なんかほんとに出来そうだ。」
まゆ子「なんだか大丈夫そうだねえ。任しておこうか。」
明美「あの、志穂美さん。」
志穂美「なに?」
明美「なんで刺し身包丁を握ってるの。」
志穂美「魚だから刺し身包丁だろ。」
明美「いやでも、お刺し身じゃないでしょ。それに三枚におろすのは。」
志穂美「なんだ、もう腸は取ってるんだ。つまらん。」
明美「処理をするのも出刃包丁でしょ。」
志穂美「なんだ、大きいのもいるじゃない。こっちは刺し身にしてアラはお吸い物にするぞ。」
明美「それでいいんだけど、どうして刺し身包丁を手から放さないの。」
志穂美「それにしてもなんだな、今日はこれがあるからいいとして、これからの食費はどう始末つけるかだな。明美、これが終わったら一週間分の献立表と食材の買い出しスケジュールを作るぞ。」
明美「それはいいけど、どうしてトマトを刺し身包丁で切るの。しかも空中で。」
志穂美「刺し身は私が請け負った。あんたは小さいのをどうかしとくれ。」
明美「だから三枚におろすのは刺し身包丁じゃなくて!」
弥生「どう?」
まゆ子「出来てるよ。刺し身包丁で三枚におろしてる。」
じゅえる「嘘みたいだけど、志穂美ってお料理得意なんだ。」
ふぁ「どちらかというと生き物を切り刻むのが好きって感じだけど。」
まゆ子「出来てるものは出来てるみたいだから。」
弥生「私達が口を出す筋合いじゃないってわけか。」
まゆ子「あ、明美がこっちにマル出した。ホントに出来てるんだ。」
じゅえる「うーーーーむ。なんとなく釈然としない。なにか落とし穴とか爆発トラップとかあるんじゃないだろうか。」
ふぁ「夜な夜な包丁を研いであたしたちを襲ってくるとか?」
弥生「そりゃじぇいそんだ。」
志穂美「そこ!外野うるさい。」
しるく「おこられてしまいました・・・・・。」
聖「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。」
10分後。
鳴海「こんにちわー。」
弥生「お、来たね。」
しるく「いらっしゃい。」
鳴海「あれ、皆さんなにぼーっとしてるんです?」
じゅえる「待機中。御飯ができるのを待ってるの。」
ふぁ「この合宿所もねー、クーラーが使えたらいいんだけど。」
しるく「父がクーラーは嫌いなもので。でも日本家屋にクーラーは本当に似合いませんわ。」
鳴海「じゃあ御飯を作ってるのは明美さんと、あれ?」
じゅえる「あんたの姉さんだよ。」
鳴海「ゑ、おねえちゃんですか・・・・・。」
ぴく、とその場の全員が鳴海の言葉に凍りついた。
そして、
弥生まゆ子じゅえるふぁ「なるみちゃん、あんたの姉さんのりょうりにいったいなにがあるんだ。答えるんだ、志穂美の料理はだめなのか、食えないのかあああああ?????」
鳴海は四人にぐるんぐるんと振り回されて目が廻ってしまった。
鳴海「いえ、お姉ちゃんの腕はたしかなんですけど、その、味つけが。」
科学調味料が大好き 全部同じ味になってしまう!
「きゃあああああ、やめてえーー。」
突然、明美の衣を裂くよな悲鳴が飛ぶ。
ふぁ「とめろ!志穂美を止めるんだ!!」
ばたばたばたばたばたばたと弥生ちゃん達は厨房になだれ込んだ。
志穂美「放せ、本場中国の中華料理ではこのくらい入れるもんだ。」
まゆ子「お吸い物でしょ。これお吸い物じゃないの。」
じゅえる「おたまいっぱい入れる馬鹿がいるもんかーー。」
弥生「解任だ!志穂美の解任動議を提出する!!」
しるくと聖はその騒ぎに加われなくてただ引き攣っていた。
聖は、しかし、本当にそれくらい科学調味料を入れる店があるのにな、とちょっと志穂美に同情した。
2000/08/12/

祐木聖は現在深刻な状況にある。人生最大の危機にあると言ってもよいだろう。未熟児としてこの世に生を受けて以来これほどまでに死というものに直面する事は無かった。
なんでもない事だったのだ。合宿の仕事の分担をくじで決めただけで,それで聖は「お菓子の買い出し」という任務を引き当てた。最悪の選択ではない。いつも聖とついて歩く山中明美は2キロ先の学校まで備品を調達にいくという過酷なミッションを引き当てた。それに比べればたかだか600メートル先のお菓子屋に行くなど問題と言えるようなものではないだろう。十人分とはいえ所詮はお菓子である。軽い。誰一人それが極めて困難な状況を聖に与えるなどと思わなかった。
当の聖ですら考えもしなかった。金属バットより重い物体などこの世にあろうはずもない。それですら以前の自分では持ち上げる事もできなかったのが,うえんでぃずに半ば強制的に加入させられ過酷な訓練を課せられた結果、振り回してもこけないだけの十分に強力な筋力を獲得する事に成功しているのだ。
お菓子で死ぬ,などありえる事では無かった。
太陽が無ければ,である。
聖は汗をかかない。低体温であり生まれてこのかた汗をかく程の運動もしなかったからだ。小学生の頃は虚弱児で体育の時間はいつも見学だった。むりやり動いたら気絶する。冷却の為の汗腺も発達していないから特に夏場は見学しているだけでも気分が悪くなる。中学生の時は唯一水泳の授業には参加できたが,それは水の中で常に冷却されるからだ。聖の類いまれな知性は代償として脳への負担をもたらしている。頭が上せたらどうなるか、夏場の運動は絶対のタブーなのだ。
だが蒲生弥生は聖の欠点を瞬時に看破して見事解決した。彼女自身が夏に弱かったからだ。
のびたら水に漬ける。
蒲生弥生が開発した聖の冷却法である。たったこれだけで聖の運動時間は驚く程延長された。聖自身も信じられなかったほどだ。そしてだんだん身体が慣れてきて、現在では春先のひなたで30分も野球が出来るようになった。といってもほとんど棒立ち状態で球を待っているだけだが,それですら聖にとっては驚異の進歩だったのだ。
だから過信した。
衣川邸は樹が茂って適度に陰を作ってくれる。具合がいい事に門を出る頃は雲が日差しを遮っていてちょうどいい気温だった。聖自身はウエンディズのメンバーから託された種々雑多のオーダーに気を取られていてつい注意がおろそかになった。それ以前に600メートル歩くという大仕事に緊張していた。
必死でたどりついたお菓子屋はただの駄菓子屋ではなかった。お菓子専門店だった。問屋のような形態で通常のコンビニやスーパーでは見られない怪しいお菓子がいっぱいあるという変わった店だ。聖はそこで自分が託された注文の本当の意味を知った。
お菓子は大きかったのだ。業務用のパックというものがこんなに大きいとは想像もしなかった。おかきをキログラム単位で売ってるなんて聞いた事もなかった。志穂美の言う「毒々しい色のついたキャンディ」というのが数百種類もあるなんてのも知らなかった。ふぁの注文の羊羹は聖の脚よりも太かったし,まゆ子のせんべいは直径が30センチもあり鉄鈑より固い。結局ビニール袋は5個にもなった。
聖はかろうじてすべての袋を持つ事が出来た。持ったまま歩く事が出来た。以前の聖にはとうてい不可能に思えた事だ。だが今回それが間違いだった。自分ひとりでは持てないとあきらめていれば,電話でもして誰かに迎えにきてもらう事も可能だったろう。なまじ持ててしまったが為に,聖は死のロードに足を踏み入れてしまった。
限界が来たのはお菓子屋を出て50メートルだった。そこで聖は初めて「暑い」という事を意識した。雲が晴れ,太陽が強烈な日差しを投げかける。午後2時だ。一日の内で最強の光線が聖の身体を灼いた。自分の皮膚の一枚一枚がめらめらと燃え上がりめくれていくビジョンが聖の脳裏にかげろうのように揺らめいた。
しまったと思った。しかしもう戻れなかった。足を止められなかった。止めるともう二度と歩けない事は分かっていた。手の中の袋は鉄の錘と化し聖の掌に刃のように食い込む。収縮する筋肉は開く事をもう忘れた。もはや選択の余地は無い。ひたすら前に、衣川邸へ、一刻も早くたどり着く事を祈るばかりだった。すでに歩みは聖のコントロールを離れ、勝手に前へと進んでいる。聖本人は茫然と見守るだけだった。
聖の足はそれでもよく働いた。炎天下、照り返すアスファルトの両面攻撃に耐え衣川邸へ戻る中間地点300メートルまで進んだ。しかし、そこが限界だった。ここから衣川邸まではほんのわずか登りとなっている。行きには助けとなった坂が帰りには絶壁も同然に聖の帰還を阻む。あとはただ立ち尽くし日に焙られるままとなった。
聖は必死で考えた。どこか日陰で休むべきで、頭から水をかぶればまだ何とかなる。いや、もう一度お菓子屋に戻って救援を頼むべきだ。だがどれも実行に移せなかった。あいにくとこの地点には一点の日陰も存在しない。ひたすらまばゆい光が世界を包んでいる。聖の左手には延々と続く壁がある。この壁のむこうはもう衣川邸なのだ。もちろん聖に乗り越えられる代物ではない。うらめしく見上げるだけだ。
せめてこの荷物さえ無ければまだなんとかなるだろう。しかし魔物がとりついたようにお菓子の入った5つのビニール袋は聖の手から離れなかった。じゅえるのチョコ菓子や弥生ちゃんのするめなどはいいのだ。ふぁが、あの大女が注文した羊羹が重いのだ。どうしてこんな中身が詰まったものを頼んだりしたのか、殺意が心の奥底から沸いてきた。ふぁの白い肌が、長い手足が目の前を踊り、聖の脳を嘲弄する。想像の刃で切り裂こうとしても、現実に拘束された手が、足がコンクリで固めたように全身を硬直させ精神までも呪縛する。やがて真っ白なふぁの顔が聖の鼻先に寄せてきて、赤い唇が、きらめく歯が聖を噛み砕いていく。
ふと気がつくと、自分の呼吸音だった。いつの間にか気が遠くなっていたのだ。自分を取り戻した聖は必死で考えた。ともかく日陰に逃げ込むべきだ。無ければ自分でつくればいい。まゆ子の30センチせんべいは十分に日差しを遮ってくれるだろう。荷物を手から放して、この場にいったん置き去りにして、自分だけでもともかく衣川邸に逃げ込んで、それから・・・。
しかし、聖は自分の手がすでに自分の意思を離れて収縮し続けているのに気付かなかった。腕からも、もう感覚が無くなっていた。この呪縛から逃れる手段はただ一つ、その場に倒れ込むだけで良かったのだが、全身の硬直が聖を一本の碑と変え世界の中でその存在を主張する事を止めなかった。
聖は、やめなかった。でももう何も残っていなかった。絶望という言葉があまりにも空虚に聞こえるこの状況で、ひたすらもがき続けていたのだ。傍目には彼女の身体は微動だにしていなかったが。
だがそれも終わり、目の前が真っ赤に染まっていく。曙より紅い光が聖の額を押し破り、脳が沸騰し膨張していく音を聞いた。
「ばぐわぐきゃぐ」
「きゃああああ、聖さん、ひじりおねえさん!!」
聖を発見したのは鳴海とピカードだった。ピカードを合宿所に連れていく所だった鳴海は、聖が立ち止まっているのをはるか後方から発見していた。いつまで経っても動かない聖をただ立ち止まって休んでいるのだろうと思っていたのだが、接近し荷物を半分持ってあげようとしたところ、聖が完全に気絶しているのに気付いたのだ。
熱射病だ、と瞬時に判断した鳴海は首から下げていた烏龍茶を聖の頭からかけて冷却し、そのまま聖を担いで衣川邸に走り込んだ。聖が決してお菓子の袋を手から放そうとしなかったので、袋ごと、聖を運んだ事になる。一番貧乏くじをひかされたのは鳴海だったといえるだろう。その間、駄犬ピカードは鳴海の周りを走り廻って吠えるだけで何の役にも立たなかった。
衣川邸で手当てを受けて一命を取り止めた聖は、その後
「死んでもお菓子を放さなかった女」
として面目を施したのだった。
2000/08/01
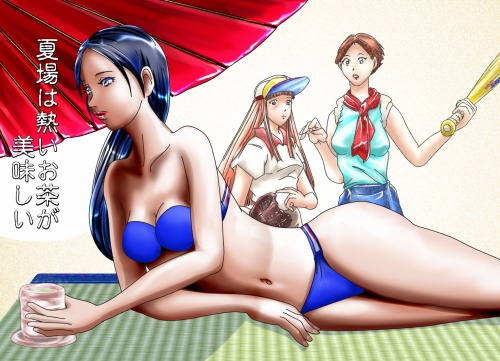
じゅえる「弥生ちゃん弥生ちゃん、野球の練習をしようよ。」
ふぁ「ごろごろしてたら何の為のウエンディズ合宿かわかんないよ。」
弥生「ぼーーーーーーー。」
じゅえる「あー、やっぱダメだわ。弥生ちゃんは暑いのダメだもん。その名のとおりに春先に大暴れするタイプだから。」
ふぁ「見かけじゃ夏もいけそうな感じだけどねえ。
あ、ども。ふぁです。
現在ウエンディズは夏季合宿に突入しています。
合宿と言っても、なんだか知らないけど学校の方では夏季講習もやってるんで、私達はこのしるくの家の合宿所から登校するってありさまです。」
じゅえる「なんだかねえ、夏期講習って二週間もあるんだよね。でもって夏休みの終わりにも一週間の講習があって半日は勉強させられちゃうんだから。正味の夏休みって言ったら二週間しか無いのよ、これが。」
ふぁ「おまけにさらに朝講習が一時間あるんだから、希望者だけなんだけど。」
じゅえる「希望者って、くらすのほぼ全員が来るんだもん。こないと肩身が狭くって、ほとんど強制にちかいものがあるわ。」
ふぁ「まったくえらい迷惑だ。しかもだよ、弥生ちゃんは朝の五時から起き出してランニングさせるんだから。こいつったら自分が日中は暑さでダウンするのを計算に入れてスケジュール組んでるんだからひきょーだよ。」
じゅえる「キャプテンの特権乱用だわ。まったく。」
ふぁ「ところでさあ、日曜日でいいんだけど、いい儲け話があるんだ。」
じゅえる「何々?」
ふぁ「しるくん家の裏山ってさあ、衣川の持ち山なんだろ。ここに登ってさ、カブトムシ採ってくるんだよ。一個五百円で売れるんだよ。」
じゅえる「最近じゃクワガタの方が値が張るんじゃない?」
ふぁ「いやいや、ここら辺には大きいのはいない。せいぜい4センチくらいのコクワガタかな、しか採れないんだ。そんなのはカブトムシ採りに行ったらおまけで採れるようなものだよ。それだったら地道にカブトムシに狙いを定めた方が賢明というものじゃないだろうか。」
じゅえる「カブトムシって、朝早いうちに採りにいくんだっけ?」
ふぁ「朝三時。前の日に蜜塗って。」
じゅえる「ぼーーーーーーー。」
弥生「ぼーーーーーー。」
ふぁ「おのれ、使い物にならんやつらばかりだ。」
2000/07/27