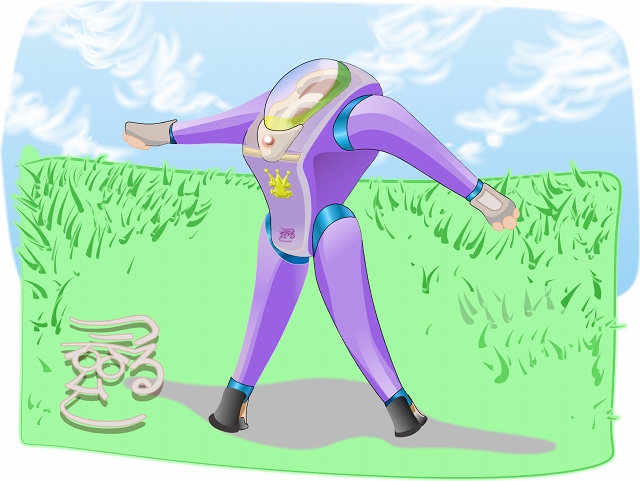本格リアルロボットSF小説
サルボモーター(β版)
上へ
第一歩 サルボモーター
軍用のサルボモーターが実際に俺達の前に現れた時は、思わず笑った。
そもそもがサルボモーターというビークルは兵器転用に思いっきり向かない存在で、それを無理して軍用に使うのだから珍妙なものだろうとは予想していた。だが、
綾子は言った。
「白く塗っただけじゃん。」
民間用、いやその言い方は卑怯だ、サルボモーターには趣味のスポーツとしての用途しか無い。ただ走る為に作られた機械に軍民の区別などありはしない。
要するに俺達が使っているものとまったく同じ機械が、国連色の白で塗装されて持ち込まれたわけだ。
「こちらでは、あなた達が先輩となりますか、よろしくお願いします。国連軍特殊装備開発局高機動ロボット評価隊のアボット中尉です。」
その若い中尉は国籍はカナダだという。国際連合から国家連合体へと名称変更されて、ついでに出来た常設軍は穀潰しとの罵声を浴びながらも着実に勢力を伸ばし、機能を強化している。
「しかし、北極に白色は無いだろう。視認しにくいぞ。」
「マーカーと標識灯を装備していますから、大丈夫でしょう。」
口調にピンと来た。この中尉、命令だからこんな馬鹿げたロボットを持ち込んだんじゃない。自分が乗りたいから志願したんだ。つまりは俺達の同類だ。
地球温暖化の影響で一度は全て消失した北極圏の氷は、揺り戻しというべきか火山噴火の影響等により、今はかなりが回復している。
だが以前のように磐石とはいかず細かい流氷が何時割れるか分からない、極めて不安定な状態だ。車両やソリでの移動は困難でもっぱら航空機に頼るか人力でとなってしまう。
そんな中、数メートルの氷のギャップを飛び越え、溺れても自力で這い上がるサルボモーターこそ適切なビークルと看做されるようになる。
しかしこの乗り物は移動する以外の能が無い。荷物は運べない居住も出来ない、両手が付いているのに作業が出来ない、おまけに装甲も無理ときてるから兵器としても役に立たない。
歩く以外の機能をすべて無視したからこそ実現した、搭乗型二足歩行ロボットなのだ。
「可愛いじゃない。」
中尉の後ろ姿を値踏みする綾子は、この馬鹿げたロボットの産みの親、ツルニハ工業の社長令嬢だ。
日本の自動車製造業界では最も小さく世界進出にも遅れを取ったツルニハが、技術力の誇示の為に作った搭乗型ロボット、それがサルボモーターの原型だ。
ツルニハの開発チームはバカだったとしか言い様が無い。他の自動車会社が次の飯の種として作業用人型ロボットの開発に鋭意努力している最中、需要をまったく見込めない搭乗型ロボットを、それも発展性の無い設計で作ってしまったのだから。
今年で30年目になるサルボモーターは、現在に至るもやはりツルニハでしか作っていない。自動車製造部門を売り払って専業になってしまった綾子の実家が今後どうなるか、すべてのサルボ乗りが危惧している。
「で。国連軍は北極で何をする気なの?」
「ゴミ拾い、だろ。俺達と同じく。」
潮が流れればゴミも来る。氷の割れ目を通って流れ込む人間の活動の残滓を回収し、しかるべき場所で処理するのが俺達の任務だ。その為に金を募っている。世界中の自然保護団体がスポンサーとして、サルボモーターの活動を支援している。
貰ったカネの分は働かねばならない。というわけで、巨大な袋をサンタクロースのように背中にぶら下げた6メートルの人型ロボットが今日も元気に走り回る。
「そうかな?」
今年で30歳の鶴仁波綾子は意外と政治的に鼻が効く。資金集めに世界中を飛び回り各国の支援者と生臭い話も交わしているから、心当りがあるのだろう。
「あれじゃないかな。この辺りには旧ソ連がなにかばら撒いていたって。」
ベンジャミン・ミン・ジャオが話に割って入る。このバカでっかい黒人はアメリカ合衆国海兵隊の出身で、極地での行動のスペシャリストだ。
身体がデカ過ぎてサルボモーターのコクピットに乗れなかったが、綾子が手配して特大コクピットを設計してもらい、御機嫌だ。彼が言うには、サルボモーターは人間が本来あるべき姿を拡大したもので、実態としては衣服であり乗り物とは認めない。服は着る人に合せるのが当然だ、と。
国連軍の機体は大した事はないが、支援装備と人員は大したものだ。
たった3機のサルボモーターを動かすのに100人もの兵隊が動き回っている。大型の輸送ヘリは現地まで吊っていくのだろう。全備重量3t以下のロボットならパラシュートで落とそうとかも考える。
日々活動費の捻出に苦労する綾子は、涎を流しながら言う。
「ちくしょうブルジョアの狗め。」
それは違うだろう、とさすがに俺も思う。
サルボモーターのどこがいいのか、と問われると大抵のサルボ乗りはこう答えるだろう。
「いや、趣味だから。」
基本的に、これは世の中に無くてもちっとも構わない機械だ。
搭乗型二足歩行ロボットの未来がどうなるか予測できないが、間違いなくサルボモーター形式は早晩絶滅する。ヘリコプターの登場で消滅したオートジャイロと同種の過渡期の発明だ。なにせ実用の方法がまったく見付からないのだから、仕方が無い。
とはいえ、ではオートジャイロで飛ぶ事に快感は無いのか、と問えばそれも否定されるだろう。同じだ。サルボモーターの歩行は面白いし、人間の感性にフィットする。否定派もこれが面白い事までは疑わない。
歩行という原初の喜びが拡大して見出せる。完全オートであるべきなのが、サルボモーターの歩行は自らの脚によるものと錯覚させる感触がある。
そもそもは原理が簡単というところが良いのだろう。
全高6メートルの巨体であるが、脚部の実態はただの板バネだ。長大な炭素繊維のバネがすっと伸びている。
これに空気圧で動く単純なアクチュエータが配置され、曲げ具合を操作出来る。故に膝関節が無い。曲り方も鳥脚の様に後ろに曲がる。
人間の関節構造とはまったく異なるこの設計は、二足歩行出来りゃいいんだろ、との開き直りの産物だ。
綾子が言うにはこれは竹馬だ。人間が上に乗って歩く竹馬を機械化したに過ぎない。だから脚はただの棒で良い。バネを使うのは自重と歩行による衝撃を受け止め蓄積し、次の一歩に集約して解放させる力のコンデンサだ。
アイデア自体は単純だが、無論制御は難しい。なにせ不整地路面を不規則に跳ね回るバネが制御対象だ。絶対に転ける。歩いたとしても真っ直ぐには進めないし、止まれない。
歩行機械として致命的な弱点であるが、ツルニハの開発者は逆転した解決を思いつく。
受け身をすればいいんだ。
柔道の受け身をロボットに教えて、転けても壊れないように機体を保つ。いや、転けた勢いをそのまま利用して体勢を立て直し立ち上がり、走り続ける。
バネだからこそ、この発想は生まれた。衝撃が直接機体に反映しないバネの脚を持っていたからこそ、サルボモーターは立ち上がる。
その為に腕を付けた。脚と同じバネ構造同じ大きさの腕、これで転倒時には地面を叩き衝撃を逃がし、機体の立ち上がりを支援する。胴体が直接打撃を受けるクリティカルな転倒でも、巨大なダンパーとなり保護する。
また大きな腕を左右に張り出して、バランスを取る。綱渡りの芸人と同じく、腕を使って機体を安定させ千鳥足を制御して直進に成功した。
デリケートな空気圧アクチュエーターを保護する為に腕脚を柔軟なカバーで覆った姿は、どうみてもビニール製のダッチワイフだ。
だが綾子はそう呼ぶことを許しはしない。
「これは日本の猿ボボと呼ばれる人形を摸したものなの。」
と、熱心に布教活動に勤しんでいる。
だから綾子の機体は深紅の手足に胴体部は黒。正面にコーポレートアイデンティティである「ツルニハ」の家紋が入っている
「つる二ハ○○ムし」と日本語で書かれたそれは、どう見てもまぬけな男の顔だ。
「せーの。」
で動き始めるのが、サルボモーターの歩行だ。両腕を振り上げて振り下ろす。その反動で脚のバネにテンションを与えて、最初の一歩を踏み出す。
実に幼稚、だがこれがいい。
ざんざんと3歩踏み出すとスピードが乗り、姿勢が安定する。回るコマは倒れないように、歩き続けるサルボモーターはそう簡単には転ばない。
ツルニハ正規の姿勢制御ソフトは悪路面での高速走行時の安定性を重点に設計されている。突っ走る為にのみ作られている。
そうは言っても北極だ、氷の上だ。平面とはいえ突起物は固く、踏み潰せない。引っ掛かって躓くのもしばしばだが、そこがパイロットの腕の見せ所。
制御ソフトの癖を見抜いて巧みにエラーを避け、路面のイレギュラーを極力回避し、真っ直ぐ走る。
この真っ直ぐ走るのが難しい。人間でもそうだが、悪路面では真っ直ぐ走らないのがセオリー。姿勢を正しく保ちながらの走行ではむしろ進路の直進性は無視するべきだが、6メートルの巨体となれば安全上そうもやってられない。
だから、熟練したサルボ乗りは自ら転倒する。横路に外れるよりは前に転げた方が機体も周囲も安全だ。レースなどでは見物人の中に飛び込まない為、敢えて機構上難しい後方受け身すらやってのける。
「うひょおおお!さすがはKING!」
「こら、意味も無いのに回転しない!」
俺の名はローリング・キング。サルボモーターで受け身を取らせたら世界一の「受身王」だ。あんまりカッコヨクないような気もするが、それで通っている。
無論KINGを名乗るからには、他人には出来ない優れた技を持っている。俺の受け身は電光石火、転んだ姿を目に留めることも出来ないの角速度で回転し、そのまま姿勢を立て直し走行を続ける。走行速度を落とさない受け身は、センスの無い奴には真似出来ない。
機体色は青地に白黒のチェスの「KING」をあしらっている。
サルボモーターはさすがに転倒を念頭に開発されただけあって、塗装も摩擦に強い。日本の漆塗りをヒントに開発されたとか聞くなんとか重合塗料は、硬い氷に接触してもまったく剥げない。剥げはしないのだが、
「うるるううぐぐう。」
綾子が目を尖らせるのも仕方ない。
転がるのがデフォルトの設計とはいえ、コクピットごと地面に突っ込むのだ。寒冷地仕様のキャノピーシールドは特注品でしかも破損し易い。環境保護団体から支援を仰いでいるとはいえ、無駄な費えの掛るバカをされては困るらしい。
「いえいぃぃぃぃ!」
「こらあ!」
ベンの漆黒のサルボモーターも転倒回転する。
子熊座の星を描いた機体は、だが誰も子熊座なんて無視するから意味が無い。折角北極星をフィーチャーしているのに「柄杓」と間違われて残念だ。
ベンと俺とはサルボ乗りとしての性質が違う。求めるものが違っている。
サルボ乗りは主に二種類に分けられる。突っ走るのが好きな奴と、動くのが好きな奴。ベンは後者になる。
元々走る為に作られたサルボモーターだが、人型ロボットがそれだけにしか使われない道理が無い。しかもゴム風船のくせにこいつは中々器用な動きが出来る。
作業には使えない。向いていない。直立するだけでぶるぶると震える機械に精密作業が出来るはずがない。
にも関わらず、至極便利に動くのだ。
例えば格闘。
世の中に格闘する機械なんてありはしない。モンスタートラックをぶつけ合う娯楽も存在するが、所詮は自動車。人の考える格闘の概念からはるか遠くに位置する色物だ。
サルボモーターだとて格闘を想定して開発設計されたわけではない。無いのだが、
「うりゃ。」
綾子のお仕置きパンチがベンの機体に入る。
地面に全速力で突っ込む機体を受け止める腕、激突しても破損しない胴体、搭乗者を完全に保護するコクピット、地面をぶん殴る為に作られた手足末端、CNTラバーで覆われた風船腕脚カバーの靱性と弾力。これすべてサルボモーターに打撃攻撃をせよと訴える。
ただ走る為に備わった機体特性は、真っ正面から格闘を指向していた。
走行中に殴られたベンの機体は横に飛ぶ。左手を地に着いて、横回りに回転する。さすがに速度は落ちるが順当に機体姿勢を立て直し、わずかの遅れで俺達を追随する。
「さすがに横は来るな。びびっと脳幹に来た。」
「ちょっとは暖まったでしょ。」
北極での使用を念頭に改造された俺達の機体は、だがコクピットの暖房は付いていない。あえて付けなかった。シールドが曇って前が見えなくなるというのもあるが、外部と同じ空気、北極の風を感じることなく氷原を走っても意味が無い。
というわけで、暖房は個人装備の防寒服にのみ存在する。最近の服はさまざまな電子機器を用いる為に太陽電池を仕込んであるから、防寒服とはいえこれだけで極地探検できるほどの優れものだ。乗り物が破損し動けなくなっても、多分大丈夫という事になっている。
だから、サルボモーター本体に搭載される情報機器には大したものは無い。まあ、スポンサー様の為にインターネットで中継するカメラくらいは積んでいるが、さすがに極点。電波障害も多くて「常時接続」しなくて済む。
「お。」
赤外線レーダーが飛行物体を発見する。先程の国連軍のヘリだ。俺達が今走っている場所の西10キロの地点から離陸した瞬間、らしい。
「連中、なにか目当てが有って来たみたいね。」
「ああ。ピンポイントで降りやがった。」
「やはりヤバい代物を回収しに来たんじゃないか?」
しかしどうせ持っているのはおとといの地図だろう。現在の北極は日毎に地形が変わる。朝に通った道が夕方には割れた氷の水道で隔てられる。
だからこそサルボモーターを持ち込んだ。限定的ではあるが、これならば海も渡る事が出来る。
「どうも、レーダーの画像がおかしいね。」
「ヘリが帰らないな。上空で旋回してる。なにか引っ張り上げてるのかもしれん。」
落ちたかな、と感じる。最近良くある事故だ。磐石に見える氷の上に機材を下ろしたら、何故かそこから割れて海に転落する。一度出来た水道の上に雪が積もって氷になり平原に見えるから、騙される奴も多い。
とにかく地球温暖化の影響は凄まじい。最近ようやくに太陽光レーザー発電衛星が出来たから救いもあるが、この50年人類はまったく何も手を打たなかった。そのツケを存分に払わされている。
「まあ助けにいかなくても大丈夫だろ。あんだけ支援設備が揃ってるんだ。」
俺の意見に二人も従う。こっちはこっちで適当にやる。
当初の計画に従って1時間半走る。と簡単に言うが、サルボモーターで走るのはひどく神経の疲れる作業だ。
割れて水没の怖れがあるから、だけではない。どこで走っても、アスファルトの路面であってもやっぱり同じくらい疲れる。長距離走行自体を看板に掲げる者すら居る始末だ。
もちろん自動操縦機能はあるのだが、そんなものに頼っていてはサルボ乗りとは言えない。
まあ綾子には悪いが、ツルニハ謹製の自動操縦機能は本当にアスファルトのみでしか使えないから、悪路ではやはり個々のパイロットの技量がものを言う。
ざくざくと氷を踏みしめて歩く足元は、北極圏仕様の特殊シューズ。硬い氷原、積雪で柔らかい路面、さらには氷が弛んで溶け滑る路面にまで対応出来る。
無論これは俺達専用というわけではない。30年の長きに渡り先人が至る所でサルボモーターを使いバカを繰り返して来た、努力の結晶だ。
サルボモーターのシューズはつま先と踵が分かれており、踵が軟路面では二つに分かれて接地面積を稼ぐようになっている。「ラクダの蹄」と呼ばれ、砂漠で中東の王子様が遊んで回った恩恵で、俺達もこのややこしい足を使う事が出来る。
氷に突き刺さる短いスパイクは踏み出しの衝撃で効率的に撃ち込まれる機構がゴムの蹄に仕込んである。それでも滑った場合には、逆にスパイクが引っ込んで氷に吸着するタコの足みたいな部分も有る。南北の極地は昔からサルボ乗りが目指すフィールドで、たまに命も落しながらもここまで鍛え上げて来た。
サルボモーターの魅力とは、この未完成さにあると言っていいだろう。至極手間が掛る、故に面白い。
「ちこちこちこちこ。」
と綾子が口ずさみながら走るのも、その手間の一端だ。一歩ごとに接地する場所を探して、小さく歩を刻んでいる。
だがパイロットに制御可能なのは足を踏み下ろす角度のわずかな修正、前か外にほんの少しずらすだけだ。時計の振り子と同じくリズムを取って脚が前後するサルボモーターには、自由度は無いに等しい。
足に連動するペダルの感触を確かめ、コンマ2秒ほどの時間内に接地位置を決定する。これを両脚別に、延々と繰り返すのだ。疲れない道理が無い。
まあ慣れの問題もあり、やばそうな時だけ足が勝手にペダルを操作してくれるのだが、やはりセンスの問題と言える。そして何より必要なのが、
綾子は叫んだ。
「にゃああ!」
転倒を怖がらない勇気だ。家の二階から地面に向けてコクピットが真っ直ぐ落下する恐怖、しかも顔面から、に耐えられる者はそうは居ない。いかに強固なシールドがあるとしても、地面に頭を突っ込んでいく姿勢は死そのものへのダイブであろう。
しかしこのおもちゃはこれで正しいのだ。コクピットのシールドは大抵の場合接地せず潜り込み、背中のかまぼこ形のダンパーで綺麗に回り、速やかに正しい直立状態に復帰する。そういう運動をするように設計されている。
転倒の衝撃は板バネの脚がそのまま前に曲がって吸収し、起立後の次の踏み出しエネルギーへと転化する。
怖れなければ、サルボモーターを信じていれば、正しい運動で機体にダメージを残す事は無い。信じられない奴は思わずブレーキを引いてしまい、転倒のエネルギーをすべて受け止め破損させる。
「おお、やっちまったよお。尖がった氷がシールドの顔んとこでバリンと割れたよお。」
「氷はやばいぞ。たまに突き破るからなあ。」
言いながらも、俺達は氷の割れ目に覗く北極海を飛び越えた。
歩くのは脚だ。だが跳ぶのは腕だ。腕を振り上げ振り下ろし、その反動を脚のバネに吸収させて飛び上がる。
歩行の衝撃が腕のバネを振動させ、固有の周波数で震え続ける。低周波が常に発生し、操作するパイロットの手ににフィードバックされている。
機体によって振動数は変わるし、パイロットの生理的なリズムに合わせて執拗なまでに修正する。調律を繰り返す。
これが上手くいくと、サルボモーターは自分の手足同然の鋭い反応を示してくれる。魂を得たように動き出す。
或るアーティスト崩れのサルボ乗りが言っていた。
「サルボモーターは大地と共に奏でる音楽、楽器だよ。」
俺もそう考える。ガソリンエンジンが載っていた昔のモデルであれば、なおさらに感じられただろう。
目的地は幅が30メートルになる大きな割れ目、水路だ。
昨日の天気予報と海中の潮流から推測して、ここに現われるだろうと睨んでいた通りにある。自慢はしない。コンピュータシミュレーションの成果だ。
そして予想通りに白いゴミが無数に浮いている。
主にプラスチック、ビニール、木切れ。棄てられた漁具も多い。もちろん北極海は漁業禁止だが、違法操業を行う船は後を立たず、ゴミも盛大にばら撒いていく。
「中国、韓国、ロシア、日本、アメリカ、フィリピンetcetc。」
「綾子、この文字はアラビア語かな?」
「いえ、タイだわね、それ。」
とにかく世界中のゴミが有る。北極海でこの有り様だ、世界の海がどうなっているか言うまでも無いだろう。
しかも、今は戦争中と来たもんだ。太平洋全域に拡がる海賊が至る所で破壊と掠奪を行っている。北極だとて例外ではない。
ゴミの中にはごく稀に機雷や爆弾、不発弾も混ざっている。海兵隊出身のベンはそれらを見分ける為に今回のゴミ拾いツアーに付いて来た。
「じゃあ、お仕事始めましょうか。」
俺達はそれぞれのサルボモーターから降りて、腹部のトランクを開けた。中からゴミ拾いの道具一式を引っ張り出す。
念の為に言うと、サルボモーターは作業用機械ではない。作業なんか出来ない。そんな便利な機械じゃない。
しかし人間が出来ることはあらかた出来る。水上のゴミを拾うとなれば、人間と同じように、
「タモ取りつけ完了!」
特大のタモ網を使う。
サルボモーターの手は足のシューズとほぼ同じで、作業もモノを持つ事も出来ない。が手の横に付いているフックに括りつければ、理論上何でも使える構造だ。
人間に換算すると3人力、てのが大体の通り相場だ。6メートル2トン半の機械がそんな非力でいいのかと皆笑うが、これがサルボモーターだ。
右手のタモを伸ばしてゴミをすくう。膝を折らねば坐れないが、生憎サルボモーターに膝は無い。
ダンパーのエアを抜いて、脚は降着状態にする。立っていればふらふらする機体でも、さすがに地面に下りれば安定する。
インターネットで俺達のリアルタイム動画を見ている奴は、さぞ笑っているだろう。
ダッチワイフみたいな手足のロボットが、氷に片手を突いて上体を伸ばし、ゴミをすくっている。やってる本人が笑うのだから他人はなおさらだ。
で、当然、
「うわあああ。」
落水する。ベンが北極の濃い塩水に落っこちた。
だが問題無い。手足が風船のサルボモーターは沈めない。この風船手足はただの保護カバーではあるがCNTラバーという強靱な材質で作られており、拳銃弾程度であれば弾いてしまう。氷の角にぶつけても破裂しない。
落ちたのを幸いに、ベンの黒いサルボモーターは効率良く水面のゴミを拾い始めた。一度落ちた者は度胸が座る。
反対に、綾子は海水の機体への影響とメンテナンスの費用を考えて額に皺を作ってるだろう。
ベンが寄せ集めたゴミを、氷の上の俺達がすくう。計画の30倍の速度でゴミ拾いが完遂される。やはり犠牲を怖れていては何事も為し得ない。
「ミサイルがあるぞ。」
「え?」
「おいほんとかよ。」
全長150センチほどのオレンジ色の物体だ。ロケットモーターは原型を留め、ミサイルだと判別出来る。
「不発弾か?」
「違うみたいだ。というよりも、俺はこんなミサイル見た事無いぞ。」
海兵隊出身のベンの言う事だ。間違い無かろうが、しかし俺の常識からみてもこのミサイルは変な形をしている。なんというか、古臭い。
綾子も言う。
「子供の絵本に載ってるようなミサイルね。」
「ひょっとして20世紀のものかも知れん。頭部が破損しているから爆発の危険は無いだろう。揚げるぞ。」
水に浮いているくらいだ、それほど重くはない。ベンが寄せたものを俺達二人で持ち上げた。タモはなかなか便利だ。
綾子がコクピットから降りて、調べる。その間にベンはサルボモーターを氷の上に引き上げた。水中から自力で上ってみせるのが、サルボ乗りの腕だ。
「ロシア製、…いえこの表記は、」
「ソビエト連邦だよ。」
「ソビエト、ってあの20世紀史に出て来るアレ?」
俺も良くはしらないが、かって地球にはソビエト連邦という国があった。アメリカと対峙し世界を二分する超軍事国家だと聞く。北極海はソ連に面していたから、その遺物だろう。
ベンもサルボモーターを座らせて、コクピットから降りて来る。破損部分から内部を覗いて、言った。
「ミサイルじゃないな。人工衛星かも知れない。」
「じんこうえいせい?こんな小さいのが?」
「いや、これカメラだろ、レーダーだろ、制御装置があって、もうエンジンだ。爆薬積むスペースが無い。」
「でもこんなに小さくちゃ、大気圏突破できないでしょう。」
「それはそうなんだが、」
電子部品がごっそりくっついた基板から、外れ掛けてた毛虫みたいなのを引っこ抜く。昔懐かしのLSIて奴だ。今の機械ではほぼ見掛けない。
「”MADE IN CHINA”?」
サルボモーターから降りていた俺達は気付かなかったが、その時遥か遠くの南方に軍用大型ヘリが飛んで居たらしい。
それは俺達の方に真っ直ぐ進路を向けて、低空を突き進む。
今時の軍用ヘリだから電波・赤外線ステルスもそれなりに完璧だ。国連軍が存在する領域に進出するのだから警戒はしていたのだろう。
目の前に降りられるまで本当に気が付かなかった。静音ローターを備え、ただでさえ氷原に光が乱反射する北極で映像カモフラージュまで使われては、民間人がどうこう出来るはずも無い。機数は2、エスコートに無人低速域戦闘機も付いて来る。
その間俺達が何をしていたかと言うと、一生懸命拾ったゴミを袋に詰めていた。
サルボモーターのトランクは狭く、支援装備だけで満杯。サンタクロースみたいに袋を担がせて外部に積載する事となる。
袋を担いだ状態では転倒・受け身はやりづらい。帰りの方が技量を要求される。
拾ったミサイルらしいものの処分は、考えあぐねていた。紐で引っ張るか、機体に括りつけるか。重たいから電波タグでも付けて放っておいて国連軍に任せるか。
悩みはあっさりと解決する。
「ろ、ロシア軍、ね。」
「極地専門の特殊戦闘部隊だ。」
「参ったな。」
20人ばかりの白色の倍力耐弾スーツに身を固めた兵士に包囲される。手にするのはグレネードランチャーが一体化した低反動対装甲ライフルだ。サルボモーターに穴を開けるには大袈裟過ぎる威力を持つ。
ロボットまで出てきた。ヘリの尻のカーゴハッチが開いて、段ボール箱を組み合わせたみたいな装甲のロボットアーマーが2体も降りて来る。
全高250センチ、サルボモーターの半分にも満たない。脚部に大きな車輪が付いているから高速走行も可能だ。足と車輪は相反する存在ではなく、回転を微妙に制御して「車輪で歩く」事さえ出来る。
「25ミリなんてこっち向けるなよ。」
軍人はどういうわけだかサルボモーターに異様な警戒をする。一般2トントラックの方がよほど物騒な戦闘力を持つだろうに、手足があるからと過剰な武装で制圧を試みる。
世界中どこに行ってもこうだ。
行き掛かり上、綾子が部隊指揮官と交渉する。彼女はサルボモーターの納品に世界中を駆け回ってるから、何ヶ国語も素で使える。ロシア語も翻訳機を必要としない。
だがうまくは行かないようだ。
俺とベンは防寒服の付いているコンピュータで同時翻訳を聞いた。どうもあのミサイルはロシア軍に所有権が有り、極めて高度な軍事機密なのだそうだ。
綾子は必死で弁明、というよりも抗議を繰り広げる。北極海を汚すなばかやろうとか言ってるが、まあその理屈は通らないだろう。
それにしても、ソビエト連邦製のミサイルとなればもう半世紀前の骨董品だ。
そんなものにまだ価値が有るのか。連中も必死で探して見付けきらなかったモノが、何故今頃簡単に出て来るのか。
この部隊もこれほど迅速に出動出来たのは何故か、疑問は山ほど浮いて来る。
兵士達は折角サルボモーターに積んだ袋を引きずり下ろし、氷上にゴミをばら撒き始める。複合センサーで調べているのだから中身がただのプラスチックだと分かるだろうに、念入りに散らかす。
一応サルボモーターにも北極熊対策に銃を積んでいるが、見つかっても大丈夫だろうか。
「こいつら、後でゴミ拾いしないよな。」
「賭けてもいいが、そのままだな。」
技術士官らしい奴がミサイルを調査するも、なにかおかしな素振りを見せる。他に部品が浮いていないか、氷の割れ目に覗く藍色の海を指し示す。
段ボール箱ロボットアーマーが2機とも動き出し、氷の上を徘徊する。これら軍用ロボットには高度なセンサーが搭載されており、
「あ、」
落水した。言わんこっちゃない、あんな重たいものが動き回るのに、現在の北極は向いてないんだ。ばっきり割れた氷の塊と共に2機一緒に飛沫を上げる。
ちなみにサルボモーターはゴミ等担いで最大3トン、ロボットアーマーは弾薬積まない空重量で5トンも有る。
突然の事故に兵士は俺達を放ってロボットアーマー回収に集まる。これがまずかった。
落水事故をロボットアーマーが考慮していないわけじゃ無く、緊急に展張されるフロートが装着してあった。防弾機能さえ持つ丈夫な袋が高圧ガスで膨脹する衝撃に再び氷が割れ、兵士も海に落っこちる。
部隊指揮官がロシア語で「なんてこったい!」と叫ぶのを、俺は翻訳機能無しでも理解する。
綾子の顔を見ると、肩をすくめて来た。まああちらも北極のプロだから、こんな時どうすれば良いかぐらいちゃんと考えているだろう。
しかし、
「流氷の下に、ロボット潜っちゃったね。」
「下手に暴れたからなあ。潜水能力あるんだろうか、アレ。」
現在の装甲ロボット兵器は全天候型だが、水中にまで潜れるものは多くない。太平洋上では現在日本とアメリカの連合軍がさんざん海賊と戦っているらしいが、これに参戦していないロシアならその種の兵器の必要も無いだろう。
つまり、ロボット可哀想な状態が続く。
ベンは米海兵隊出身なだけあって他国の兵器にも詳しい。サルボ乗りであるから、一応は人型ロボットの技術情報にも目を通す。
「あのロシアのロボットな、型式はRG-08とかいうんだけど、第三世代型の戦車を撃破するだけの能力はあるんだよ。キネティックミサイルを搭載して。」
「凄いんだね。」
「今って第五世代戦車じゃなかったっけ?」
「装甲で着膨れているけれど、一応は手足があってどこにでも進出できる事になっている。実際タジキスタン紛争で投入されて対ゲリラ戦で赫々たる戦果を上げてるんだ。」
「ま、ヘリで積んで来れるくらいだから、展開力は大きいんだろうな。」
2機一緒に落ちたのは痛恨の一事に尽きる。どちらか上に残って居たら簡単に引き上げられただろう。
またこんな割れやすい氷上でなければ、ヘリコプターを使って吊上げられたかもしれない。だが彼らに残された手段は唯一つ。
「人力で引っ張ってやがる…。」
「見ちゃいられないな。」
見かねて綾子が立ち上がり、指揮官の所に行く。お人好しなことだ。
「あの、お手伝いしましょうか?」
改めて言っておこう。サルボモーターは何の役にも立たないロボットだ。
作業に使うマニュピレーターが付いてないし、重量物を抱え上げる事も出来ない。積載量は200キログラムがいいところ、牽引すればすっ転ぶ。そもそもが安定して静止する直立すら出来はしない。
だがそれでも機械だし、出力は同重量の自動車と同等にある。熟練したサルボ乗りが使えば、冗談のように器用な動きを見せる。
ロシアの指揮官の許可の下、3機のサルボモーターが立ち上がる。綾子の赤は氷上で牽引し、俺達は水の中に入っていく。
もちろん、サルボモーターだって水中に潜る事は出来ない。水上を移動する為のウォータージェットもスクリューも付いてない。手足をじたばたさせて泳いでいる。
こんなバカな使い方をメーカーであるツルニハは想定していないから、水中運動制御ソフトも開発していない。
だがソレが有る。動いている。
世界中のロボット研究者、車両設計技術者、コンピュータ技術者、マニア、おたく、その他サルボモーターに興味を抱く人間が寄ってたかってあらゆる環境で動くようにしてしまった。世界で唯一民間人の手の届く搭乗用人型ロボットは愛されているのだ。
氷の下に潜り込んでしまったロボットアーマーを引っ張り出す手段を、サルボモーターは持たない。そもそもが掴む指が無い。
しかし俺はやった。2本の脚を巧みに動かしてロボットアーマーの機体を鋏込み、両腕をじたばたさせる。ベンの機体が流氷をパンチで破壊して、フロートが水面に出る手助けをする。
俺はコクピットシールドを開き、外に出てワイヤーを掛けていく。
氷上の綾子が引っ張り上げる時には、俺達は一度自機を水中に沈めて、足場にしなければならない。手足の空気圧を調整して浮力を減少させる。こんなことをしても転覆沈没しないのも、バランス制御こそが最重要の機械ゆえだ。
「せーの。」
綾子が転んで再度ロボットアーマーを沈めたら、もう取り返しがつかない。牽引は慎重に一歩ずつ確実に足に荷重を掛けて最大限のトルクを引き出していく。氷を割らない注意も必要だ。
ロシア兵も左右に分かれてワイヤーを引っ張るが、またぞろ落水しかねない。いや、綾子が転べば絶対彼らを巻き込んでしまう。
サルボモーターは後ろには引っ張れない。前を向いて背中にワイヤーを接続する。手を地面に突きながら、一歩ずつゆっくりと進む。
慎重に、安全に、脚部の空気圧を絞り込んで機体重量を長大な板バネに吸わせていく。足のシューズが展開して氷にスパイクを打ち込み、食らいつく。曲がったバネの脚がじんわりと伸びて、機体は数センチずつ前に進む。
ガリガリと氷を削る音を立てながら、ロボットアーマーは持ち上がる。硬いセラミック装甲が氷を斜めに削り上げ、かき氷の煙を吹き上げた。
足場となって機体を沈めている俺達も空気圧を増やして、ゴム風船の手足を膨らませる。
「よし!」
完全に氷の上に引き上げたと見極め、手を放す。ダメ押しにもう一度機体を水中に沈めたベンが浮上する勢いを使って、突き上げた。
はらしょーとかすぱしぼーとかの声が上がるが、もう1機有る。今度は楽だ。先に引き上げたロボットアーマーをアンカーに使えば、綾子の牽引は至極簡単になる。
5分で次も引き上げた。自分で言うのも何だが、よくやった。残る難題は自機の引き上げだ。
ロシア兵はこれからサルボモーターがどうなるか、雁首揃えて見守っている。既に引き上げたのが有るのだからロボットアーマーで引き上げよう、とか考えるだろうが、それは剣呑。うろつき回ってまた氷を割られては災難だ。
ベンが俺の足場になる。無くても出来るのだが、これもデモンストレーションの一手法。さっくり上がれば拍手喝采!
「よ。」
氷の上に上げた両手で、機体の上半身を持ち上げる。ここまではどんなロボットでもやるだろうが、これから脚を陸に上げるのが大苦労だ。しかしサルボモーターは。
「よっと。」
コクピットガラスが氷に接触する。前転だ。持ち上げる代りに前に転がる事で、機体全部が陸に上がる。大きく水飛沫が弧を描いて、白夜の空に舞上がる。
前に転べば、脚の板バネは前に曲がる。回転力がバネに貯えられ、空気圧アクチュエーターで補助してやるとそのままの勢いで立ち上がる。
大きく振り上げた両手でバランスを取り、静止して完了となる。
まあ、賞讃の声という奴は何語でも嬉しいものだ。
俺達に助けられた特殊部隊の指揮官は、最大限の謝辞をロシア語でなく英語で言ってくれた。が、向こうも商売だ。
サルボモータはすべてコンピュータの記録を検査され、拾ったミサイルに関連する映像や音声、座標データ等々一切合財を消去していった。生憎とネットに繋いで配信していなかったので、まったく何も残らなかった。
ついでに起った事を口外しないと確約させられた上で、彼らは笑顔で去っていく。輸送ヘリの吹き降ろす風でまた氷が割れて、帰り道の足場が分からなくなってしまうが、大雑把な連中は気付かなかっただろう。
もちろん散らかしたゴミを片付けようとはしなかった。俺達3人は必死になって氷上に散らばるゴミを集め、袋と網に詰めていく。この作業だけで3時間も掛った。
ベースキャンプの有る頑丈な氷塊に戻ったのは、出発してから27時間後。予定を12時間もオーバーする。
俺達を出迎えたのは、国連軍の中尉さんだ。
「やあ、さいなんでしたね。」
「…なにが起ったか、ちゃんと御存知のようだな。」
「やあ、ハハ。ちょっと責任感じてしまいますね。」
アボット中尉はもちろんロシア軍の出動とその目的を知っている。おそらくは、彼らが回収したミサイルについても詳細が分かっている。
「で、あれはなんなんだ?」
「潜水艦発射偵察衛星です。水中から発射されるミサイルの弾頭が、偵察用になってるんですね。」
「なんでそんなものが、宇宙から人工衛星で見ればいいだろ。」
「それは当時の状況を知らないから、簡単に思えるんですよ。」
つまりソビエト連邦崩壊直前の軍事バランスだと、敵国アメリカによって軌道上の偵察衛星がすべて駆逐される可能性があったそうだ。もちろんソビエト側も同じ事をする。
敵の状況が分からなくなるから、一度きりの使い捨てで弾道飛行しながら敵領内を偵察する機械が必要になった。落とされる前に使命を終える人工衛星だ。
「アイデアはいいのですが、開発時期が悪くて数回の試験発射のみで計画は放棄されました。あなた達が見たのは試射に失敗して墜落した残骸です。」
「今も最高機密扱いなのか、アレ。」
「そうみたいですね、50年前の機械なのに。」
「だが中国製の電子部品を使っていたぞ。」
中尉は俺の言葉に左の眉を上げて応えた。確信する。あのミサイルはこいつがあそこに置いてきたんだ。
共産主義国家時代の中国で電子部品産業が興ったのは1990年代。91年に崩壊したソビエト連邦の、しかも最高の技術を要する偵察衛星に中国製の部品が使われている道理が無い。
使われているロケットモーターの方にも見覚えがある。旧設計のまま延々と作り続けるルーマニアのメーカーの製品だ。中古のサルボモーターに組み込もうとした事があるから、間違い無い。
つまり俺達が見付けたアレは、レプリカだ。アボット中尉が、いや国家連合体が未承認のロシアになんらかの脅しを掛ける為にこしらえたわけだ。
だが50年前の機械になんらかの軍事的価値が残っているのだろうか?
中尉はにやにや笑いながら雑談を続ける。
「ロシア人てのは物持ちがいいんですねえ。アレに使われている通信システムの根幹は30年前まで残っていたんですよ。00年代までロシアは貧乏でしたから、システムを抜本的に更新する資金が無かったんです。」
「30年ももう二昔だろ。」
「いやいや、たった30年です。その頃の通信傍受のデータがちゃんと残ってます。現在の世界状況を作った痕跡がばっちりと。」
「ふうん。」
現在の地球の破滅的状況を引き起こした責任の一端は、資源大国としてエネルギーを掌握していたロシアにもある。
突かれるとまずい古傷が、ここ北極海にはまだまだ眠っているらしい。
「で、あなた達はどうします。私は1ヶ月ほど北極で探査任務を続けなければなりませんが、」
1ヶ月給料をもらいながらサルボモーターでお楽しみ、という羨ましい身分というわけだ。温厚な俺でもさすがに腹が立つ。
怒りは綾子も同じだ。中尉との会話を聞いても裏は分からなかったろうが、女の勘て奴でこいつが胡散臭いと気付いている。
「いえ、私達の活動は今週で終わりです。次はEUのとある筋からの依頼でアマゾンに潜ります。」
「アマゾンですか、あそこは今は良くない。海賊が逃げ込んでいるとの噂ですよ。」
「だから行くんです。密林の未発見現住民の安否を確かめに、ついでにゴミ拾いに。」
ちなみに密林でサルボモーターを動かすのは、地獄の苦しみを伴う。北極の氷原が天国みたいに感じられるのだが、まあ頑張るよ。
第二歩 密林のサルボモーター
「長い事この商売やっているが、こんな妙な機械運ぶのは初めてだよ。」
河下りのハシケのおっさんは煙草を燻らせながら言う。タバコの原産は南アメリカだから、喫煙根絶運動も関係無いのだろう。
北極から帰った俺達3人は休む間もなく南米はアマゾン川流域に向かった。
休まないと言っても北極仕様のサルボモーターをまるっきり反対の密林湿地帯仕様に変更するのに時間が掛る。そもそもが北極から撤収するのに貨物船を使ったから、それなりにのんびりとしたものだ。
しかし船旅はこの頃は物騒で、ただの貨物船といえども安心は出来ない。遠洋を航行すると海賊に襲われるから、米軍の管轄下にある北米西岸沿海を通っていく。
航路が定まると船が集まる。ひっきりなしに行き交う船の列に、今世界で何が起きているかよく分かった。
ツルニハのサポートチームに連絡し、ヴァンクーバーで機材を積み込むとそのまま船上でサルボモーターの改装作業を始める。試運転は出来ないがそれなりにまっとうに仕上がった。
その間綾子はひとり船を下りて、飛行機であちらこちらに飛び回る。
彼女はツルニハの広報部長級ヒラ社員として、世界中のVIPに機体を納入する手伝いをしている。
なにせ生まれた時からサルボモーターの宣伝をやってたのだ。その筋では知らぬ者の無い広告塔である。納入時彼女が来ないと承知しない困ったさんも居ると聞く。
なにを隠そう俺達も、その広告塔をサポートする「チーム・ツルニハ」のメンバーだ。
広告宣伝費をほとんど掛けないツルニハは、実際にサルボモーターを動かした映像を配信し代りとする。北極の次にアマゾンの密林という強行スケジュールもその為だ。
俺達だけじゃない、一般ユーザーの活動も宣伝になる。
中東の王子様とかが大暴れしてくれると、メンテ代向こう持ちでいい絵が撮れて宣伝になる寸法だ。実にせこい。
とにかくサルボモーターは実用がまったく無い単なる趣味のおもちゃだから、ユーザーの興味を惹き付けねばならない。停まったらそこで終るサメみたいなビジネスだ。
メキシコから南に真っ直ぐ下り赤道を越えると、なんだかきな臭くなる。戦闘は行われていないはずなのに、船員の顔付きが変わり空気がぴりぴりする。
「海賊は中国船だけじゃなく、地元の武装船も居るらしい。」
全体的に襲撃が頻発すると、参入を試みる部外者も居るわけだ。
ツルニハの技術者は船でなくカーゴジャイロという飛行機でサルボモーターを運ぼうと言い出した。
これは輸送専門の電動ヘリコプター、いやオートジャイロみたいなものだ。5~10トンの積載能力がある。50メートル四方空き地があれば離着陸できる優れもので、おまけに燃費がバカみたいに安い。長距離トラックの3倍ほどしか掛らない。
時速は120キロ、航空機としては論外の遅さだが滞空時間は10時間以上、しかも無人で運用出来る。人間を乗せないから安全装備を省くことが出来、機体の価格も運用コストも安くなる。
国連軍が難民支援を行う際も、こいつでコンボイを作って飛んでいく。先導機のみ有人で貨物は全部無人だから楽なものだ。世界中で頻発する災害や紛争の救援に大きく役立っている。
が、文明の利器には副作用も伴う。地形を無視して安価な物流が可能となった結果、これまで人の入らなかった僻地にも開発の手が及んでしまう。
今回俺達が赴くのもそんな土地だ。アマゾン河の最深部、本来ならまったく経済的価値が無かったはずの場所に不法に人が住み着いて森林を破壊している。パナマ運河を通らなかったのも、ペルーからカーゴジャイロで山越えするつもりだったからだ。
どうせ飛ぶなら内陸を飛べばいい、というが空中にだって賊は居る。無人機相手と見て無茶をする輩も少なくない。
海の上ならまだ護衛となる艦船があるが、空中の護衛となると大事だ。無人低速域戦闘機なんて結構なものを配備している国はここら辺りには無い。
「違法に人を乗せているカーゴジャイロも有るっていうじゃないか。どうするんだそういう時。」
「いやもう諦めるしかないんじゃないかな、それは。」
「いっそのことサルボモーターにローター付けてみるてのはどうだろう?」
ベンの冗談にツルニハの技術者はおおと手を打った。瓢箪から駒で、数年後ローター付きサルボモーターが出来るかもしれない。
ペルーに着いたらすでに綾子が待っていた。カーゴジャイロの手配も整えている。
「遅いじゃない。」
「船が遅いのはあたり前だ。サルボモーターで歩いて来るよりずっと早いぞ。」
「うう、それは言わないで。」
カーゴジャイロは積載量5トンタイプで2トン半のサルボモーターなら楽に載る。ただ手足を畳んでコンテナに突っ込むのが少し厄介だった。有人機1、無人機2の構成で飛び上がる。
有人機は人間が乗るだけあって結構まっとうな航空機だ。ジェットエンジンもサブで装備してあり、200キロ以上スピードも出る。
「飛んでくのはいいけれど、下に住んでる人は大迷惑ね。」
窓の外を眺めながら綾子が言う。
カーゴジャイロはあまり高度を上げられないから、山岳地帯を飛ぶ時は飛行ルートが決まってしまう。機構上墜落し辛いのだが数があれば幾つかは落ちるし、上からゴミを棄てる奴も居る。道の下になってしまった人は理不尽な被害を被っているだろう。
ペルーの密林のど真ん中がキャンプ地だ。ここはカーゴジャイロの荷物集積所となっており、結構栄えている。ただ森林を無計画に切り拓いた感じがして、上空から見た限りあまり健全には思えない。
ここでサルボモーターの手足を伸ばし最終調整をして、目的の未踏の奥地に踏み込んでいく。
が、問題がひとつ有る。サルボモーターはそれほど燃料を詰めないのだ。バイオエタノールを用いる燃料電池が動力なのだが、いいところ一日分しかタンクに入らない。
俺達はエコを名目に活動を行っているのだが、実際はそれほど地球に優しくなかった。
「ま、それも計画の内だわ。」
と綾子は涼しい顔で諦めた。カーゴジャイロのさらに小さい郵便用のを使って、燃料を上から投下する。
それでも燃料タンクが廃棄物として出てしまうのだが、これはキャンプの焚き付けに使う。紙パックで生分解する燃料タンクってのは、かなり物騒な代物だな。
浅黒い肌をした現地の野次馬が大勢集まる中、俺達は活動を開始する。地面の上でサルボモーターを動かすのも1ヶ月ぶりだ。
今回機体色は密林で目立たないように迷彩塗装している。単純にペンキ塗っただけだから、この旅でぼろぼろに剥げてしまうだろう。
綾子の機体にだけは正面に映像ディスプレイを装着している。機体から下りなくても原住民と交渉ができるようにした装備で、この集積地に待機する通訳が応答する手筈になっていた。
立ち上がる3機のサルボモーター、6メートルの巨人が歩き出すと野次馬は大騒ぎだ。テレビやインターネットでは見た事があっても、実物は初めてだろう。なにせ世界に2万台しかない。
ぐりんぐりんと腕を振り回して調子を試す。意味もなくその場で高度な技術を必要とする後方受け身をやってみる。
野次馬は瞬時に、この機械は近付くとヤバい、と理解したようだ。子供たちがいきなり親に後ろに引っ張られて近寄るのを禁じられる。
ベンがくいくいと腕で示すので、どんと右手でぶん殴ってやった。ベンの機体は密林迷彩の上にも律義に仔熊座を描いてある。
殴られたショックで機体が大きく傾きぐるっと旋回して、その反動で脚を浮かして回転飛び蹴りをする。もちろん宙を斬っただけだが、野次馬は凄いものを見たと目が点になっている。
うん宣伝効果抜群だ。
「じゃあいくわよ。」
「おう。」
「ジャングルクルーズと決め込むか。」
サルボモーターは大きな機械である。体積と重量は大したことないが、ともかく高い。だから普通、林の中なんか通れないと考える。
サルボ乗りだってそうだ。広い場所で走り回るのが本来の機能と理解する奴が半分、だが残りは薮の中こそサルボモーターの神髄を発揮する場所と心得る。
他の機械や箱型ロボットと異なりサルボモーターは腕脚がゴム風船状になっている。肘膝の関節も無い。柔軟に障害物を跳ね除ける構造だ。
強度も高い。CNTラバーで作られた薄いカバーは拳銃の9ミリホローポイント弾を止めてしまう。
柔軟かつ強靱。この腕脚があればこそ、密林でロボットを動かそうと考える。
「よっこらしょ。」
おばさんくさい声を出しながら、綾子がサルボモーターを林に乗り入れる。樹が生い茂り下草も絡みついて、人間であっても通るには困難な場所だ。
だが、難無く機体は入り込む。
実際にやってみると分かるが、十分に成長した樹々の中では6メートルの身長は決して大きくない。いやむしろ小さい。
姿勢の関係で脚は常に湾曲しコクピットも前傾した状態で進むから、せいぜい4メートル半という高さにしかならない。これは一番下の枝の高さでしかない。
しかも足元の低い草木は、サルボモーターの脚にしてみればかなり低い。ざくざくと上から踏みつければ、邪魔というほどの抵抗も無かった。
森林破壊ではないかと考えるだろうが、車両に比べれば本当に問題ない。根を斬るように進む車輪と違い、一足ごとに荷重を掛けて歩くサルボモーターは致命的な損傷を与えない。
では上はどうかと言えば、大きな樹にとってサルボモーターは軽過ぎるのだ。時速40キロで激突すれば折れる事もあろうが、風船腕で寄っ掛かったくらいではたわみもしない。
そして丈夫な樹々を手掛かりに腕で漕いでいけば、簡単に前に進むのだ。
最後まで付いて来た野次馬の声が聞こえる。ロボットがこんなに簡単に密林に進入できるとは、彼らもまったく想像しなかっただろう。
あっと言う間に集積所が遠くなる。森林中でのサルボモーターの移動速度は時速10キロ、凄まじい早さだ。
しかしこの速度では未発見部族が居るという密林の最深部にはなかなか辿りつけない。そこでショートカットの山越えをする。
「地図の上では崖があるはずなんだけど、」
「あれだろう。」
「あれ? 嘘。」
2時間弱で到着したそれは高さ50メートルの崖だ。これを下りると河がある。アマゾン河の源流の一つだ。川沿いに歩くのはもちろん密林探検のセオリーである。
「電波状態はどうだ?」
「OKだ。全機搭載カメラ異常なし。」
当然の事ながら、スポンサー様の手前営業活動もやらねばならない。崖を下りるなんて見せ場の映像配信をしないわけにはいかない。
いかにバネの手足を持っていても、サルボモーターで飛び降りるわけにはいかない。ワイヤーを掛けて、ゆっくりと下りていく。
今回秘密兵器があった。「ダンゴ虫ワイヤーエンド」、軍隊でも使っている全身ゴムで作られたロボットだ。丸まってダンゴ虫みたいになる。
これは機体を下ろすのに使ったワイヤーを回収するのに人手を要しない、という優れもの。リモコンひとつで自分でワイヤーを設置したり回収して、自分はダンゴ虫状態で上から転がり落ちて来る。
登る時にも役に立つ。こいつにワイヤーを掛けて上に放り投げれば、自分でそこらへんの岩や樹に引っ掛けて準備を整えてくれる。まあそのワイヤーで人が登って、荷重に耐えるか設置具合を確かめるようにマニュアルには載っているが。
コクピットから綾子が下りる。今回アマゾンの密林に入るということで、特別なコスチュームを拵えて来た。「ニンジャ」だ。
「いえ、これは「クノイチYUMIKAORU調」ってスタイルだよ。」
とにかく派手だ。ツルニハのコーポレートアイデンティティに従い赤と黒のだんだら模様。全身タイツにハッピを引っ掛けた、なんだかすごくエロチックな服だ。長い髪はポニーテールでまとめ、背中に日本刀まで担いでいる。
彼女だけに任せるのも心配なので、ベンも外に出て来る。海兵隊でもダンゴ虫を使う。サルボモーターの4倍も重たい車両をこんな具合に吊るすそうだ。
ワイヤーでぶら下がるサルボモーターががりがりと赤土を削りながら下りて行く。ウィンチは使うが、パイロットの操作でちゃんと手足を使って降りていく。オーバーハングじゃない急斜面だから割と簡単だ。
外したワイヤーを回収し、仕事を終えたダンゴ虫が落ちて来る。転がり落ちる、凄まじい勢いだ。あんなものがぶち当たれば機体もぶっ壊れてしまうぞ。
降りた先は泥だった。アマゾン河なんだから当然だ。水辺の泥地は当然機体の足が沈みこみ、歩行不能に陥る。
が、問題ない。サルボモーターを開発する前のツルニハは農業機械メーカーでもあった。泥田への対応は得意中の得意だ。
綾子も小さい頃は日本の小規模農業に適応した稲作用機械の宣伝に駆り出されていた。サルボモーターで田植えをしている写真も残っている。
「河を渡るのか? ワニは居ないだろうな。」
「ワニが怖い? 巨大ロボットに乗ってるのに。」
「いや、ワニの方が怖いんじゃないかと思ってな。」
ワニもジャガーもアナコンダも、こんな化物を見掛けたらすっ飛んで逃げるだろう。少し残念だ。アフリカやアラスカではサルボモーターを使い野生動物と触れ合って楽しんでいる。体長4メートルの灰色熊なんてお友達だ。
河を半分溺れながら渡り、ぬかるむ崖をよじ登り再び林に入り、また小川を見付ける。
未発見部族というものは、だいたい小川の流れる近辺に居るらしい。水の確保を考えれば当然だが、こんなものいくらでもあるからどれを目当てにすれば良いか分からない。
スポンサーも俺達も、その目的は9割方諦めている。もっと重要な問題は。
「ゴミがあるぞ。」
某ファーストフードチェーンの包み紙だ。何故こんなものが密林奥深くに有る?
「空から落としたんじゃない?」
「たぶんそうだろうが、ということはこの辺りにカーゴジャイロの航路があるのか。」
「ペルー政府のデータじゃ、ここらは開発禁止区域になってるし、飛行も特別な許可が要るぞ。」
インターネットで繋がっているんだ、スポンサーと検討して目的を一時変更、環境破壊調査となる。
カーゴジャイロの飛行高度は通常1500メートル。しかし失速し難い構造だから200メートル以下で飛ぶ事も可能だ。レーダーで捕捉できない時もある。
この特性を悪用して、人間をへんぴな地に送り込むビジネスが有るらしい。奴隷労働の場合もあるが、むしろ逃亡者に安住の地を与えるのが目的だ。
地球温暖化の影響による気象変動、とくに海洋国、島嶼国では人間が住めない土地が多数発生した。
また中国では100年に及ぶ環境破壊の結果数億の人口が海に流れ出し世界中に亡命している。この中の一部で武装している者がいわゆる「海賊」だ。
さすがに南米の奥地にまでは海賊は来ない。だが逃げ出したその他大勢はどこでもいいから陸地に移り住みたいと願っている。
そこで、不法に人間を住まわせるビジネスが発生する寸法だ。アマゾンの密林はその格好のターゲットとなっている。ただでさえ伐採が進み砂漠化が進行しているのに、これでは数年の内にまったく無くなりかねない。
俺達の未発見原住民探索も、そのような不法移民によって迫害されていないかを調査する為でもある。
密林をサルボモーターで潜っていくと、段々分かる事がある。人間の臭いは非常にきつい。人の手が触れた事の無い場所にも、人工物の痕跡が散見される。
それは意図してもたらしたものではなく、また誰かが来たわけでも無いだろうに、何故かそれがそこに有る。
最早世界から人間を排除出来ないのだろう。
「キング。」
ベンが呼び止め示す先に、非常に不愉快なモノがあった。死体だ。すっかり白骨化しているが、衣類等は残っていて身分が分かる。
これは町に住むはずの人間、たぶん女だ。若いのかもしれない。もちろんこんなところで死ぬはずの人ではなかった。
棄ておいてもいいのだが、一応降りて調べる。身元を知る手掛かりがあるかも知れない。
「動物が食べた、というよりも腐敗と虫の仕業かな。骨格がちゃんと一揃い残ってる。」
「無線端末は破壊されている。衣服のコンピュータは全部いかれてるね、電池が腐食したんだわ。」
「DNAサンプルになりそうなのは、頭髪かなあ。毛根は残ってるから分かるかもしれんぞ。」
「生体情報登録しとけばね。」
回収はしない。電波タグを残してそのままにしておく。埋葬もやめた。探している人が居るかもしれない。
インターネット経由で法医学者が協力してくれて、死因が判明する。頭部の傷から、右後方より木材かなにかで殴られたらしい。れっきとした犯罪だ。
「賭けてもいいが、原住民のしわざじゃない。」
「ええ。ひょっとするとレイプされたのかも。」
「密輸業者か、それとも仲間内か。それらしい連中に出くわしたら報せない方がいいかも知れないな。」
開けた場所に出たので、赤外線レーダーを使って近辺の森を探索する。熱源反応を捉えられなくとも、なんとなく人の居る気配は分かるものだ。
進めば進むほど、人の痕跡が増えて来る。連中はかなり苦労しているようだ。そりゃあそうだ、こんな密林に連れて来られては食べるものも無い。
開墾しようとして断念した形跡がある。農業に関しても素人なのだろう。ただ切り拓いただけで作物が育つのならば、この辺りはとっくの昔に開発されている。
谷間を見下ろすといきなり熱を検知した。コクピットからは見えない。草木でカモフラージュをしているようだ。
空中から無人偵察機で調べれば一目瞭然だが、こんなところ調べる価値も無いと公的機関は思っているのだろう。野放し状態で、おそらくは数十もこんな場所が有るに違いない。
関係機関と交渉して、綾子は機体正面の映像ディスプレイの電源を入れた。スピーカーで呼び掛ける。
『こちらは国家連合体の難民支援調査隊です。取締まりではありません、責任者は武器を伴わずに出頭して下さい。係官が今より参ります。』
これを12ヶ国語で流す。もちろん俺達がなにも公的な権限を持っていないなんて言う必要は無い。
林の向うにぞろぞろと人の集まる気配がする。金属反応も多少有る。多分武器だ。
今時コンピュータ制御の自動射撃銃くらいどこでも買える。対戦車ミサイルだって持っているだろう。苛酷な環境にある難民集団であればなおさらだ。
太平洋沖の海賊達と只の難民との間に本質的な差は無い。ただ武装のレベルが違うだけだ。
もういいだろうと判断して、サルボモーターを乗り入れる。果たして100人を優に越える人数が待ち受けて居た。女子供も少なくない。皆陽に焼けて真っ黒だが、中国人ではなかった。
「フィリピンか、東南アジアっぽいかな?」
人間の玉突きで追い出されて来たのだろう。シワ寄せはいつも弱者に押し付けられる。
近くの人と二三言葉を交わし、当該国の大使館と接続する。何人か男が出て、ディスプレイに大きく映る眼鏡の官僚っぽい人と熱心に話をしていた。
抵抗や攻撃はして来ない。一度見つかったらお終いで、しかも追い出したりしないと彼らは知っている。
不法移民は発見しても他に収容する場所が無く、国外退去を求めるにも海の上に追い出す事となってしまう。現状維持のまま国際機関が食糧支援等をしなければならない、見付かり得の見付け損だ。
大丈夫と見て俺と綾子が外に出る。ニンジャ姿の綾子はさすがに彼らの度肝を抜いた。
綾子はおばさん達を捕まえて、さっきの死体の話をする。身元確認が出来るかと思ったのだが、どうやら行方不明者は月に5人ほども出ているらしい。周囲は誰も居ない密林なのだから、犯罪やりたい放題だ。移住経費の一部だと納得してさえ居る。
子供たちがサルボモーターに集まって来る。テレビでは見た事があるが実物は知らないので、3DCGかと疑っている。
妙な話で、彼らにもテレビ番組を見る機材はある。服に付いている安物のコンピュータでもインターネットに接続して世界中の番組を視聴できた。「市民にパンと娯楽を」と言うが、娯楽に関してはまったく不自由していない。
責任者の話だと現在は350名だが、入れ代わり立ち代わりして人数は不定だという。これでは殺されたのが誰か分からないはずだ。
これ以上は俺達には無理と判断し政府担当者の派遣を確約して、早々に立ち去る。
「覚悟しておいた方がいいな。こんなところが幾つも見付かるかもしれん。」
「うんざりだわ。」
それから5日、俺達は密林を進み続けた。高低差500メートルでおよそ400キロというのは、密林内ではかなりの走行距離だ。
にも関わらず未確認部族の発見には至ってない。それどころか既確認の部族にすら出くわさない。元々の原住民はとっくの昔にこの辺りから逃げたのだろう。
さすがに俺達も疲れ果てた。林の中ではサルボモーターは転ばないが、足場の確保に神経を使う。通常の走行ならば自動操縦も使えるが、今回すべてマニュアルだ。いい加減神経が参って来る。
加えて環境の問題がある。特に虫の攻撃にひどく悩まされる。寝る時はちゃんと防虫対策を施したテントを使うのだが、それでもどうやってか侵入してきて驚かされる。綾子なんか、昨日はサルボモーターの中で宙吊りのまま寝て、身体の節々が痛いと喚く。
物資の面においては問題無い。通信1本で小型カーゴジャイロがすぐ飛んで来る。こんなに簡単だと冒険と言えないくらいだが、さすがに交代要員の用意は無い。
「今日1日探索したら、計画通りに撤収しよう。」
「うん、うんうん。」
「成果が無かったわけじゃあないから、よしとするかあ。」
初日に見付けた不法移住者のような集団を、俺達は10箇所見付けた。合計1000人を当局に通報する。全部外国人だった。
こんなに人が居るのでは、アマゾンといえども人跡未踏の地とは言えない。もはや普通に人が暮らす場所だ。
「じゃあ最後は、アレを渡るか。」
「アレって、アレ?」
「滝か、わくわくするな。そうだろ。」
地図にも記載されているちょっと大きな河の滝の向こうは、俺達は行っていない。最初から行く予定は無かった。面倒くさいからだ。
だがこちら側で原住民が確認されないとなれば、渡るしかない。
河幅は30メートルと狭いが、深さがあった。流量も多い。サルボモーターで渡ろうにも、流されて滝壷に転がり落ちてしまう。
また河縁が高く、なかなか入っていけない。直接乗り込むのは無理だから、ワイヤーを張らねばいけなかった。
サルボモーターでダンゴ虫ロボットを投げた場合、到達距離はちょうど30メートル。万無能なロボットだが、こういう器用な真似は出来る。しかしぎりぎりの距離はいただけない。
ベンが投擲に挑戦する。足場の悪い場所でぐるぐると旋回して、リリース。細い糸を引きずりながら丸いゴムタイヤみたいなのが飛んでいく。
距離は良かったが斜めに飛んだ。やっぱりぼちゃんと水に落ちる。ダンゴ虫は重い、浮かばず沈んでいく。
「アレ結構高いのよおお!」
綾子が悲鳴を上げるがベンは涼しい顔をしている。はったりか、とも思えたが、
「お、出て来た出て来た。」
「大丈夫だよ、ロボットなんだから。」
ダンゴ虫はダンゴムシ形態を取り、無数の足で川縁をよじ登る。綾子が必死にがんばれまけるなと応援する声に応えて、見事対岸に上がりきった。
ダンゴ虫は自分が渡した糸と交換するようにワイヤーを引き寄せ、太い樹の周りに掛けて準備を調える。ベンがワイヤーを伝って生身で渡り確かめると、今度はワイヤーの上にダンゴ虫を乗っける。こちらに帰って来たダンゴ虫は、今度はワイヤーの回収を行うのだ。
ワイヤーが掛っていれば、サルボモーターの河渡りに懸念すべきなにも無い。ワイヤーを挟んだ電動ローラーがういいんと回るのを見とけばいいだけだ。
コクピットのシールドを開け、じゃばじゃばと弾ける水を浴びながら渡りきる。河縁を登るのには技術が要るが、5日間泥と草の中を格闘してきた俺達には問題はまったく無い。
と思ったが、俺が転倒した。
登るのに邪魔だからワイヤーを外していたのは失敗だ。機体が流されていく。
「キング!」
改めて説明しておこう。俺の流されていく先は、滝だ。落差は20メートルほどだが岩がごつごつして至極危険。サルボモーターがいかに丈夫でもこれはちょっと耐えられそうにない。
立ったまま右回りに回転しつつ、俺は流されていく。これでは泳げない。そもそもサルボモーターの水中での速度は時速3キロがせいぜいだ。流水に抗するパワーじゃない。
「受身王」の名を恣にする俺でも、さすがにちょっとピンチだ。
だが、
「おお! すごいぞキング!」
「あれは伝説のサルボスイマー、オリーバー・コールマンの技じゃない!」
通常サルボモーターは腕の浮力で浮き、脚で水を漕いで進む。そうでなければ沈んでしまう。
しかしオリバー・コールマンは敢えて機体が沈むのを許し、この技を開発した。「バタフライ」だ。全力で回転する両腕のパワーは強力無比、時速80キロで地面に激突しても跳ね返せる。
と言っても10メートル泳いだだけで、どうにか岸にしがみ付いた。この技はやばい、コクピットに水が浸入してくる。サルボモーターは完全防水というわけでは無いのだ。
陸に上がった俺達は、その後機体の整備で2時間を要した。河なんかやっぱり渡るもんじゃない。
整備が終った直後、今度はスコールが降って来る。それこそ滝のような雨に打たれて立ち往生だ。今度は俺達が要整備となる。
「うう、けいかくどおりに今日でミッション終了ね。」
「ああ異論は無い…。」
めんどくさいから、まっすぐ森の中を進む。それまでは人を探して8の字9の字で歩き回ったのに比べると、かなりの手抜きだ。未発見部族なんかもうどうでもいい。
ベンが言った。
「あ、人だ。」
「ああん? また不法移民か?」
「いや、槍持ってる。」
おいおい嘘だろう、と立ち止まり振り返って見ると、絵に描いたようなアマゾン奥地のネイティブ狩猟民が居る。金縛りにあったみたいにぼーっと突っ立っていた。
そりゃあ、巨大なサルボモーターは密林の奥で見たくないものNO.1だろう。
「おい綾子。」
「う、うん。」
こんな時の為に綾子の機体には映像ディスプレイが装着してある。ベースキャンプに通訳も確保してある。
泥だらけのディスプレイが光を発すると、男達はそわそわと身体を揺すり始める。魔法だ、とか思って居るのだろう。
通訳は出て来ない。出て来れない。5日間ずっと待機して待ちぼうけを食わされているんだ、すぐ出ろと言われても無理なはずだ。
たっぷり5分間は気まずい時間が続く。未発見部族の言葉なんか翻訳機で解読出来るわけがないから、致し方ない。
仕方がないから綾子が適当に環境映像を流している。海のクジラとか、空を飛ぶ鳥の目線の絵とか、月面とか。彼らにしてみればまさしく魔法を掛けられているようなものだ。
「イヤドウモオマタセシマシタ、∑⊿〇+♂♀☆★☆◎§…。」
下手くそな英語で詫びた後、現地民出身という通訳が画面に出た。でっぷりと肥ったなかなか不健康な男だ。痩せてすっきりした目の前の現地民にすれば、同じ人類とは思えないだろう。
俺達の目の前で、二人はなにかこそこそと話し始めた。通訳の話は聞いていない。分かっていないような気がして来る。
「∑⊿〇+♂♀☆★☆◎、ウワア!」
一人が投げた槍が映像ディスプレイのど真ん中、通訳の額の所にぐっさり刺さる。見事な腕前だ。画面の向うの通訳も腰を抜かしてひっくり返る。
そのまま走って逃げていった…。
記録映像をインターネット経由で大学の文化人類学者に分析してもらうと、この二人はどうやら既に確認されている部族の人間だったらしい。通訳の言葉とは全然違うから、まったく話は理解出来なかったとの事だ。
俺達は探索を終了し、当初の予定に従って回収地点へと向かう。ベースキャンプに戻るのは随分と面倒なので、別の物資集積所に向かう。
ここはかなり以前に拓かれた場所で、森を抜ける道路が通っている。ただペルー側ではなくブラジルの方に向かう。
疲労困憊しきった綾子は、ぐったりと宿屋のベットに上半身だけ投げ掛けて言う。この宿屋も床は地面のままで虫が湧いて来そうだが、それでもここら辺では悪くない宿らしい。
「えーとねえ、カーゴジャイロで回収する前にブラジル入国の手続きをしなくちゃいけないらしくて、なかなか大変らしいわよ。」
「そういうのはスタッフに任せればいいじゃないか。」
「いやそれが、私達はいいんだけどスタッフ側の入国がめんどうなのよね。機材も持ち込むし。」
「帰れないのか。」
「どちらかというと、このまま陸路を通った方が楽みたい。」
「俺、車輪嫌いだよ。」
実際泥道を車輪で行くのは随分と苦痛だ。トラックを雇って運んだのだが、俺達3人車酔いしてしまう。サルボモーターの方がずっと揺れるのだから、妙なものだ。
仕方がないから、途中でハシケに乗せてアマゾン下りする事になる。
船で揺られるリズムと、サルボモーターの脚のバネのリズムは似たようなもので、トラックの小刻みな振動よりはるかに良く眠れた。
ロボットで密林の中を歩いて来たと話すと、ハシケの船長のおっさんは目を丸くする。吸っていたタバコの煙を呑み込み、げほげほと咳き込んだ。
「いけねえ。どうにもいけねえ。あんな妙な機械が森の中を歩くようになっちゃあ、世の中お終いだ。」
と、キリスト様にお祈りする。
俺もそんな気がする。
第三歩 砂漠のサルボモーター
「いやあ、アマゾン河流域の探索行見せてもらったよ。密林というのもなかなか楽しいものだなあ。今度私も挑戦してみるよ。」
サルボモーターの世界には4つの主要な大会がある。
まずアメリカで自動車用サーキットを用いて行う舗装路面高速レース。がっちゃがちゃクラッシュしまくる。
次にオーストラリアで行われるトライアスロンレース、海浜部で行われ水泳もある。元はツルニハの主宰で小豆島でやって居たものが、戦争の勃発でオーストラリアに移った。
3つめはおいといて、
4つ目が今年はアフリカで行われる格闘専門の競技会。ベンは前回のチャンピオンだ。
で、今俺達の前に居る男が3つめの大会、中東の砂漠地帯で行われる1000キロ耐久レースの主催者。王子様だ。
アブドラ・カサン・ハメーイ王子、35才。
なかなかのハンサムで国民の人気も上々。世界的にも注目される次代のリーダーの一人とその筋の専門誌にも取り上げられる。
だが俺達にとって重要なのは、彼が筋金入りのサルボ乗りというところだ。ツルニハにとっても上得意で、綾子も度々納品に行っている。
何を隠そう彼の国の軍隊には、サルボモーターだけで構成される部隊がある。
王立警護隊第一機兵教導団、王子様自らが率いる部隊だ。14機を保有する。
と言ってもサルボモーターに軍事的価値はまったく無い。各国軍隊は試しに1、2機買って試してみるが、どこも有効に活用する方法を見出せなかった。
何故ここにだけサルボモーター隊があるか、単純にかっこいいからだ。
漆黒のボディに白でイスラム特有の文字か紋章か分からない装飾を施されたサルボモーターは、見栄えは抜群だ。これに旗でも持たせたらパレードに最適なのは間違いない。
ただカサン王子は、サルボモーターをお飾りで終らせなかった。
御多分に漏れず、現在の中東情勢も混乱している。
石油ビジネスもエネルギー源としてはいいかげん終了なので、国民も焦ってデモや暴動を繰り返す中、王子はサルボモーターで単身乗り込んでいく。
報道で動画を見た事あるが、通り一面を埋め尽くす群集が、王子の機体を見てモーゼが海を割ったかにざあっと道を開けていく。
サルボモーターという乗り物は本質的に不安定でしかも静的な自立もできない。野生動物を目の前にしたのと同じ制御不能性を、人は直感で看破するらしい。
頭に血の上った連中もはっと冷静になるみたいだ。
「これを怒らせたらヤバい」と。
で、乗り込んでどうするかと言えば、デモの首謀者やら中心人物と王子が直接対話をする。
王子は必ずしもその件に関しての権力を持っているとは限らないが、メディアの前で対話をする事で相互の立場を明確にして理解を積み重ねていく。
王子への信頼と民衆の支持も上がっていく。
生まれ持ったカリスマ性を増幅する役を果たしているのが、サルボモーターというわけだ。
「お招きにあずかり光栄でございます、殿下。」
「おおAYAKO、君が居ないと折角の大会も光が失せてしまう。」
「またまた人を喜ばせる事を仰しゃって。」
聞いた話だと、5年くらい前に綾子は王子からプロポーズされた事があるらしい。第2夫人にという話で丁重に断ったのだが、「ちと失敗したか」と来る途中に陰で零していた。
ちなみに綾子は22、3才の頃ミスなんとかの日本代表に成り損ねた純然たる美人だ。
敗北の原因を「ミスコン会場にサルボモーター持ち込めなかったから」と分析していた。最強のカードを封じられて、アピール度に難点があったのだろう。
もちろん現在では、全世界のサルボ乗りの女王様だ。
「これはツルニハより心ばかりのお祝いでございます。」
「おお! これが無いとサルボモーターの集まりでも点睛を欠く。ありがとう。」
綾子が差し出す紙箱は、ツルニハの本家である菓子処『鶴仁波○○堂』の銘菓「鶴仁波」、饅頭だ。
ツルニハは自動車会社だった頃から納車の際には顧客にこれを持っていく習慣があった。サルボモーター専業となった今でも、社員が世界中どこにでも届けている。
おかげでサルボ乗りは皆日本の小豆餡に慣らされてしまった。「鶴仁波」を知らない奴はモグリと言って良い。
今回綾子は100箱ばかり会場に持ち込んでいる。なにせ中東の大会だ、参加者の半数はVIPでありツルニハの上得意。そのことごとくに綾子は御挨拶をする。
さてその中東の王子様だ。参加者123名中半数が王子様とその親戚・部下という有り様だ。もちろん遊びで出ているわけじゃない。
現在中東各国は「統一アラブ連合体」というEUをモデルとした地域統合を行い、これまで封じられて来た民主化も同時進行となる。
ここで問題なのが産業構造。今や石油はエネルギー資源としての役割を終え、かってのような繁栄は望めなくなっている。民衆の不安の種もこれだ。
だが各国を支配して来た王家はまったく心配が無い。100年近くも続いた石油景気で十分な資産を形成し、国際資本として独立が成り立っている。
彼らにもはや国家も国民も必要無い。いや、石油を失った後の国民に関わっていたら、折角築いた資産を失いかねない。
そこで、民主化を口実にさっさと支配から手を引いてしまおう、てのが彼らの考え方の主流だ。
おかしな話ではない。王家に富が集中したとはいえ、国民もそれなりに石油の恩恵を受けたのだ。後は自力で頑張れよ、という態度は他国の人間からすればむしろ当然だ。
その一方で、土地や民族、宗教のしがらみも当然それぞれの王家を拘束する。王の権威を失ってただのビジネスマンになるのは、彼らも好むところではない。
そこで各国王家は談合して、こういう筋書きを作り出した。
「統一アラブ連合体」は民主主義に基づく統合国家であり、共通する議会と憲法で運営される。その上位に一人の王を戴き立憲君主制として成り立っていく。宗教の擁護者であり、民衆統合の象徴として高い権威を認められる。
各国王家はその君主と繋がるものの国民とは直接の支配関係は持たず、地域的な権威として存在するに留める。
なかなかご都合主義の極まった体制であるが、一つ問題がある。
「誰がその立憲君主になるか」だ。特にこの地域は宗教がうるさいから、生半可な人物ではその役を務められない。
で、カリスマ性抜群のカサン王子は現在そのレースの筆頭に挙げられるのだな。
だがそう簡単に王の座を譲るのもおもしろくない。王家にも序列があり歴史的宗教的な経緯があり、納得いく決着を求めて暗躍をしている。時には銃弾も飛び交うおっかない事態にもなる。
カサン王子が催すサルボモーターレースに王子様達が集まるのも、その為だ。
王子の得意とするサルボモーターで優位を示し、あわよくば事故を装って暗殺しよう、なんて考える。無論ターゲットはカサン王子のみならず、それぞれも互いを殺し合うのも辞さない。
というわけで俺達「チームツルニハ」は今回レースには参加しないで、運営スタッフに回る。アクシデントが起きた場合すっ飛んでいって解決に当たる損な役回りだ。
ちなみに俺はこの大会で2連覇した事がある。またカサン王子に求められて、今回のコース選定は俺が監修した。
出るのは反則だから仕方がない。
「それではエントリー別に集合して下さい。一般参加者は西ゲート、特別参加者は中央に機体を進めて下さい。」
この大会、参加者には2種類ある。つまりが王子様連中とそのお付きの3機一組のチーム。一般参加者は単機での参加だ。
一般参加者は揉め事に巻き込まれないように別にまとめてある。
世界中でレースの模様は実況中継されるし、中東各国の王子様勢揃いだから注目も熱い。表向きはなにごともなくレースが進んでいくと演出しなければならない。
「”マハラジャ”の爺さんも出ているな。」
一般参加者の中に全身金ぴかのサルボモーターが混ざっている。有名なインドの財閥の総帥だ。毎回宝石だらけの機体で出場しては石が落っこちたと大騒ぎする。
一方中央ゲートは殺気立っている。こちらの王子様達は件の理由から皆敵同士、3機一組なのは本人と護衛なのだな。
だからして、こちらの機体は特注品が多い。サルボモーターのコクピットは元から拳銃弾くらいは防ぐが、さらに小銃弾を防御するように出来ている。1億円オーバーの機体も少なくない。
もちろん武装は一切搭載を認めていない。のだが、なんやかやで文句を付けて来るので、護身用の拳銃やらカタナやらはパイロットの携行物として認めざるを得無かった。
宗教的な儀式とか国賓の挨拶とかがあり、スタート地点となるスタジアムに詰め掛けた観衆もいいかげんうんざりした時、深紅のパイロットスーツに身を包む目の醒めるような美女が現われる寸法だ。
どうもどうもと左右に手を振る綾子を、こんな暑い日にわざわざ観に来るほどの客が知らない道理が無い。熱狂的な歓声と花束テープが飛んで来る。
かっては自動車の運転さえイスラム圏の女性は禁止されていた。だが人型は別ということで、サルボモーターの女神「鶴仁波綾子」はなんとなく女権解放のシンボルにもなっているらしい。
頭から布を被った若い女の子が千切れそうなほど手を振っている。
第一機兵教導団の士官の先導で綾子がスタジアムの真ん中に特設された壇に登る。ツルニハの家紋「つるニハ○○ムし」が描かれた旗を振って、競技開始だ。
綾子の隣の礼装軍服に身を包む士官が参加機体の中に混ざるカサン王子を双眼鏡で覗き、目で確認する。
「スケジュールに変更ナシ」
うん、と首肯く士官に促され、綾子が大きく旗を振る。
サルボモーターのターボコンプレッサーの音が幾重にもスタジアムに轟いた。
サルボモーターの基本を説明しておこう。
空重量で1.8トン、パイロット燃料支援装備等々満載重量が2トン半。カサン王子が乗ってる防弾仕様の機体が満載で3トン程度になる。
燃料はバイオエタノールを用いる燃料電池、もしくはキャパシタの電力。長距離レース仕様の機体は100リットルを積んでいる。
これで8~10時間動く。キャパシタのみの場合は6時間が最高だったはずだ。重たい防弾仕様機体は当然もっと早くに燃料切れになる。
最高速度は時速90キロだが、これはサーキット等のまったくに整った舗装路面で地面に障害物が落ちていない場合の数字。通常舗装路面だとせいぜい60キロ、土路面だと40キロにまで激減する。
これに坂道というハンデが加わると、もっと遅くなる。サルボモーターのレースはややこしい場所ばかり通るから、時速30キロが平均速度だ。
だからと言って、決して遅くない。
サルボモーターは道の無いところを走る為の機械だ。ギャップや段差、垣根等を越え、河を泳いだり崖を吊るされたりして目的地までほとんど直線で走行する。コースを間違えなければかなり効率的に移動が可能となる。
それで燃費だが、意外と路面状況に左右されない。速度や負荷に関係無く定常出力を出し続けるわけで、搭載燃料に規定される稼動時間はきっちり動くものだ。
つまり平均速度時速30キロで8時間、240キロ前後が走行距離になる。リッター2.4キロだ、ちっとも地球に優しくないな。
今回のコースは全長1000キロ。ただし途中に通常道路を走る高速区間を設けているので、30時間が目標タイムとなる。
3回は途中で補給が必要になるから、3箇所の補給所を設けてある。
最初の補給所は300キロ地点。しかし理論的到達距離は240キロ、60キロ手前でダウンする計算だ。
これをカバーするには、とにかくスピードを出す。止まる前に辿りつかねばならない。
ここがパイロットの腕の見せ所、てことだ。
無論それが出来る奴は限られるから、特別参加の王子様達にはチートが認められている。
一番簡単なのが燃料増量だが、これは機体重量が増加するデメリットがある。また彼らの機体は大概防弾仕様なので、元から燃費が悪い。必要だが余り得にならない改造だ。
次に目が向くのが、サルボモーター自体の性能を上げる方法。これはなかなか面白い。
世界で唯一サルボモーターを製造販売するツルニハは、しかし内部コンポーネントまで作ってる訳じゃない。
最重要の部品である燃料電池やキャパシタは、自動車用の部品を他社から供給されてそのまま搭載しているだけだ。
故にこれを交換すると簡単にサルボモーターの性能が上がる。もちろん値段も跳ね上がる。
通常2千万円程度の機体価格が簡単に5千万を突破してしまうが、中東の王子様には痛くも無い。
そして最後の手段が、3機一組のチーム編成だ。
本命の王子様がガス欠になったら、お付きの者の機体から燃料を供給して最後まで走らせる策を取る。お付きのパイロットは熟練したサルボ乗りで、当然燃料消費量が少ない。
実はこのアルバイト、俺もやった事がある。
一人でパーッと走り距離を稼いで、王子様がやって来るまでじっと待つ。技術は必要だが実に退屈な仕事だ。
カサン王子にそんな必要は無い。機体は特注で燃料増量もコンポーネント入れ換えもやってるが、お付きの者は純粋に護衛だ。
しかも脚部のバネのセッティングをハードにしている。高速走行用で固い路面に対応した設定だが、砂丘もガレ場も有るこのコースでは博打に近い選択だ。
それだけ操縦技術に自信が有る。他の王子様とは格が違う。
さてレースの行方は、まずその第1補給所まで辿りつけるか、てところが見物になる。
基本的にここまでは予選の趣を持つ。お遊びで出場した者、カッコツケの王子様はおもしろいように脱落して行く。
運営側としてはここで足手まといをふるい落としたらケアの手間が省ける。コースは一般幹線道路の脇を走る形で選んでいるので、回収は至極楽だ。
ということで、ここまでは単純に走るのを目的としたコースを設定した。飛んだり跳ねたり転げたり、といった技量は必要無い。
難易度は低いが、スピードを上げるとすぐコースアウトする。カーブがきつく、また下り坂というサルボモーターの鬼門も用意した。
慎重に行けば制限時間内に到達出来ない、だがスピードを上げれば引っ掛かり回復に手間を要する。そういう道だ。
もちろん救済策もちゃんと用意してある。
ナビゲーターに入力してある模範的走行手順を忠実にトレースすると、誰でも走れる。綾子が実際に走って作り上げた、非常に素直なコース取りだ。
最後まで指示に従う集中力が保てば、だが。
「保たねえよな、やっぱ。」
8時間ずっとナビ通りに走り続けるのは非常に困難。4時間も走るとあちらこちらで停止した機体に遭遇する。
停止自体は問題無い。トータルの稼動時間が燃料消費に関連するのだから、むしろ初心者は集中力が切れたら機体を止めて回復に務めた方が良い。
レース運営の第一機兵教導団の機体が停止した参加者の間を回る。
サルボモーターは器用な機械だが、逆にちょっとした障害に引っ掛かり脱出不能に陥る事もある。他の機体にほんのちょっと押してもらえば回復するささいな障害で立ち往生するのも、醍醐味てものだ。
でその間、俺とベンは自分の機体と共にトレーラーの上で待機している。
アラビアの荒地ってのはまあひどく埃っぽくて暑くて日光がきつくて、とてもじゃないが生身では耐えられない。
おまけに苦手な車輪の上、車酔いを我慢してひたすら出番を待っている。
「王族の機体は無いかあ?どうぞ。」
「ありません。一般参加者ばかりです。」
「了解。」
王族というのはプライドばかり高くて、助ける人間にも格を要求する。また競合相手のカサン王子の手下には助けられたくない奴も居る。
そういう連中には、このレース2連覇の俺さま「KING」と、昨年度サルボ格闘チャンピオン「ベンジャミン」がお相手する。
なにせどの王子様もツルニハの上得意だから、けっして粗略には扱えない。いわば接待レースだ。
しかし序盤ではさすがにサポートの厚い王子様は擱座しなかった。俺達の出番は、皆殺気立って来る第2ステージ以降だ。
そこらへんの懸念を後ろのトレーラーのベンが電話で尋ねてきた。
「武器持ち込んでどんぱちするバカは居ないだろうなあ。」
「いやあ、銃火器無しで襲撃なんてバカはしないだろう。」
「しないかなあ、やっぱ。」
素直にレースで雌雄が決するならばどれほど揉めても大事ないが、バカは手下やならず者を雇って襲撃するから困る。
全世界に放送されているにも関わらず、そして地元国民も固唾を飲んで見守るというのに、やってしまうのだな。
だがら、空軍の無人低速域戦闘機まで動員して不審者のコース内進入を警戒している。
とはいえ全長1000キロでしかも一般道路が傍を走る。襲撃者は確実に入り込む、と思わねばなるまい。
「あーそこのバス、右に寄りなさい。運営車両が通ります。」
入り込むのは襲撃者だけじゃない。観客が自動車やバス、トラックに乗ってコースのあちらこちらに移動し、贔屓の選手を応援する。
つまりはゴルフの観客のように、プレイヤーが通る場所近くに先行して陣取り観戦応援するわけだ。車輪てのは早いなまったく。
一般車両が立て込んで来て、俺達のトレーラーを邪魔している。数が多いから身動き取れない。
「ベン、ここでいったん降りるぞ。」
「了解。」
観客の誘導整理も俺達の仕事だ。2連覇のKINGさまと格闘王ベンさまの機体を拝ませれば、人の目を惹き付けられる。
俺達が車の流れを堰き止めている間に、別ルートで第一機兵教導団の連中はさっさと移動して行く。規定の行動だ。
キングキングと歓呼の声がこだまし、ベンの回転飛び蹴りの試技にカメラのシャッター音(擬似)がばちばち鳴る中、がりごりと路肩を踏んでトレーラーが行く。
教導団の士官がすまなそうな顔をしていた。
第1補給所に辿りつけなかったのは、123中32機。一般参加者と王子様のお付きが数台。さっそくに燃料交換をしたらしい。
第2ステージからはさらに苛酷なコースになる。砂漠の外縁部を走りぬけねばならない。
中東といえば砂漠、もちろんコース選定の際には積極的に取り込んでいる。だがやはり足元が不確かだと速度が落ちて、面白みに欠ける。
だから外縁部を選んだ。
第2ステージは進行方向左にごく緩い坂になっている。砂は薄く岩場に掛っているだけで、足元が滑ってずるずると落っこちて行く。
これを利用するとかなりの速度が稼げるが、機体制御は極端に困難になる。転げまくる。
だが砂漠だ。王子様達が見せ場とするのは、伝統的に砂漠と決まっている。
砂煙を上げて進むサルボモーターは、そりゃあかっこいい。ここを外してアピールするなんて、ありえない。
しかもこのステージは、相互の走行の妨害が許可される。あくまでサルボモーターの機能を利用しての直接攻撃が解禁される。
王子様のお付きが役に立つのも、ここからだ。王子様同士が相互に激しくバトルを繰り広げる。
その間俺達がなにをしているかと言えば、寝ている。
第2ステージは既に夜に突入し、日付を越える。暗視装置はどの機体にも搭載されているから視界に問題は無いが、パイロットの疲労はピークに達する。睡魔も襲う。
そのピーク時に突入するのが第3ステージ、山間部の危険地帯を走りぬける、真にパイロットの技量と根性が要求される区間だ。
王子様連中はここを通る気は無い、と言うか付け焼き刃では通れない。
第2ステージで精々暴れてアピールして、棄権するのがベストな選択だ。
というわけで、第2ステージには各所に観客席や撮影のベストポジションが設定してあり、照明もばんばん焚いている。
衆人環視の中で暗殺やら発砲するわけも無し。第一機兵教導団の連中も半数を撤収して、次の出番に備えている。
代りにコース保安を担当するのが、深紅のボディに黒の腹巻、綾子率いるサルボクィーン隊だ。
全機立体カメラ搭載のテレビ中継仕様。バトルを繰り広げる王子様達の中に割って入って迫力満点の映像を撮って回る。
パイロットは全員女性で6名。世界中から選りすぐった美人ばかりで、無論レース前にさんざんマスコミにお披露目している。
これを傷つける真似をすれば、いかに王様王子様でも批難は免れない。
暴れ方にも枠が出来て大事には至らない寸法だ。
「キング、ちょっとこれを見てくれ。」
ツルニハの派遣技術者が寝ようとする俺達に連絡して来た。第1ステージのレースのデータに不審な点があると言う。
「なんだ。」
「複数の機体に異常な走行記録が見られる。まるで人間が走ったんじゃないみたいだ。」
「オートか? だがオートの使用は禁止されてないし、第一このコースは難し過ぎて走れないぞ。」
「そうなんだ。通常AIでこのコースが走れるはずが無い。にも関わらず、」
ディスプレイに示される走行曲線に、俺とベンは唸った。上手いだけじゃない、野生の勘が冴えている。
こんな走行曲線を描けるのは世界中に一人も居ない。俺ですらここまでは無理だ。
「人間業じゃねえな。」
「そうなんだ。遠隔で操作している遅延反応が見られないから搭載のはずだが、車両用AIではありえない。推測なんだが、これは『カラスの脳』じゃないだろうか。」
「! アレ、もう使えるのか?」
『カラスの脳』とは、文字どおりカラスから抜き出した脳の事だ。
カラスは鳥類では最高の知能を示す。サルやイルカに匹敵する高度な知能でありながら、重量12グラムと極めて小さい。生命維持に必要な臓器を入れてもトマト缶1個に納まる。
おまけに鳥だから、知能は視覚に依存して形成される。触覚が重視されるサルでは難しい仮想空間内実験も問題なくクリアする。
故に、人工頭脳研究はもっぱらカラスに絞って進められて来た。
サルの脳は年々倫理規制が厳しくなり、なかなか突っ込んだ研究が難しい。人間の脳と精神に直結するのだから当たり前だ。
その点カラスは霊長類でも哺乳類でもない。また卵から生まれるので、発生段階から知能を直接制御出来る。研究対象としては最適だ。
そして、光コンピュータの素子でカラスの脳を複製する試みも進められている。現在の文明に必要とされる人工知能レベルはこれで上等過ぎるらしい。
「ひょっとすると、今回第3ステージまで到達する王子様が居るかも知れないな。」
「山岳コースは荒れると人死にが出るぞ。」
「仕方ない。俺達も区間全部走ろう。」
というわけで寝る。第3ステージ突入は深夜2時頃の予定だ。
目が覚めるとお祭り騒ぎだ。
第2ステージのレースは綾子の煽りも功を上げて、凄い戦いになったらしい。トレーラーの近くに居た見物人が野外スクリーンを見詰めて大興奮している。
なんでも、どこやらの王子様がカサン王子に追い上げて幾度か接触したらしい。もちろんカサン王子は『カラスの脳』なんか使わず自分の腕だけで走っている。
「参ったな。第2ステージでも効果有ったのか。」
「キング!」
ツルニハの技術者がインターネットで照会して、該当する研究機関を発見した。『カラスの脳』のサルボモーターへの搭載実験で抜群の成績を発揮したと記述がある。
「メイドロボへの搭載研究、だ?」
「どうやら人間サイズのロボットに搭載するついでに、サルボモーターにも載っけてみたらしい。転けても大丈夫なロボットはそんなに無いからな。」
「これは生身のカラス脳だろ。コピー出来るのか?」
「中東マネーで何ヶ月も前から育成してたんだろう。だが弱点も判明した。長時間は使えない。」
生身なら当たり前、サルボモーターの操縦という神経を使う仕事を何十時間も続けられる道理が無い。
第2補給所に次々と機体が飛び込んで来る。スポットライトに照らされる機体はどれも砂埃でくすんで見えた。よほど派手に転げ回ったのだろう。
第2ステージを生き残ったのは91中33機のみ。
カサン王子は3位で飛び込んだが、護衛の2機は脱落した。カサン王子をターゲットに集中攻撃が繰り返され、楯となって擱座している。
そして、
「例のカラス野郎は全部生き残ったか。」
「データから推測するだけだが、4機。すべて特別参加者だ。」
第3ステージ開始は、前とは少し手順が異なる。
このステージは非常に危険だから、パイロットには2時間の休息が課せられ、到着順に1分ずつの間隔を開けて出発する。
この区間では相互の妨害は禁止だ。断崖絶壁もあるので、一歩間違えれば死も有り得る。
「なんだい、マラハラジャも生き残ってるぞ。」
第3ステージ開始直前、黄金の機体がゴールラインに飛び込んだ。走行時間は10時間弱、よくもまあ燃料が保ったものだ。
よほどへろへろになったかと様子を確かめにいくと、確かにバテてはいるのだが思ったほど反応が鈍くない。精神的な負担が軽かった場合の疲れ方だ。
オフィシャル記録センターでマハラジャの機体データを見てみると、これも。
「オートだな。安定して走行曲線を描いている。」
砂漠の第2ステージもAIで走れるところではない。マハラジャマネーでこれも『カラスの脳』を搭載していたんだろう。爺さまの腕で俺の設定したコースがクリア出来る道理が無い。
ツルニハの技術者に転送してデータ確認させると、同じ結論を出した。
「王子様達とは設定が違うようだ。完走目的の堅実な走りを狙ってる、てとこか。」
「来年からは、ちょっとレギュレーション考えないといかんな。」
「そうだなあ。生体脳の使用は禁止にするか。」
「オプチカルならいいのか?」
「技術の進歩を禁止すべき理由が無い。まあ、ハンデをつけるくらいで。」
「うんん…。」
第3ステージが開始される。補給所への到着順に一人ずつ1分の間隔を空けて、暗い山に登って行く。
標高500メートル。高さは問題じゃない、道の険しさだ。
このステージは道幅が狭く瓦礫や浮き石が多く、一足たりとも気を抜けない。3メートル以下のギャップも多数存在し、惰性で走っていく事が不可能だ。
そしてコース終盤、明け方近くに通過するだろう地点はサルボモーターが苦手な長い下り坂になる。
なにせこのコース、そもそもが道じゃない。サルボモーターのみが通れるルートを、俺が実地で調査して選んで来た。
もちろん一定以上の技量を有するサルボ乗りであれば、9割方が完走出来ると見込んでいる。中の中、というレベルかな。
懸念があるとすればこのコース、近辺に自動車を乗り入れる道が無く、警備や救援の人員を投入し難い点だろう。
カサン王子の前2人は一般参加の上級者だ。言うなれば俺のライバル達でまっとうなサルボ乗りだから、騒動は起さない。
例の『カラスの脳』を使った王子様達は5位から15位までに入っている。
生体脳によるサルボモーター制御って奴が見たかった。だから俺は5位の後に出発する。ベンは15位の後に付いて出る。
砂漠の面影が急速に薄れ、どんどん岩山へと変わって行く。
山岳地帯こそ歩行機械としてのサルボモーターが最も期待される領域だが、まあ生身の人間でさえ歩きづらいものがそう快適になる道理も無い。
いや、悪くはない。サルボモーターは崖っぷちやガレ場でもちゃんと歩いて見せるし、巨体な分速度も出る。
問題はパイロット自身にある。
正直、サルボモーターで山を歩くと強い精神的負担を感じる。恐ろしい、というべきだろう。
平地を行く時は大型トラックと同じで、高いコクピットのおかげで速度が緩やかに感じられる。見通しも良く周囲の状況をすべて把握出来る。
だが山道となると、足元が見えない。下面カメラの表示ももちろんあるのだが、スケール感が狂って空中に浮いている感触がする。
虚空にパイロットが一人漂っている、そんな気分だ。
しかも足元は非常に悪く、一歩踏み外すと大事故に繋がる。浮き石を避けて歩調がぶれると、機体もふらふらと曲線を描いて進む。見るからに危なっかしい。
が、実際はそんなに簡単には事故らない。
なにせサルボモーターは静的な直立すら出来ない不安定な機械だ。ふらふら対策は幾重にも用意されている。6メートルの巨体も、大きさ故の遅延で細かい揺動を防ぐ為だ。
サルボモーターを信じる事。これが山道を行く時の絶対条件となる。
だが『カラスの脳』を用いる王子様に、その信頼は無かった。
俺は5位の王子様の走行を見て、パイロットがパニックに陥っていると知る。
『カラスの脳』による自動走行はたしかに素晴らしい。複雑で予測不能な路面状況を瞬時に認識し、危険を勘で見極めて実に的確に足を運んで行く。
左右に展張した腕の振動は小刻みに揺れる足元をカバーして一定のリズムを保っている。
サルボモーターでは腕の上下前後の揺れが安定していれば、コクピット周辺が揺らぐ事はまず無い。
作業用にあるのではなく、まさに安定を作り出す為に腕はある。歯車時計のテンプみたいなものだから、ここが機能していれば大丈夫なのだ。
腕を上手く使える奴が、良いサルボ乗りと言えよう。
同時に、腕の操作はパイロットが最も神経を使うものだ。
AIによる自動操縦の場合、足の運びは機械がやる。人間が関与してはならない。代りに腕の操作に介入して自分の意志を間接的にAIに伝える。
『カラスの脳』のよる制御も同じシステムを用いている。遠目でもそう分かる。
なにせ腕の動きがデタラメだ。パイロットがびびって、必死にコントロールを自分の手に奪い返そうとしている。
自動操縦に任せていればおそらくは何事もなく走れるだろうに、空中に投げ出される感覚に耐え切れず直接操作したがっていた。
これは危ない。
『カラスの脳』は生体脳であり、機械の正確さを長時間保つ事は出来ない。しかも外部から自分の操作を妨害されるとなれば、ストレスが溜る。
身体に絡みついたゴミを振り払うように、機体を振り回して妨害を排除しようとする。
俺は自機のヘッドライトでパッシングをした。果たして、前方の王子様は俺に気付き、透明のコクピットの中から縋るように振り返る。
どうやら忍耐もここで限界らしい。
自動制御の走り方を十分に観察した俺は、タイミングを見はからって後ろから機体を引き倒す。
絡み合った2機のサルボモーターは路面にしりもちを付き、滑走を始める。山岳コースを時速40キロ近くで突っ走っていたのだ、停まるに止らない。
王子様の機体はじたばたと手足を振り回し、走行を続けようとする。凄い力だ。
だが俺だってサルボ格闘には多少の自信がある。暴れる機体の手足を封じ、機体重量で抑え込む。風船手足がぎゅうと言った。
無数の石を弾き飛ばし谷底に放り込んで、2機の巨人は停まる。王子様が自動制御のスイッチを切り、やっと本当に停止した。
「√∵¨?〆仝±~&♂!!!」
「落ち着いて下さい、機体は停止しました。」
アラビア語で狼狽して喚き散らされてもなにがなんだか分からない。
俺はコクピットから出て、王子様の機体のキャノピーシールドをこつこつ叩く。外に出るべきだとようやく理解して、王子様は弾けるように飛び出した。
「ハアハアハアハア、停まった、やっと停まった。」
「自動操縦を切れなかったんですか?」
「いや切れる。だが切った途端に転んで道を踏み外すとどうなるか、考えただけでも恐ろしくて、手が出せなかった…。」
息を弾ませる王子様は、俺の記憶によると、なかなかに勇猛で威勢のいい事ばかり高言している人だ。実際勇気はあるのだろう、こんなところまで来れたのだから。
しかし技量と度胸は表裏一体。自分に出来るものが分かっているからこそ、無茶な場面にも飛び込める。
まともにサルボモーターの操縦を訓練していれば、自動操縦に怯える必要は無かったのだ。
改めて王子様に確認し、レースの棄権を運営委員会に報告する。リタイアだが、恥にはなるまい。
「KING、聞こえるか!」
「ベンか、どうした。」
「そちらでは強制停止させたみたいだが、残りの連中ももう限界だ。これから停止させる。」
「おう。すぐ応援に行く。」
4人の王子様を停止させた俺達は、これでもう何も起こらないと安心した。ついうっかり、だ。
王子様が自力で名誉を獲得する機会が無くなればこそ、暗殺者の出番が来るというのにだ。
カサン王子を除いて特別参加者は全滅した。残ったのは腕っこきのサルボ乗りばかり、王子も存分に腕を揮える。
勢い機体の速度も上がる。
足場の悪い山道では昼間であってもこれほどは走れない、てほど飛ばしていた。
暗視機能はちゃんと動いている。路面をスキャンするミリ波レーダーがしっかりと浮き石を発見し、パイロットは瞬時に対応する。
暗い崖の上をちらちらと覗くサルボモーターのヘッドライトが、まるで悪霊の灯火に見える。
いや迷信深い人が見れば、巨人の走行はまったく地獄の鬼と映っただろう。
「夜明けだ。」
冥い空にインクの沁みに似た赤が差し始める。この時間帯が最も危険だ。
夜間用のセンサーから昼間の肉眼による視認に変わる、その狭間が状況認識を間違える最悪のゾーンだった。
だがもう少し、この坂を下りきれば第4ステージは平面。砂漠と幹線道路を高速で突っ走り、出発地点の街に戻る。
曙の光こそが、ゴールに至る最後の関門だ。
俺はショートカットをして、先頭の機体の前に居る。いつでも飛び込んで行けるように、コースの上100メートル付近の崖に待機する。
カサン王子は相変わらず3位。よく順位をキープしている。第4ステージで一気に追い抜く為に、ここは必死で食らいつく。
その他の機体も、夜通し突っ走って来た疲労も見せず、足元の滑り易い下り道で確実に歩を刻んでいる。
熟練者ばかりだ、平地で勝負を掛ける為にもはや無理な追い抜きはしない。
「ん、観客か?」
俺の真下80メートルほどに、いかにも中東山岳地帯の民族っぽい数名が居る。
当然ここは立ち入り禁止だ。悪意は無くとも何らかの弾みでパイロットに動揺を与えかねない。機体が転倒すれば巻き添えも喰う。
男達はなにか棒のようなものを取り出し、肩に担ぐ。
「おいまさか!」
驚く間も無く、棒が火を噴いた。RPGだ。
生まれて100年経つ誘導機能も無い老いぼれた武器だが、威力は未だに健在だ。最新鋭の装甲兵器であれば造作もなく防ぐだろうが、サルボモーターの軽量では有効な防備を施せない。
というか、足元の地面を狙って崖下に転げ落とす気か。
狙いは違わずカサン王子の前方30メートルで爆発する。穴が開いたが、かまわずジャンプする。さすがだ。
2発目も前方で爆発。今度は近い。機体が多少ぐらついたが、まだ走る。
中々有効打が得られないので、刺客は自動小銃を撃ち出した。その口径の銃弾は、カサン王子の特別製機体には通用しない。
だが王子の機体はその場に立ち止まってしまう。2発目の影響か?
3発目を構えている。今度は弾の形状が違う、誘導弾だ。レーザーを目標に当て続ける事で誘導する旧式タイプと見たが、サルボモーター程度であれば十分有効だ。
「!」
俺は跳んだ。手遅れなのは明らかだが、これ以上カサン王子を傷つけさせる訳にはいかない。
大事なスポンサーであり、なにより優秀なサルボ乗りの仲間だ。
滑りおりる崖の途中で、俺は信じられないものを見た。
カサン王子は機体の左腕を前に突き出し、身構える。焔を吹き出し飛んで来る誘導弾を真正面から受けた。
次の瞬間、弾はどこか遠くに飛んで行く。
「弾いた?!」
サルボモーターの腕脚は強靱なCNTラバー素材で作られたカバーで覆われている。中に圧搾空気が詰っているから、文字どおり風船だ。
強度は非常に高い。拳銃で撃たれても貫通しないほど。だが小銃弾や徹甲弾、成型炸薬弾のメタルジェットには耐えられない。
カサン王子はこの腕で、誘導弾を横からぶっ叩いた。
高速で飛来するロケット弾も、信管に当たらなければ作動しない。風船腕にぺんと弾かれ明後日の方に飛んでった。
そして爆発。
俺は刺客を沈黙させる為に、機体を崖で転倒させる。上から転げ落ちる岩や土で埋めてしまう作戦だ。
「受身王」KING、ローリング・キングの名は伊達じゃない。
崖を左右に斜めに転がり、満遍なく岩肌を削る。たちまち刺客の上に大量の土砂が落ちて行く。
「王子は、」
誘導弾の爆発は随分と離れた場所だった。損傷は無い。だが爆風に煽られて機体が揺れている。
銃弾を浴びて脚部の機構に支障を来したのかもしれない。
よろよろとサルボモーターは歩いて行く。倒れないようにバランスをとり続けると、どうしようもなく歩いてしまう。
王子襲撃の急報を聞いて、王立警護隊の武装ヘリが飛んで来る。吹き降ろす風が、だが逆に王子の機体をさらに不安定にする。
機体のすぐ脇は150メートルもある断崖。20メートルくらいは平気で飛び降りるサルボモーターでも、こんな高さには耐えられない。
落ちるな、落ちるな、その場に転べ。
「落ちた!」
カサン王子のサルボモーターが転落する。人型が両手を拡げて宙に舞う。スケール感が分からず、妙にゆっくりと下がっている風に見えた。
だが現実は物理の法則に従い、厳然たる解答を導き出す。
足から着地した機体は大きくバネ脚をたわめ、コクピットが地面に衝突するかと思える沈みを見せた瞬間、前に飛び出した。
ごろごろごろと下って行く。受け身もなにもあったものじゃない。50メートルも転がって、ばきいとフレームが割れる音を立て静止する。
俺も、王子を追って崖を滑り降りて行く。近くに居た参加者の機体も150メートルの崖を下って行く。
ちゃんと降り方を知っていればこのくらいは出来るのだ。カサン王子だって機体の状態が良ければ、無事に降りられたはず。
4機のサルボモーターが王子の傍に立つ。誰から手を着けるべきか、一瞬迷う。
幾らなんでも、あの高さは無茶だ。助かりようが無い。
サルボモーターは或る程度以上の高さを落ちる時、必ず足から接地するように姿勢を制御するが、そんなものでは間に合わない。
黒いボディに白色でアラビア文字を描いた機体が大岩にもたれ掛かり倒れている。激突したコクピットのシールドは細かいひび割れで真っ白になり、中が見えない。
ぼん、と爆発してシールドが吹き飛んだ。びっくりするが、通常の機能だ。サルボモーターには随所に戦闘機の技術が使われている。
白い煙の中から伸びる手がある。黒と白のストライプの、カサン王子のパイロットスーツだ。
よたよたと這い出して来る王子は、一見して怪我がある風には見えない。
俺は急いでコクピットを開く。脚をたわめて降着させる。
無事か、無事なのか。
眼を貫く曙光の中、王子は両腕を天に衝き上げた。
「カサン王子は棄権、と。特別参加者は全員リタイアね。」
綾子は王子の危機にも平然としたものだ。その時間帯寝てたのだから仕方がない。
刺客は全員無事掘り出され、逮捕される。依頼主は多分分からないだろう。
それでもレースは続く。第4ステージは朝の光の下、到着した機体全てが一斉同時に走り出す。
タイムの集計はされており、既にこのステージでは挽回出来ない差が付いている。順位は確定したようなものだが、やはりゴール前のデッドヒートは観客の期待するものだ。
俺とベンにはもうどうでもいいことだ。
カサン王子は無事だった。来年もレースは行われる、それでいいじゃないか。
綾子が言った。
「あ、マハラジャのお爺さん。最下位だけど残ってるね。どうしちゃったの。」
「あー、話せば長いものがあるが、爺さんに直接聞いた方が喜ぶんじゃないか。」
「うーん、そうね。そうねそれも悪くないわ。」
ツルニハの商売は今日も大繁盛だ。
第四歩 アフリカのサルボモーター
綾子はサルボモーターに格闘なんか出来ないと言う。
その言にも一理ある。
おもいっきりパワーを込めてぶん殴っても、民家のコンクリート壁を貫けない。威力の観点からすれば、軽トラでぶちかました方がマシだ。
しかし彼女がそれを言うのは、おかしな話だ。サルボ格闘は彼女が始めたことなのだから。
今でも覚えている。全世界の人が覚えているだろう。
もう20年も昔、当時9歳の綾子がサルボモーターを操って、ツルニハのテストパイロットが乗る機体を蹴り倒した。
今でいう「右手旋回軸足払い」て技だが、あまりに鮮やかに決まった映像はニュースバリュー抜群で、全世界のテレビで一斉に流された。
ガキだった俺はこの映像を見て、脊髄に電撃を食らった気がした。直感が走った。
サルボモーターという機械に無限の可能性がある、と確信した。それからだ、俺がこの道に首を突っ込んだのは。
確信は俺だけのものでは無かった。
その年、ツルニハは年間製造台数を5倍も上回るオーダーを受け、機体を一気に世界中に拡散させた。サルボ乗りが10倍に増えた。
基本的にサルボモーターは走るしか能が無い機械だ。が、アレを見せられた俺達がそれだけで済ますはずが無い。
走行の可能性を追求しレースが開催されるのと同時に、格闘競技も試みられていく。
そしてアフリカ。
2041年のサルボ格闘競技会はアフリカのサバンナで開催されると決まる。
アフリカはいいところだ。地平線の彼方までどこまでも走っていける。サルボモーターだけでなく、無数の野獣が草原を走りぬける中、俺達も同じ速度で走っている。
車輪では決して得られない自然との同化を、この風船手足のロボットが実現してくれるのだ。
そうすると、当然次を求める奴が出る。
「どうぶつたちとおともだちになろう」
この欲求の正常さは、誰もが認めざるを得ない。そういう機械を人類は手に入れてしまったのだから。
次の大会がアフリカと決まった瞬間から、ツルニハの営業所やHPに特殊な部品のオーダーが相次いだ。
「もふもふ手」と呼ばれるハンドシューズだ。
「あーあー、平原全体のサルボ乗りに告げる。無闇に動物に触らないでください。野生動物は臆病です。特にカバを触るのは禁止です。カバの皮膚は非常に薄く、もふもふ手での接触でも大きく傷付く可能性があります。決して水辺に近付かないでください。というか、てめえらきたねえ手で触るんじゃねえ!」
オープン回線で大会参加者全員に呼び掛ける女性が、「もふもふ手」の開発者マリーアン・ミメット博士(54歳)だ。
彼女はサルボモーターが発売になる前から、アフリカで野生動物の研究と保護に携わっている。それなりの誇るべき実績も有る。
だが所詮人間は野生に受入れられる事は無い。人工物で囲まれその助けが無いと小さなネズミにも嘲笑われる、それが人間て生き物だ。
彼女はそれが我慢出来なかった。もっと近くに、動物達が生き生きと活動するど真ん中に乗り込んでしかも生活を妨害しない、そんな手段を探していた。
そこでサルボ、とはならない。6メートルの巨大ロボットが野生動物に受入れられる道理が無い。
仕方がないから、彼女は「もふもふ手」を作る。
「もふもふ手」はネコ科の動物の前足を摸したハンドシューズ、受け身用の接地パッドだ。
プラスチック製の大きな肉球が有り、ふんわり柔らかく動物に接する事が出来る。これで動物を抑え込み、医療行為を行う。
通常は麻酔薬を用いるのだが、人事不省に陥った状態で好きなように弄くるというのが、彼女には我慢出来なかったらしい。ま、精神安定剤は使うのだが。
これを装備したサルボモーターを使いながら、動物達の周辺で研究と保護活動に勤しんでいる。すると、妙な現象が起こった。
動物達になめられた。サルボモーターがまぬけな生物と勘違いされた。弱っちい奴、と平気で傍に寄るようになる。
で、サルボモーターだが、これがまた本当に弱いんだ。
ゾウにもサイにもカバにも突き転ばされ、ライオンにしがみ付かれて噛みつかれ、シマウマに蹴っ飛ばされる。
そしていつの間にか、草原にサルボモーターが立つ風景が普通になった。
「AYAKO! どうしてアフリカなんかに決めた!!」
「いや、あたしは大会運営とはなにも関係無くて、濡れ衣ですよお。」
金髪のおばさんに怒られる綾子はひたすらに謝り続ける。開催地を決めたのはツルニハじゃないが、「もふもふ手」を売らなければこうまではならなかっただろう。
もちろん、アフリカが会場に選ばれたのには理由がある。毎度おなじみのエコだ。
現在世界全体を巻き込む戦争が行われている。
強大な国家同士の争いでなく、環境激変で生活が立ち行かなくなった国の民衆が武器を手に海に乗り出した。
この戦争の特徴としては、敵と呼べる勢力が貧困に喘ぐ難民そのものであり、膨大な数を有しているところだ。
アフリカも例外ではない。かって貧困は陸上に封じ込められて来たが、今や海に夥しい人数が流れ出す。しかもそれなりの武装を手にしてだ。
こんな状態では野生動物の保護がないがしろにされるのも当然。マウンテンゴリラなんかは、先進国の動物園以外では既に絶滅してしまったと聞く。
だが動物保護の寄付金を集めるのも昨今は難しい。なにせ人間が数億も難民化して、金は幾ら有っても足りないのだ。
下手に動物に資金を回せば、人命を軽視したと指弾される。人権ナチと称される攻撃的難民支援団体も有る。非常の時は優先順位を変えるべきだ、ともっともらしく有識者は語る。
今ではどこのサーバーに繋いでも、泣き叫ぶ子供や女性の悲惨な映像で溢れている。それ以外のニュース映像は制限されているかにも思える。おそらくは何者かの陰謀だろう。
で唯一可能なのが、見世物としての野生動物のクローズアップ。あくまで娯楽として放送配信の枠を確保し、視聴者の関心を振り向けさせる。
俺はおばさんに聞いてみた。
「ここは密猟は大丈夫なのか?」
「みつりょう? ああ、まあサルボモーターのセンサーが見張っているから、たいがいは大丈夫ね。リモコン戦闘機もあるし。」
「そんなものどうやって手に入れたんだ?」
「有る所にはあるのよ、そんなもの。武器はどこでだって買えるわ。ミサイルだってレーザー砲だって。」
おばさんも大会の意義はちゃんと理解しているのだ。金は幾ら有っても足りないし、かってのような消極的な保護策ではなにも護れない。地元国家の支援はアテにならない。
一方前回チャンピオンのベンは、そこらへんでサインやら握手やらを求められて大忙しだ。
ベンジャミン・ミン・ジャンはアメリカ海兵隊に所属していたデカい黒人だが、ここアフリカでは地元出身者扱いされる。
世の中変わったもので、アメリカの相対的衰退と同時に、アフリカでは民族意識の高まりが盛り上がって来た。黒人は全部アフリカ人、黒人が成し遂げた成果は皆アフリカ人の持つ先天的な資質の表れだ、という事らしい。
この風潮がいいか悪いか、俺には分からない。長年欧米白人の支配に虐げられて来た民衆が自信を持つのは素晴らしいのだろうが、どうにも政治的プロパガンダの趣が強くて辟易する。
それほど自信があるのなら、木造ボロ船で脱出する難民をなんとかすればいいのに、とも思うのだ。
アフリカも貧困一辺倒というわけでもなく、かたや昔ながらの難民が居るかと思えば、こなたには資源ビジネスで財を成し競技会に家族連れで見物に来る成金もある。
俺達の使命は、この成金どもから金をふんだくって、アフリカ全体の至宝である野生動物の保護を推進する事にある。
まあせいぜいベンには頑張ってもらおう。
「KING!」
と、旧知の友が声を掛けて来た。右手を上げて互いにパンと打ち鳴らす。
トマース・ハヴェイ、33才。熊みたいに毛深い小男だ。こいつも格闘系サルボ乗りで、前回大会で4位に入っている。前々回は2位だ。
こいつが持ち込んだ機体はかなり年期が入っている。例の綾子の映像が世界中に出回りサルボモーターが大ヒットした時代の骨董品を、いまだに修理しながら使っている。
「相変わらずスポンサーが付かないのか。」
「おう、やはりビジュアル面において若干の問題があるらしい。今回も自腹だ。」
「もふもふ手は買わなかったのか。」
「似たようなのを自作してみたんだが、動物を傷つけない機能てのはなかなか実現出来ないな。」
おばさんが尖がった目で睨むので、俺は申し出た。
「良かったら俺のもふもふ手を使わないか? 俺は競技会に出ないんだ。」
「そりゃあ残念だが、仕方ないな。ローリング・キングの妙技は反則だもんな。」
俺もサルボ格闘にはかなりの自信が有る。独自の技で一世を風靡した事がある。だがこれは効果が有り過ぎて国際サルボ格闘競技連盟が反則にしてしまった。
つまり、寝技だ。
自分の機体をわざと転ばして相手を巻き込み、グラウンドで手足を封じ動作不能に追い込む。
理論上はサルボ格闘の最初期から有る戦法だが、実質確立したのは俺なんだろう。そもそもがサルボモーターには地面で蠢く機能が無い。それだけ難しい。
ただこれは、見た目がかなり悪かった。
6メートルの巨人が互いに殴り合う姿を観客は見に来ているというのに、地面の上でだだっこが手を振り回す格闘は金にならんて事だろう。
今の規則では、サルボ格闘フィニッシュ時相手を動作不能に抑え込む場面でも、自機は起きていなければならないと決まっている。
つまりはカッコツケをしなければならん、てことだ。
さて今回の競技会、参加者のほとんどが「もふもふ手」を持ち込んだ為、現地に集合した時点でいきなりレギュレーションが変わった。
「もふもふ手トライアル」と銘打って装備を義務づけ、もふもふ手を生かした格闘が評価基準となった。
これはちょっと大事だ。もふもふ手は打撃力がほとんど無い。そもそもが動物を優しく撫でる為に開発された装備だから、格闘と対極に位置する存在だ。
引っ掛ける爪も無ければ握る指も無い。手を使っての技がほとんど使用不能になる。
足技主体の奴は大丈夫だろうが、その分機体のバランスを取るのが難しく転倒続出の期待が高まる。いい絵が撮れるぞ、と素人カメラマンがうろちょろしている。
それに先立って、すべてのサルボ乗りがアレに挑戦した。新装備の習熟訓練みたいなものだ。
俺のもふもふ手を早速取りつけたトマースが、おんぼろ機体に乗り込んでびしっと敬礼してみせる。
「じゃあ俺ももふもふして来るぜ!」
サバンナに棲息する野生動物との触れ合い、と言えば聞こえはいいが、つまりはサルボモーターでゾウやらサイと格闘する。
いや、格闘とは言い難い。サルボモーターが一方的に蹂躙されるのを楽しむ、これが「もふもふファイト」だ。
サルボモーターにすっかり慣れてしまった動物の中には、たまに異様な興味を示すものが居る。サルボモーターをぶん投げるのが趣味になった奴だ。
それらが、俺達の集合をどこで聞きつけたのか集まっていた。祭の気配を感じ取ったのだろう。
中でも一番人気なのは、巨大なオスのアフリカゾウ「ジーク」と百戦錬磨の古強者サイの「フレディ」だ。
この2頭のぶちかましは他の動物を圧倒して機体を30メートルも吹き飛ばす。特に「ジーク」は器用に鼻を使って、サルボモーターを横回転で投げる事が出来る。
だが人気が高いからなかなか順番が回って来ない。2頭の気が向くまでじっと忍耐が必要だ。
「もふもふファイト」のシーケンスはこうだ。
集まったサルボ乗りが互いに順番を決めて、1体だけが進出する。目標となる動物の傍に歩いて行く。
そこでそのまま待機する。突っ立ったまま、ぼーっと揺れている。
動物は次第にサルボモーターの存在が気に食わなくなり、いらいらしてぶちのめしに来る。
ここで逃げてはいけない。殴られ突き飛ばされるままに攻撃を受ける。派手に転がる。
何度でも立ち上がり、何度でも突き飛ばされる。ごろごろと草原を回転する。
動物が疲れて飽きたら終了だ。その間何度突き転ばされたか、これが動物に与えた好感度としてカウントされる。
抵抗はしない。する奴は即退場だ。周囲のサルボ乗りが実力で排除する。そんなバカは居ないんだが。
上位入賞者として皆に瞠目されるトマースは、順番を譲られて「フレディ」との対戦を行った。
回る回る、すっ飛んで行く。奴も受け身はなかなかに上手い。即立ち上がり、ゆらゆらと「フレディ」を挑発する。
久しぶりに骨の有る奴が来たと「フレディ」も根性据えて突っかかる。サルボモーターが宙に浮く、なんてのはなかなか見られるものじゃない。
11回も突き転ばされ、最後には糞までもらってトマースは退場する。全員拍手だ。
遠目で見ていたおばさんが言う。
「ふん。まともなサルボ乗りが来たから、今日はごきげんね。」
下手な奴だと2回も突き転ばしてもらえないのだそうだ。機体の転がり方に美を見出さなければ、「フレディ」はすぐ飽きるらしい。
綾子は言った。
「あたし! ライオンにかじられて来る!!。」
競技会が始まる前日。妙な客が来た。
巨大なカーゴジャイロで運ばれる機体だ。支援装備と技術者が何人も乗っている。
どこのお大尽かと思ったが、それは俺達の予想をはるかに越えるものだった。
「なんだありゃ、ロボットじゃねえか。」
「ロボットだ。ほんもののロボットだよ。」
「うわあ、頭が付いてやがる。」
サルボモーター形式でない、通常の肘膝に関節のある電気モーター駆動の巨大ロボットだった。アニメで見る奴にそっくりだ。
色は全身オリーブ、マーキングは無いが機体随所に黄色い丸が描いてある。ビデオで動作確認をする際の目印だから、実験用の機体をそのまま持ち込んだってわけだ。
全高は6メートルでサルボモーターと同じ。ただ立派な頭があるからこの分を差し引いて、心持ち小さく感じられる。
「どこのバカ?」
綾子が血相変えて問うのも無理はない。この大きさの二足歩行ロボットには実用の価値がまったく無い。無いからこそ、サルボモーターの市場独占が可能なのだ。
「”I・R・S・P”のロゴだ。ヨーロッパの兵器メーカーだな。戦闘機とか作ってる。」
「そんなまともな企業が、どうしてバカロボット作るのよ。」
「俺に聞くなよ。」
それはまったくもってロボットだった。手足が角張っていて、ちゃんと関節が付いている。人間と同じ自由度を持ち、作業も自在にこなしそうだ。頭部はセンサーの塊で兵器級の機密の塊らしい。角張っているから多分、装甲も出来るのだろう。
なにより驚いたのは、立っているのにふらつかない点だ。サルボモーターなんか静的に自立するのさえ高等技術と目されるのに、普通に立って居る。
「人類の技術力は、ついにここまで到達したのか。」
「いや長生きするもんだ。ほんものの巨大ロボットにお目にかかれるとは。」
6メートルの巨大ロボに日頃乗ってる奴の台詞じゃないが、俺達は皆そう思った。
なんかキザったらしいビジネスマンみたいな奴が来た。綾子がツルニハの看板だと知ってか、まっすぐこちらに向かって来る。
背の高い奴だ。ベンと同じくらいあるが、細い。アフリカの日差しがまぶしいのか、手で顔を被いながら自己紹介する。
「お目にかかれて光栄、ミスAYAKO・TURUNIHA。いや、サルボクィーンとお呼びするべきでしょうか。私はIRSP技術開発局多脚ロボット開発部主任プロデューサー、シバ・ネベと申します。」
「なにあれ。」
くいと親指で示す綾子に、奴は言った。
「いやあ、搭乗型二足歩行ロボットの先駆者としてサルボモーターは評価はしますが、時代は常に移り変わるものでして、我々もこの分野に参入する時を迎えたとお考え下さい。」
「二足歩行ロボットなんて、役に立たないわよ。」
「立ちませんね、サルボモーターなんて。」
いちいち挑発的な奴だ。だが冷静になって考えてみれば、大会にわざわざぶつけて来るのだから、このロボットの特性はサルボモーターとあまり変わらないのだろう。
綾子を抑えて俺が質問する。
「鋼鉄の装甲を持ってるロボットは、この大会お断りだ。」
「今回はクッションで各部を覆っております。動物と接触しても傷つけないように、細心の注意を払いました。」
「大会に来るってことは、出る気だな。」
「国際サルボ格闘競技連盟規約には、サルボモーター形式のロボットに限る、とは書いていませんから。」
「つまり、このロボットは格闘が出来るのか。」
「出来ますとも。格闘でも戦闘でも。」
凄い自信だ。だが巨大二足歩行ロボットの研究は、サルボモーター以外聞いた事が無い。実験室レベルのものがほんとうに使えるのか、はなはだ疑問だ。
「今回の大会は「もふもふトライアル」と決まった。もふもふ手は無いだろう。」
「あー、対人作業用の繊細なマニュピレーターエンドがありますが、御検分いただきましょう。」
メーカーオフィシャルチームである「チームツルニハ」には、大会事務局と同等の権威が認められる。同伴する技術者は、サルボモーター開発陣に籍を置いていた者だ。
だから俺達と事務局は合同で「ほんものロボット(仮)大会出場資格審査会」を結成し、検分を行った。
誰もが最初に気付いたのが、このロボットの外装だ。
「この外部クッションは、急ごしらえの間に合わせ品じゃないぞ。しっかりと実用を考慮して設計されている。」
「サルボモーターが柔軟なクッションによって活動域を拡げているのを参考に設計してるんだな。装甲も可能と言ったが、実質は戦闘用じゃないってことだ。」
「つまりサルボモーターと同じくスポーツ目的なの?」
「違うな、特殊環境下の作業用だ。聞いた事がある。戦場の無人化ロボット化が進展して、却って人手が必要になったって。それを代替するものだ、これは。」
「人は殺さないが、兵器には違いないってことか。」
外観上最も特徴的なのは、頭だ。サルボモーターには存在しないこのパーツは、受け身をする時に非常に邪魔になる。
このロボットを俺達が操縦するとして、頭を破損しない為にかなり無理をして転ばねばならない。
ベンが格闘王として質問する。
「シバ・ネベさんよお、このロボットの頭は壊れてもいい部品なのかい。遠慮泣く潰させてもらうぞ。」
「あーそうですね。頭部にはクッションが無いので、大きな衝撃を受ければそれは壊れます。ですがサルボモーターの攻撃では難しいのではないですか?」
「う、…む。」
スペックの問題だ。サルボモーターの出力よりも、このロボットの全身アクチュエーターの合計出力の方が3倍ほど大きい。非力なロボには壊せない、と言いたいらしい。
サルボ乗りが車になって囲む中、ほんものロボットは一通り歩いて見せる。動きは滑らかで繊細、確かによく出来たおもちゃだ。
ただ俺が気付いた点は、たぶんこいつの欠陥と言えるだろう。
「動きにリズムが無いな。」
「ええ、ただ動いてるってだけね。パイロットが操縦スティックを前に倒せば、自動で前進するのよ。」
「格闘できるのか、これ。手足をパターンに従って自動で動かすだけじゃないのか。」
「巨大ロボット格闘ソフト、ってのはサルボモーター用のしか無いはずだ。違うか?」
シバ・ネベは居並ぶサルボ格闘強者に対して、胸を張って答える。
「物理シミュレーションで対サルボモーター格闘を学習させています。御心配は要りません、がんがん当たってきて下さい。」
「ま、重量倍有るしな。」
重量2倍で出力3倍。まあ普通に考えれば勝てるんだが、最終的にはパイロットの腕次第だろう。
デモンストレーションを終えてロボットは停止し、降着姿勢を取る。膝脛がクッションになってるから、跪いて上半身を直立させる。下腿部に車輪が付いていて牽引出来る、この機能はいいな。
コクピットは腹部に有る。胸腹部一体の正面装甲が下から開いて跳ね上がる。肉眼による視界は取れず、すべてカメラに委ねる方式らしい。
シートが前方に迫り出してパイロットが降りて来る。小さい奴だ。
「女の子だわ。」
至る所コンピュータが貼り付いた未来的なパイロットスーツから透けて見える身体は、15、6歳の高校生と思う。白人で髪は赤い。幼さを残す表情に強い緊張を覚えている。
「エルシイ!」
シバ・ネベの声でこちらにやって来る。彼女の瞳は俺に集中する。俺が何者であるか、ちゃんと知っていた。
「我が社のテストパイロット、アル・エルシイです。」
「アルが苗字?」
「はい。」
声は可愛い、と言うと怒られるだろうか。なんとなくアニメ声だ。ドイツ語の訛りの有る英語だが、移民らしい。
俺を見て、何か言いたそうな顔をする。
綾子がシバ・ネベを言葉責めしているから、ロボット乗り同士勝手に話を進めよう。
「エルシイ、こう呼んでいいか?」
「はい、キング。私達は貴方の事を随分と研究しました。このロボット、”ヴァン”にも貴方の操縦を参考にした運動シーケンスが多数組み込まれています。」
「そりゃ使用料貰わないといかんな。どうだ、「もふもふファイト」は出来るか?」
エルシイはオリーブ色のロボットを振り返り、マニュピレータの指を見る。動物に接触するには少し細過ぎると俺は思うのだが、
「指に追加のクッションを装着すれば。自由度が無くなりますが、手首だけ動けば多分。」
「OK。順番を譲ってもらおう。」
十数機のサルボモーターが囲む中、ほんものロボット”ヴァン”がアフリカ大地の洗礼を受ける。
対するは雄のアフリカ象「ジーク」、サルボモーターを転がす事に関しては右に出る者の無いアーティストだ。
ただ「ジーク」はかなり気難しい。気に入らないと投げてくれない。見た事の無い形式のロボットに興味を示すか、ほとんど賭けに近い試みだ。
俺はサルボモーターに乗らず、遠くピックアップトラックの上で待機している。一応は麻酔銃の用意もしておかなければいけないのが、「もふもふファイト」のルールだ。
代りにトマースがリーダーとなってサルボ乗り達を指揮する。「もふもふファイト」に関してはやはり格闘専門の連中の方が見極めが上手い。
ベンはと言えば、こちらも待機。自分の機体のコクピットから眺めて居る。
”ヴァン”が一機のみで進み出て、「ジーク」が近寄るのを待つ。この待ち時間こそが「もふもふファイト」最大の試練と言える。
とにかく動物が近付いてくれなければ話にならない。こちらから追い回すのは虐待に相当するから、禁止だ。
果たして「ジーク」はかなり不愉快に見える。”ヴァン”が新しくて、未だ有機溶剤の臭いを漂わしているからだろうか。
様子見で他の機体にちょっかいを掛けていた「ジーク」が、いきなり”ヴァン”の傍にどんどんと駆け寄った。
俺には彼が何を考えていたか分かる。”ヴァン”の重量が分からなかったのだ。
サルボモーターの重量はどれもほとんど同じ、だから決まった力でぶん投げれば思い通りの転がり方をする。
対してまったく違う形状の”ヴァン”は、その重量も転がるフィーリングも想像出来ない。理想的な転倒の仕方をしなければ、アーティストとしての矜持が許さない。
そうは言っても、ほんものロボットの重量をどのように表現すれば良いだろう。
全身バネが連なっているサルボモーターは揺らしてみれば感じで分かる。しかし、各部関節で分離している通常のロボットは、ちょっと触ったくらいでは分かり難い。
「ジーク」がアーティスト、てのはそういう事だ。ゾウでありながらもロボットの構造の違いをちゃんと認識して対応を変える、この知性が芸術家の証明だ。
偉大なる彼は、結局最もシンプルかつ有効な手段を選択する。
関節で手元が揺らがない肩口を鼻で引っ掛けて、力任せに倒す策だ。サルボモーターであれば急角度の横回転、或いは斜めにぶん投げられるクリティカルの旋回をする。
「!、なに?!」
”ヴァン”は飛ばない。重量が大き過ぎたのではない、抵抗して飛ぶのを拒否したのだ。これでは「もふもふファイト」にならない。
「やばい!」
俺とベンはいきなりそれぞれの乗り物に火を入れた。エルシイは「ジーク」の真の恐ろしさを知らない。野生のアフリカ象の破壊力をまったく理解していない!
果たして「ジーク」は怒り狂う。彼は非力などとは縁の無い、極めて兇暴な生物だ。鼻で投げて見せるのは、サルボモーターがそれを望むからなのだ。
その信頼関係が失われたとなると、目の前に有るのは単に彼らの棲み家に闖入した侵略者に過ぎない。
倍で4トンもある”ヴァン”だが、全力で突進する6トン半のアフリカゾウに腰高の機械が敵う道理が無かった。
だが耐える。牙に掛けられたオリーブ色のロボットは瞬時その場に立ち尽くす。が、2秒で力尽き、とんでもない急角度で地面に頭から激突する。
「トマース!!」
「だいじょうぶだキング。大丈夫、これなら多分鎮まってくれる。」
通信でトマースがかなり自信のある声を出したので、俺はその場に留まって成り行きを見守る。銃やら麻酔弾やらは使わないに越したことは無い。
トマース率いるサルボモーター達は、必死で「ジーク」の興味を別に逸らし、”ヴァン”の傍から引き離す。
ちょっと眼を逸らした隙に、2機掛りで”ヴァン”を物凄い速度で引きずって行った。「もふもふ手」装備の不器用な状態でありながら、眼の醒める早業だ。
彼らはこのような事態に結構慣れているらしい。不心得者をつまみ出すのも、「もふもふファイト」の通常ルーチンという事だ。
その間トマース達は必死で「ジーク」とコミュニケーションを取ろうと試みる。十数機のサルボモーターがその場に土下座して、荒ぶる草原の魂に訴え掛ける。
ゾウの知能は高い。トマース達が何を言わんとするか、「ジーク」に対し何故謝るかをちゃんと理解してくれた。
暴れるのを止め、正面先頭に居たトマースの機体のコクピットシールドを前足でぐりぐりと踏みつけた後、ふんと鼻を鳴らして悠然と水飲み場に去って行く。
まずは一件落着だ。
シバ・ネベは自信たっぷりだった”ヴァン”の頭だが、さすがにかなりの損傷を受けている。機体フレームにも重大な支障が発生したらしい。
点検整備にたっぷり時間を費やし、ようやく作業終了した時にはもう夜10時を回っていた。
作業員達が引き上げる中、ひとりぽつねんと輪から外れて居たエルシイを見付け、俺は手を上げた。この時間まで彼女との接触も禁じられていたのだ。
エルシイは走って俺の前に来た。言いたいことが幾らでも有る、そんな感じがするが、俺から話を始めた。
促して近くの資材に二人で腰かける。
「…何故、あそこで飛ばなかったんだ。」
「飛べないんです!」
悲鳴にも似た叫びを上げる。やはりそうだったか。
エルシイは自分の出した声に驚いて、小さな低い声に変えて話を続ける。
「”ヴァン”は、サルボモーターみたいに気楽に飛んで転がる真似が出来ないんです。そういう風に作られている。」
「最初から分かっていたよ。アレは、「転ばないロボット」なんだな。」
「はい…。」
設計思想の差、いやサルボモーターの設計思想がそもそも異端なのだ。
機体の損傷を防ぐ為には、なによりもまず転ばないように最善を尽す。それが機械として当然の設計だ。「よりよく転がれば損傷を受けない」というツルニハ開発陣の発想こそ、非常識の極みだ。
だがこれ故に、「もふもふファイト」やサルボ格闘が可能となる。転がってもぶん殴られても壊れない魔法のタネが、ここに有る。
「だが飛ぶべきだった。君も分かっていただろう、下手に抵抗して金属部品や角が当たれば、動物は怪我をしてしまう。人工物の方が固いに決まってるんだから。」
「そのつもりでした。でも出来ないんです。あなた達みたいに、あんなに上手に大丈夫な場所を差し出すなんて。」
この娘はサルボモーターの事をよく分かっている。「もふもふファイト」が何故ファイトなのか、その理由をちゃんと知っていた。
単に殴られて転げ回るだけでは、ファイトにはならない。
機体の柔らかい場所、弾力が十分有る場所をさりげなく示し、安全を最優先に確保しつつ動物の意図通りに飛んで見せる。
高い操縦技能とイメージの豊富さを必要とするからこそ、サルボ乗りの興味の対象となる。
単純な力競べでないと見抜く慧眼の持ち主でないと、人間の造物が野生に蹂躙されるだけの不愉快極まりない遊戯に映るだろう。
エルシイは一人でぽつりと喋り出す。
「”ヴァン”は、”ヴァン・ダム”は私の父が作ったものです。ロボット学者だった父は、何時の日にかサルボモーターを越える実用搭乗型ロボットを作ろうと、熱心に研究していました。」
「じ、実用ね。」
「はい。サルボモーターが作業にはまったく使えないのを改良し、より有益な、人間の役に立つロボットを作ろうと努力していました。」
「だがその努力は徒労に終る。このサイズのロボットが必要な作業なんて無いからだ。」
「父のロボットは誰の注目も浴びず、プロジェクトは中止に追い込まれました。要素技術は揃っていたにも関わらず、1体のロボットとして組み上げる事を許されなかったんです。暇人しか振り向かない穀潰しの人類に不要な研究だ、と。」
「ま、まあ、そうかな。」
なんとなく抗弁したくなるが、感傷的な女の子の話の腰を折ることも無いだろう。
「父は実機での研究を凍結し、サルボモーターの運動解析に集中しました。その結果、あなた方がサルボ乗りの虜となったんです。幾日もひたすらビデオに食い入り見つめ続けコンピュータで解析し、誰のどの運動が優れているか、私に浮かされるように説明してくれたんです。」
「もふもふファイトも?」
「わたし、もふもふファイトのビデオが一番好きでした。ライオンやゾウに足蹴にされるサルボモーターが可愛くて、とってもエレガントで、」
「そう、か。」
作業場から漏れ出る光に照らされる、彼女の笑顔は年相応子供の顔だ。
「5年前IRSPが資金協力を申し出たのに、父は一も二もなく飛びつきました。それが軍用だと知ってもです。父はサルボモーターを超える運動能力を持つ機体を作りたかった、それだけなんです。でも、」
「でも、IRSPは君の親父さんの意に反した研究をさせた、そうなんだ。」
「彼らのロボットは壊れてはいけないんです。壊れる為に動くロボットは、求めるモノと異なるのです。父は研究データもパテントも全て奪われ、身体を悪くしてそのまま、」
「死んだのか、」
「いえ、ぴんぴんしてますが。でも設計思想から違う機体に、サルボモーターを超える運動能力を与えようと不毛な研究に没頭して、いつまた倒れるか。」
「それで君は自らロボットのテストパイロットになる事を志願したんだ。親父さんの求める運動を実現させる為に。」
アフリカの空の下、高い星を見つめる彼女に、俺は思った。この娘はいいサルボ乗りに成る。
俺は立ち上がり、彼女の肩に手を置いた。子供はさっさと寝る時間だ。
「明日もまた見せてもらおう。サルボ格闘の大会に君も出場するんだ。」
「できるでしょうか、私に。」
不安げに揺れる瞳に、しかし俺は迷わない。サルボ乗りはサルボモーターで会話するものだから。
「君の親父さんのロボットを、サルボ乗りの連中に見せつけてやるんだ。」
次の日、取材の人間が倍に増えていた。前日の「もふもふファイト」の映像が全世界に配信され、バカ受けしたらしい。
それはまあ、そうだろう。
サルボモーターに次ぐ巨大人型ロボットの実質デビューにしてあの有り様。加えて、巨象の前に土下座する十数機のサルボモーターの絵は、面白かったろう。
飛行機チャーターして記者を送り込むはずだ。、
で、今日はサルボ格闘競技会予選。世界各国から集まった128機が本選枠12機にまで絞られる。
128、という数はアフリカ奥地しかも戦争が世界中で起こっているただ中と考えると、凄い数だ。ただし、俺みたいに付き添いで来た奴も結構居る。
アフリカの大地は突っ走る方にこそ面白みが有るから、要するに競技会を口実に遊びに来たわけだ。
逆に、金の無いサルボ乗りが金持ちサルボ乗りに便乗して長距離輸送の代金を払わせた、という例も多い。
ガチで闘うサルボ格闘家は72名。本物はせいぜい20名で、それ以下の奴なら俺でも綾子でもやっつけられる。
「AYAKOは今回出ないのか?」
とよく聞かれるが、本人は既に格闘に興味が無いのだから仕方ない。幻の大技「空気投げ」はAYAKOスペシャルとして伝説の彼方に消えて行く。
その本人は、
「シバ・ネベさん、本当に”ヴァン”を格闘競技会に出すつもりですか。」
「その為にわざわざ遠征して来たのですから、当然参加します。遠慮は要りません、サルボ格闘の上位入賞者と対戦させて下さい。」
綾子は昨日からこいつとさんざん打合わせし続けている。
ツルニハの商売としては、新型ロボットにサルボモーターがこてんぱんにやられてしまうのは、痛いだろう。
取材も多数来ている中、ボロ負け映像が世界中に配信されるのは阻止したい。たとえ重量が倍出力3倍というハンデが有っても、見た目では分からない。
いつの日か必ずそれはやって来る。機械なんだから、後から作ったモノの方が性能が高いのは当たり前だ。
無論、今日はその日では無い。
綾子の心配は別のところにある。
「正直に言いますと、”ヴァン”は格闘に向いてない構造だと思うんです。転倒時のパイロット保護が十分じゃない。サルボ格闘の形式ではダメージが、」
「それはおかしな見方ですよ。腹部にコクピットが有り重心の低い”ヴァン”の方が、コクピットに掛る荷重は小さい。むしろサルボモーターの方がパイロットが被る被害は大きいのでは。」
「いえ、モーターのテンション抜けで落下するでしょう。膝を持つロボットは。」
古典的な「尻もち」問題だ。
人型ロボットは転倒時には重大なダメージを被ると相場が決まっている。天然の人間だって危ないのだから、二足歩行の宿命だ。
サルボモーターがこの問題から自由なのは、つまりは転ける事を前提とし人間の形から解放されて設計されているからだ。
根本的に衝撃への対策が違う。だが”ヴァン”はその違いの考慮が十分でない、と綾子は危惧していた。
サルボモーターに出来る事が、30年後に設計されたロボットに出来ない道理が無い、という思いこみはどんなもんだろうな。
綾子とあいつの論争は、どこまで行っても決着を見る事は無いだろう。億劫だが、俺が出ていって解決を模索する。
「シバ・ネベさん。綾子の言う通りに、俺達は”ヴァン”がちゃんと格闘出来るか、実際に目で見てぶつかってみなければ信じられない。
どうだろう、今回正規の予選に参加ではなく、特別に審査会の形で格闘性能の実証を行ってみたらいいんじゃないか。」
シバ・ネベも少し考える。彼らとしてもイレギュラーの要素が大きい予選への出場は二の足を踏んでいた、ってとこだろう。
トーナメントだから、1回ごとの戦闘でえぐい策を持ち出す奴も居る。格闘戦のデータが確実に取れるとは限らない。
「なるほど一理ありますね。しかしそれでは正式な参加とは認められないはずです。」
「いいんだよ、サルボクィーンが宣言すれば、大抵の無茶は通るさ。」
機体の製造元の令嬢でサルボ格闘の創始者が奴の隣に立っている。綾子はにこっと笑って俺に尋ねた。
「形式は?」
「10人組み手だな。」
参加者のサルボモーターがぐるりと円を描いて降着する中心で、審査会は行われる。
直径は40メートルほど。それぞれの機体には動力が入っているから、格闘するロボットが飛ばされれば腕を上げて受け止める。
危険だから生身の人間は立ち入り禁止とするが、勝手に入って来るカメラマンなんか知ったことじゃない。
そういう俺も、今回生身で立っている。”ヴァン”の、エルシイのエスコート役に何故かなってしまっている。
インコムで、コクピット内で緊張しているだろう少女と話す。
「対戦する相手は或る程度の上級者だ。お前が思いっきり暴れても致命的な事故には繋がらない。それだけの技術を持つ奴ばかりだ。」
「はい!」
「安心して思う存分動いてみろ。機体が壊れることを怖れるな。壊れた方が良いデータが取れるんだ。」
「はいっ!」
「親父さんもデータリンクで見てる。これが最初の一歩だ。思いっきり行け!」
「はいっ!!」
オリーブ色のまともロボットが円の中心に進む。昨日と違い、歩き方にすこし無駄が見えた。オートでなく手動で動かしている証拠だ。
俺の合図で、大会運営スタッフが対戦者を呼び出す。円の中から1機立ち上がり、”ヴァン”の正面に立つ。
外周でデータ収集を行っているシバ・ネベから通信が入る。10人の対戦者を決めたのは俺だから、一応解説の義務が有るってわけだ。
「キング。1番手はあまり強くない相手ということですが、この選択の基準はなんです?」
「オーストラリア出身の”スプリング”・レイカー、23歳。奴はランキングは低いがパンチにスピードが有る。反面一撃の破壊力は低い。」
「なるほど。重量がサルボモーターの倍有る”ヴァン”には、分がいい相手という事ですね。」
「そちらの格闘シミュレーションのモデルとも近いだろ。問題無いな?」
「お任せします。」
”スプリング”・レイカーはあまり筋のいいサルボ格闘家ではない。若くてハンサム金髪のにいちゃんだが、女騙して機体整備の金を作ってる、て噂も有る。
格闘技術のレベルとしては、俺が認める20人からは遠く、ランキングでも70位近辺。今回の出場者でも下から数えた方が早い。
その辺りの情報を、シバ・ネベは独自に検索して知ったのだろう。「噛ませ犬か」という顔で納得しすまして見ている。
奴の隣で解説する綾子が、俺を見て苦笑する。
彼女はちゃんと知っている。何故こいつが”バネ”を二つ名とするか、シバ・ネベが何を誤解しているか。
サルボ格闘正式ルールでは、審判役を務める機体が2機必要だ。これは双方が絡み合って取れなくなった時に補助をする為だが、もちろんキレて無茶苦茶になった時の抑えでもある。
”ヴァン”の挙動が分からない為に、審判には最高の人材を投入した。
サルボ格闘前年度チャンピオン、メーカー公式チーム・ツルニハ所属のつまりはベンジャミン・ミン・ジャンと、4位のトマース・ハヴェイだ。
対戦する双方とも、この人選に文句は付けなかった。”スプリング”・レイカーにはそんな度胸も無い。
左右を審判機に挟まれて、2体のロボットは15メートルの距離を隔てて向かい合う。この状態から「完全直立制止体勢」を取ってから、戦闘開始だ。
「完全直立制止体勢」は、ただ立つだけでもふらふらするサルボモーターには結構負担の大きな姿勢だ。
だがさすがに、まともロボット”ヴァン”は普通に立つ。前後左右に偏り無く置物のように立っている。サルボモーターならば、これだけでれっきとした芸と言えるのだが。
どちらのロボットも、この体勢からではすみやかな運動はかなわない。一度タメを作ってでないと目的とする姿勢に移行出来ず、当然先制攻撃なども不可能だ。
が、”スプリング”・レイカーはやる。サルボ格闘定石の「瞬間起動」をやってのける。
やり方自体は謎は無い。脚部の空気アクチュエータのロックを解除して機体を落下させ、その勢いを前進に転換する。
口で言うのは容易くとも、一時的に機体のコントロールを失う技だから、素人には真似が出来ない。
これでも奴は一応ランカーだ。
”ヴァン”は通常通りの初動を行う。膝を少し曲げて機体重心を傾け、片足浮かして一歩踏み出す。人間がやるとおりにだ。
だが最初の一歩が満足に地に降りない内に、レイカーはパンチの間合いに入っていた。
「疾い!」
シバ・ネベは素直に驚く。こんな速度で巨大ロボットが動くとは、夢にも思わなかったのだろう。
一般人は皆そうだ。モニターやテレビで再生されるサルボ格闘は、所詮は実寸大ではない。大きなロボットの運動は、カメラを通して見ると間抜けな程にゆっくりと映る。
それが6メートルの巨体の持ち主だと、すっかり忘れてだ。
レイカーの右のパンチが”ヴァン”の首筋当たりにヒットする。が、相手の重量が重過ぎた。”ヴァン”はそのまま前進を続けようと、
「な、なんだこのスピードは!!」
不器用に前に出て腕を伸ばそうとする”ヴァン”に対し、レイカーの左右のパンチが立て続けに当たる。毎秒2発というところか。
こんな速度でサルボモーターが打撃を出せるとは、シバ・ネベは想像もしなかったのだろう。脇に立つ綾子に振り返る。
綾子はにっこりと、完全な営業スマイルで応える。
「シバ・ネベさん。スペック表だけでサルボモーターの能力を判断していましたか?」
「しかし肩部のモーターの反応速度は、」
「シバ・ネベさん。サルボモーターは4本のバネが連動して動く機械です。振動を合成すれば不規則な運動が可能になるし、スペックを越えた速度で手足を振り回せるんです。」
「そんな無茶な。」
確かに無茶だ。”スプリング”・レイカーが今やっている技は、早い話が胴体を左右に振って両手を高速でぶつけるだけ。初心者が最初に覚えるものだ。
彼が優れている点は、理論上真横から殴るしかない攻撃を正面のストレートに誘導し変えるところだ。
アームエンドの軌道が最短になり、小刻みな連撃で相手に反撃をする余裕を与えない。
しかしながら、この技はパワーが乗らない。事実、”ヴァン”は一方的に殴られていながら倒れはしない。
中のエルシイは必死で姿勢を立て直そうとしている。彼女はこの技の効果と対処法を知っていて、ひたすら耐える。
よくサルボモーターを研究している。もし彼女にサルボモーターを与えれば、いい格闘家になるだろう。
状況が固定して”ヴァン”の姿勢が変わらなくなったと見て、レイカーが一度離れる。たっぷり10秒も連撃を続けた。
”ヴァン”も動きだし、レイカーの機体を追う。重量が倍も有るのだから、掴まえるなりぶん殴るなりが出来れば必ず勝てるはずだ。
だが、
「ああ、ぜんぜん追いつかない!」
シバ・ネベの叫びの通りに、”ヴァン”は夢遊病者の歩みでレイカーを追う。
左右にふらふら揺れるサルボモーターは、意図的に振り回せばメトロノーム張りに上半身が振れる。まさにバネをびょんびょんと揺らすのだ。
これを使ってゲロを吐かないで済ますのは、特別な才能が要る。レイカーは乗物酔いに抜群に強い体質で知られている。
こんなものを追っかけていれば、”ヴァン”の姿勢不安定になる。必要以上に傾いだところで、再びレイカーの連撃を食らう。
ダウン。
だが周囲のギャラリーはレイカーに罵倒を浴びせる。素人同然のロボット相手に、40秒も掛るとは何事だ。
”ヴァン”が立ち上がったところで1分が過ぎ、審判が試合を停止する。
この試合はまともロボット”ヴァン”が、サルボモーターと格闘が出来るか、を審査する為のものだ。
”スプリング”・レイカーとの対戦で明らかになったとおりに、サルボモーターが逃げる攻撃をすれば”ヴァン”は絶対に勝てない。
俺はシバ・ネベの所に行って、話をする。
「シバ・ネベさんよ。折角だから、格闘スタイルの違うサルボ乗りを何人か当ててみたいんだが、どうする? これで止めるかい。」
「いや、今のは”ヴァン”の想定する格闘スタイルとあまりにも違い過ぎて、もっと正面からぶつかり合うタイプであれば、」
「よし。じゃあ”JUDO”・ハヤテで行こう。文字どおり柔道スタイルの日本人格闘家だ。」
「分かりました、それでおねがいします。」
シバ・ネベも遊びでアフリカくんだりまで来ているわけじゃない。
サルボモーターを薙ぎ倒して、まともロボットの優位性を示すデモンストレーションが彼の目的だ。
主に開発資金のスポンサーサイドへのプレゼンテーションである、と綾子のツテのヨーロッパのロボット研究者が教えてくれた。
彼の目的からいうと、”ヴァン”があらゆる状況で勝つ必要は無い。
格闘という非常に複雑な運動の中で、スピードとパワーとコントロールをバランス良く表現出来れば十分だ。
もともと開発中のロボットだし、サルボモーターと違い作業させる為の機械だ。可能性を示せれば、更なる開発資金も獲得するだろう。
シバ・ネベが随伴するIRSPの研究員がすっ飛んで来る。”ヴァン”の中のエルシイが、絶対勝てないと連絡して来たからだ。
面子を潰されてお偉いマネージャーさんは怒った。1回負けたくらいで弱気になってどうする。携帯電話で小娘パイロットを怒鳴り上げる。
だが、反論するエルシイは冷静だ。彼女は、”JUDO”・ハヤテをちゃんと知り、また”ヴァン”を熟知する。
「い、いいからやるんだ。これは命令だ!」
反論されて徐々に醒めて来たシバ・ネベは、なけなしの想像力を動員して2体のロボットが柔道するところをイメージし、ようやく何が起きるかを理解する。
「…順関節脚のロボットは、足を払われると面白いように転ける…。」
長大な板バネで構成されるサルボモーターの足は、後ろに湾曲し鳥のような逆関節脚になる。
これを柔道技で払うのはとんでもない難題だ。
しかも巨体故に転倒の許容時間が大きく、ゆっくりと倒れ、倒れる時間で次のステップを踏み転倒を免れる。
にも関わらずやってのけるハヤテは、大した技術の持ち主である。が、彼は俺のお客さんだ。
彼は機体を転倒させる事はできるが、同時に自分も転がってしまう。一度地面に落ちたら、寝技使いの俺の敵じゃない。
果たしてエルシイ操る”ヴァン”は、開始5秒で転倒する。左送り足払い。
エルシイは何を注意しなければいけないかよく知るが、手足末端が重い”ヴァン”は彼女の思う通りには動かない。誰が乗ってもこれ以上のスピードでは動かせない。
ハヤテの神速の足捌きにまったく追随出来ない。
重量が倍も有り、出力が3倍もあるのに。あ、また投げられた、今度は支え釣り込み足だ。もふもふ手装備でものが掴めないのに、さすがだ。
「ぜんぜんだめだな。」
俺の隣で眺めていたサルボ格闘競技連盟委員長が、痛ましそうに批評する。彼の立場からすると、別系統の機体の参入はむしろ商売上有益だ。
サルボ格闘が次の段階にステップアップするチャンスだったのかもしれないが、それは今日ではない。
4度投げられて、試合は終了。シバ・ネベは呆然と立ち尽くす。
30年前に設計され、主要部の構造をほとんど替えていない時代遅れのおもちゃのロボットに、これほどまでの戦闘力があるとは。
いや、実際サルボモーターは役立たずだ。あれほど一方的に蹂躙しながら、未だ”ヴァン”の機体に致命的損傷は無い。まだまだ普通に動いている。
つまるところ、この程度のパワーしか持ってないわけだ。
「次! ”首刈り”ベラドンナ。」
「ま、まだやるのですか!」
シバ・ネベは悲鳴を上げるが、俺はエルシイがまだやれると見て、次を指名する。
外から動きを見ていれば分かる。彼女は絶対的に不利な状況にありながら、必死でロボットをコントロールしている。
あれ程簡単に投げられたのは、むしろ彼女が積極的自発的に動いたからだ。投げられたくなければその場にしゃがみ込めばいい。
アル・エルシイは喜んでいる。決して勝つ事は出来なくても、サルボモーターの祭典の中に身を投じ、自ら演じることに誇りをすら覚えている。
綾子は狼狽えて逃げ出そうとする高級スーツ姿の男を抑えて、言う。
「シバ・ネベさん。貴方は、アル博士が何故『手足末端の重量が異様に小さい、非力なロボット』にこだわったのか、まるで理解していませんね。
今回実証される通りに、人型ロボットはスペックだけで計れるものじゃないんです。乗る人間の技量と機体運動のイメージ、これが全てです。
サルボモーターがろくに歩けもしなかった時分から乗っている私には、言うまでもない当たり前の話ですけどね。」
「どうすれば、私になにをしろと。」
「あんたは、GOサインを出せばいいだけだ。戦ってるのはあんたじゃない、エルシイだ。
エルシイ、まだ行けるな。」
シバ・ネベの電話をひったくって、俺が直接通話する。デジタル通信の向こうで驚いた若い息づかいが聞こえる。
『キング?、…はい、”ヴァン”はまだ正常動作を行っています。』
「よし! タフないいロボじゃないか。」
”首刈り”ベラドンナは、先の中東1000キロレースで「サルボクィーン隊」もやっていた色っぽいねえちゃんだ。本業はファッションモデルだと聞く。
だがこいつの戦い方はえげつない事でも有名だ。
「首刈り」の名を持つとおり、こいつの必殺技は相手の首にぶら下がって引き倒す。
サルボモーターには首が無く直接コクピットのキャノピーシールドになるから、これはほとんどパイロット直撃技だ。
しかも今回、”ヴァン”にはれっきとした頭が付いている。ベラは雌豹のポーズで眼を輝かせ舌なめずりしているだろう。
「始め!」
”ヴァン”の首が落ちて、一時休憩。応急修理にIRSPの整備員研究員が必死で取り掛かる。
シバ・ネベはすっかり落ち込んで、そこらの石に座り込む。毒蛇が居るかもしれない、アフリカは気を抜くと危ないぞ。
俺達の所に、一時コクピットから降りて来たエルシイが近付く。被っていた情報収集用ヘルメットを脱ぎ、まっすぐ俺の顔を見る。
いい娘だ。昨日の迷いもふっきれている。
彼女は言った。
「すいません。まるで歯が立たなくて、練習にもなりませんね。」
「いいんだ。最初はみんなあんなもんだ。それより、お前の父さんからはなにか言って来ないか?」
「データ見てました。笑ってましたよ。「だから言わんこっちゃない」って。」
「そうだよなあ。人型ロボットなんて、なんの役にも立たないもんだ。」
俺はシバ・ネベに振り返る。視線を感じたのか顔を上げ、ひっとびくつく。
ちょっと可哀想な気もするが、巨大人型ロボットなんて冥府魔道に足を突っ込んだ報いだ。最期まで付き合ってもらおう。
「おいあんた。これで終りってことは無いだろう。折角アフリカにまで来て、なんの収穫も無しじゃあな。
それよりだ。これまで戦った相手は、サルボ格闘の競技者としては二流だ。
本物のチャンピオンは、目の前に立っている。ベンジャミン・ミン・ジャン。奴のパワーは歴代最強、うん、どれも出力的には同じはずの機体で、唯一完全破壊が出来るんだ。」
「は、破壊!」
「どうだ、その技を記録してみたくないか? ”ヴァン・ダム”には測定器が山ほど積んでるんだろう、凄いデータが取れるぜ。」
「で、データ、世界最強の技の、」
彼はエルシイを振り返る。もちろんベンの凄技を掛けられるロボットは壊れるし、パイロットは無事では済まない。
彼女は、出来るのか?
アル・エルシイは微笑んだ。
「ロボットなんて、ぶっ壊れてなんぼですよ!」
それから2週間ほど、俺は「世界で一番かっこいい男」として有名であった。
新型ロボットを駆る若い少女パイロットを叱咤激励し、無敵のチャンピオンに何度も挑ませる姿を、報道のカメラが克明に記録配信したからだ。
人にちやほやされるのは慣れては居るが、今回ちと困った。
世界中から若い少女がファンレターを送ってきて、「わたしも指導して下さい」とか「サルボモーターの操縦を教えて下さい」、果ては「結婚して下さい」とか舞い込んで来る。
おかげで綾子にひどく背中を引っ掻かれてしまった。
エルシイは父親と一緒に、再び個人で巨大ロボット研究をすると言う。今度はサルボモーターとちゃんと格闘出来る、勝てるロボットにするんだと張り切っていた。
第五歩 富士山のサルボモーター
京都大原三千院。
KYOTOと言えば日本の中心にあり千年の都として長く栄え、御所や城、神社仏閣が多数在る国際的にも有名な観光地である。
という事くらいは、外人さんだってちゃんと御存知だ。
今回俺達「チームツルニハ」は日本で仕事があった為に、ツルニハが本社を構える京都にやって来た。
サルボモーター専業メーカー「ツルニハ工業」は、20世紀までは弱小自動車・農業機械製造業であった。しかしその淵源を探ると、何故か饅頭屋になる。
「鶴仁波○○堂」、ここが綾子の一族の本家である。俺も前に一度連れて来られた。
京都なんだからゲイシャヤツハシ新撰組、てのが外人観光客のお目当てで、当然そういったものに胸ワクワクさせたものだ。
そう。今日のベンジャミンのように。
「………、ど田舎、なんだな。」
「京都は山に囲まれた盆地だから、ちょっと中心から離れるとこんなものよ。」
でっかい黒人は立ち尽くす。
見渡す限りの緑の山。家はたしかにあるのだが、自然が文明に勝っている。これが本来の日本の風景だ。
綾子は彼女で、ちょっと緊張する。別に意地悪な親戚が居るのではない。むしろ逆で、優しいおばあさまが居て熱烈に俺達を歓迎してくれる。
苦手なのは、
「アヤコ、これが「ツルニハ」の本家なのか。」
ベンはまたしてもバカのように立ち尽くす。
一応は世界企業「ツルニハ」の本家を名乗るのだ。それ相応の立派な構えの店舗を期待していたのだろう。
だが目の前に立ちはだかるのは、昨日今日店を開いたかに見えるこじんまりとした可愛らしい家だ。
一応伝統的木造日本家屋ではあるが、これが17世紀から続く老舗とは、到底思えない。
綾子は別に気恥ずかしく思ったりもせず、淡々と答える。
「こんなものよ。『鶴仁波』は地元では売れないもの。」
売れない銘菓『鶴仁波』。この不思議な饅頭の来歴は一聴に値する。なんとなれば、鶴仁波家の人々の苦闘奮戦の記憶だからだ。
その頂点に、世界唯一の搭乗型人型ロボット「サルボモーター」が君臨する。
が、まあ省く。俺達はおばあさまにごあいさつするので忙しい。
店舗は小さいが、家は大きい。これはさすがと言うべきで、広い庭の植木が十分に手入れされて、庭園の美に関しては門外漢の俺達も唸った。
木造平屋ではあるが部屋が何室もあり、障子襖がするすると開いて大広間になる。百人がとこ座っても大丈夫なのは、それだけ大人数の身内が集まるのだろう。
綾子の祖母、鶴仁波清子さんは品の良い素敵な婆さんだ。これが本来の日本人てものだろう、と素直に納得出来る。
俺もベンも、この人の前に出ては小猫同然になってしまう。なんというか、むさくるしい外人で済みません。
綾子も歳を取るとこんな風になるのだろうか。いや、なってもらいたいものだ。
本人にそう言うと、「50年後をお楽しみに」とぬかしやがる。
麗しのおばあさまとのご対面の後に、本題がやって来る。綾子が緊張したのも、この人のせいだ。
「なんや。おばさままぁだ結婚してなかったんですなあ。ずいぶんとごゆっくりで。というかキングさん、あなたも手ぇが遅い!」
鶴仁波芽衣子、18才女子高生。一回り歳が違うからおばさま扱いにされるが、綾子とは従姉妹だかに当たる。
もちろん美人、ティーン時の綾子思い起こさせる日本人形みたいな少女だが、中身は随分と違っている。
多少の説明が要るな。
鶴仁波○○堂は創業400年の立派な老舗饅頭屋であるが、京都の中央ではなくこんな田舎に本店を構えている。
何故か。18世紀中頃に洛中から追放される大失態を演じたせいだ。
俺には、どうすればただの饅頭屋が市中所払いされるほどの失態を出来るのか分からない。とにかく鶴仁波○○堂は追放され、21世紀半ばに至るも復帰が叶わない。
で、これをし出かした鶴仁波家の血が脈々と受継がれているのだ。
鶴仁波家には2種類の人間が生まれるという。
ひとりは、清子おばあさまを代表とする実に穏やかな思慮深い、老舗を背負って立つのにふさわしい人材だ。綾子も多少はちゃらちゃらしているが、こちらに分類される。
だがもうひとりは、イカれた巨大二足歩行ロボットを作ってしまうほどに冒険心に溢れた、狂気の商売人だ。
鶴仁波芽衣子は、後者に当たる。
いまだ10代でありながら「ツルニハ」の経営に参画しようと虎視眈々、日々努力しているのだ。
勿論彼女の興味の対象は、現在ツルニハが唯一の商品として扱う「サルボモーター」。
ツルニハの広告塔である綾子おばさまのやり方が手ぬるいと、ちくちくトゲを刺して来る。それがまた正しいから、困るんだな。
「月産1000台! 年間12000台のサルボモーターをうちが社長になったら、売ってみせましょう!」
「いや、サルボモーターってそんな需要無いから。高価いし。」
「実は新製品の企画立ててみました。企画書をごらんください。」
御丁寧に、芽衣子は俺達の為に英文の企画書も用意していた。
最近はコンピュータ翻訳の質が格段に向上したから、世界中どこでも意思疎通に不自由は無いが、わざわざ自分で書いてるところが気合い入ってる。
「め、メイドロボ!」
「サルボモーター形式の、人間大ロボット。これを300万円台という、他社の3分の1以下の値段で売る…。」
「既にツルニハの開発部に試作品の製作を依頼してます。みなさんなかなかに乗り気でしたわ。」
「ちょっとまってくれ、MEIKO。サルボモーターってものは、」
サルボモーター形式のロボットは、作業にはまったく向かない。そもそもが静的な自立すら難しいのに、家庭内で家事労働を行うメイドロボとして用いるのはあまりにも無謀。
と言うよりも、家の中で転倒したらどうするのだ。
最近の運動制御ソフトの品質であれば、無人で動かしても或る程度は大丈夫だろう。それにしても、子供や老人だって居る家庭内で。
だが芽衣子は涼しい顔をしている。
「キングさん、そのくらい最初に考えました。その上で、屋外野外専用メイドロボ、いう新しいカテゴリーを開拓するんです。」
「屋外専用、か。」
これには元アメリカ海兵隊出身のベンが唸った。
つまりこのメイドロボは、メイドとは名ばかりの警備ロボットだ。
今や警備といえばロボットやマイクロマシンが全盛だ。しかし、人間の姿を見せることでしか成り立たない威嚇の機能も要求される。
当然人が兵士が立っているべきだが、それは剣呑。狙撃や地雷、自動車爆弾と生身の兵士の危険はうなぎ上りで、どこの軍隊でも警備任務をいかに安全に行うかで苦心している。
人型ロボットを用いる試みも各国でなされているが、十分な運動能力を持つロボットは当然高価で、壊されるに決まっている任務になど使えない。
そもそも頭身大人型ロボットは作業を目的に開発されており、機構が複雑で低廉化が進まない。2041年に至るも未だ家庭用メイドロボが普及しないのは、この為だ。
その点サルボモーター形式のロボットは機構が恐ろしく単純で、安価に作れる。運動能力が優れている事は6メートルという大型で十二分に実証済みだ。
ただ立っていれば良い。だが動く時は機敏に人間を越える能力で走る。出来れば人間相手に格闘して、無傷で制圧する機能も欲しい。
まっとうな人型ロボットには難しいこの要求は、まさにサルボモーターにこそふさわしかった。
改めて芽衣子を見直す。たしかにこの娘はツルニハに次の時代を拓くだろう。だがそれだけに、より大きくスッ転ぶ可能性が高い。
「あ、そやけど家事がまったく出来ないいうわけでも無いんです。6メートル型と違って腕の板バネはあそこまで強おなくていいですから、弾力を弱めて人工筋肉の手指を備えて。」
「それにしてもね、家事労働となると制御ソフトがウチにはまったく無いでしょ。大手ロボットメーカーの研究開発に追いつくのは、時間的にも資金的にも、」
「心配あらしません!」
芽衣子はびっと右掌を俺達に示す。つられて俺も、掌を前に出した。
「触覚感応マウスを使こて、遠隔操作するんです。」
「つまり、手動メイドロボ、なのか。」
「そんなの自分でやった方が早いじゃない!」
「いいえぇ、昼間会社に出掛けていながら家の用事を片付けよ思えば、この機能はむしろ必須です。だいたい今のメイドロボは只のAIですからちいとも気ぃ利かなくてあきません。」
触覚感応マウスとは、手や足に埋めこまれたマイクロチップで様々な機器を操作するポインティングデバイスだ。サイボーグ技術の進展と共に開発が進み、今では普通の人でも仕込んでいたりする。
この技術が優れているのは、単に外部機器の操作だけに用いられるのでなく、触覚を利用してコンピュータが提示する情報も読み取れるところだ。
つまり、字が読める。文章が分かる。また仮想キーボードを作って触覚だけで各キーの表示を読み取り、入力が出来る。それも手指を動かさずにだ。
視覚障害者が触覚に優れ点字を読むのを、効率化したと考えて欲しい。文字認識率と文字種の数が飛躍的に高まった。
また視覚障害というのなら、これを用いて路面や周囲の状況を確実に認識出来る。杖が手の中に納まっているわけで、人工眼球やら電脳処理をしていなくとも困ったりしない。
国連では発展途上国の視覚障害者に処理を施す事を積極的に支援している。
俺がこの技術に詳しいのも、実はサルボモーター操縦にこれを用いる例が近年多くなっているからだ。
現在のトップクラスのサルボ乗りにはまだ居ない。ただ優れたインターフェイスは必ず普及する訳で、10年後には間違いなく触覚感応マウスを使うパイロットが主流になる。
ツルニハの開発部ではそれを睨んで、専用支援ソフトを鋭意製作中だ。
ちなみに電脳化技術は特定の障害者を除いて、世界規模で禁止されてしまった。これを使って悪さをする奴が多過ぎたし、なにより最近の社会情勢ではセキュリティが危な過ぎる。
脳内の情報を盗む為に、電脳処理者を拉致してきて信号拷問する、て話も聞いている。人を遠隔操縦するとかもあるし、とにかくヤバくて使えない。
ま、頭の中で旧態依然たるウインドウが動いてるようじゃ仕方ないな。
さて仕事の話をしよう。
俺達が今回日本に帰って来たのは、映画に出演する為だ。文字どおり、映画館で上映するあの映画だ。
実は最近日本ではちょっとした映画ブームが起こっている。一頃は情報機器で個別に映像ソフトを楽しんでいた人が、映画館に帰って来た。
理由はあまり楽しくない。社会のあちらこちらでテロやら犯罪やらが起きる世の中で、誰もが孤立する事を恐れている。
日本ほどの先進国であれば、無差別テロの可能性は実はあまり高くない。
街のあらゆるところにセンサーが仕掛けられ、自動で武器や爆発物、化学物質、細菌やウイルス、ロボットマイクロマシンを監視している。
個々人の衣服にはコンピュータが内蔵され、常に着用者の情報を警備会社に送り状態を監視している。親は子供がどこに居ても、公共のモニタカメラで安全を確認出来る。
マイクロチップを体内に埋めこんで安全を確認する事も義務づけられた。
それでも犯罪から自由では居られない。組織犯罪者やテロリストは、社会的に孤立した人を狙うからだ。
つまり我が身を護る最後の手段は、やはり人。友人や家族などの生有る者の繋がりと再認識した。
それで映画や演劇などの、皆で時間を共有する娯楽が復権する。無論、劇場側が大金掛けて安全を確保していればこその賑わいだ。
技術革新もある。
映画といえば平たい大きなスクリーンに前から映像を投影するが、これは変わらない。だがスクリーンが凹面鏡になっていた。
フレネルレンズのように平たいままでも高精度な凹面鏡を形成する。これにコンピュータで曲率を計算処理した映像を投影すると自然に、目の負担なく適度な立体感が楽しめる。
凹面鏡の中にコインを入れたら浮いて見える手品の応用だ。
完全な立体視ではないが補助器具を使わず、多数の人間が同時に同じものを同じように楽しめる。つまり、映画なわけだ。
で、今大人気なのが『若太朗』シリーズだ。
80年ほど前に流行したシリーズのリバイバルで、若くて金持ちのかっこいいあんちゃんが、ありとあらゆるスポーツを楽しみながら青春を謳歌する。まあ夢物語だな。
この物語のウリは、主人公の若太朗が様々なスポーツを実際にやって見せる所に有る。吹き替え無しで本当にやる。
オファーが来た時に幾つか観させてもらったが、なるほど主人公の俳優はたしかに運動神経には優れている。
テニスサッカー野球に柔道、ポロにヨットにスキーに登山と、まあ器用にやってのける。只者では無い。
そして次に白羽の矢が立ったのが、サルボモーターというわけだ。
「や、キングさんどうも。よくぞおいで下さいました。いやーこの映画はやっぱりキングさんの御力が無いと成り立ちません。ハハ、どうぞよろしくお願いしますよ。」
コーディネーターがへらへらと笑っているので、俺達もへらへら笑い返す。
俺達は別に映画俳優じゃない、素人だ。だから出演料も安いし、そもそもあんまり映らない。
あくまでも裏方に徹し、主人公の若太朗をかっこいいサルボ乗りに仕立てて見せる。
この仕事を取って来たのは、ツルニハの広報部だ。
ツルニハはサルボモーターに宣伝広告費を出さない。
サルボモーターは2000万円を越える高額商品だし、運用維持費がまた馬鹿高いぜいたくな玩具だ。一般消費者にテレビやインターネット広告を打っても仕方ない。
代りに、このような映像ソフトへの出演協力を惜しまない。
やはり人型ロボットは人に見られてこそ華。身近な環境では絶対にお目に掛かれない機械を人前に出すには、なかなか努力が必要だ。
というわけで、俺達「チームツルニハ」は世界中を駆け回っている。毎度おなじみ地球環境保護エコも、要するにサルボモーターの宣伝活動だ。
しかも他人の金で広告打ってるわけだな。なかなかにえぐいぞ綾子。
今回の仕事は、つまりは主人公「若太朗」とその相棒「垢太郎」役の俳優に、サルボモーターの操縦を教えることだ。
期間は3ヶ月、最終的には「若太朗」はサルボモーターで富士山に登らないといけない。なかなか厳しい条件だ。
「富士登山、ね。」
綾子がうんざりした顔でスケジュール表をぺらぺらとめくる。
映画は正月に公開されるから、おめでたい富士登山は絶対に必要だ。監督の腹案では、なんとサルボモーターが富士をバックに空を飛ぶ、とまである。
「富士登山、ね。」
綾子ははあと溜め息を吐く。無理もない、彼女はサルボモーターによる富士登山のレコードホルダーで、世界記録ブックにも載っている。回数でも速度でもだ。
開発当初のサルボモーターは決められた場所でしか動けなかった。具体的にはツルニハの自動車テストコース、それも駐車場の中だけだ。
安定な環境で地道に研究を積み重ねていたのだが、その頃の技術では一歩も外に踏み出せない。機械もパイロットも能力不足だった。
発表から数年はこの状態で、ようやくサーキットで1周完走できたのが6年後。最高時速20キロでちんたら歩いている。
停滞を打破したのが、小学1年生パイロット「鶴仁波綾子」の登場だ。
綾子は子供特有の柔軟さで瞬く内にサルボモーターの操縦をマスターし、テストパイロットの誰よりも上手になった。
操縦支援ソフトが無いも同然の中、奇蹟と思える機体の運動を次から次にこなしてみせる。
実際に機体が動き始めたので、どんどんと改良が進んでいく。姿勢・運動制御プログラムも、綾子というお手本があればなぞって組み上げられる。
今もサルボモーターの運動制御プログラムは”AY”の文字を冠する。”AYAKO”の略だ。
開発の過程で、富士登山を何度も綾子はやらされた。宣伝活動の分も含めて、およそ300回。おかげで俺達は自由に荒野を駆け回れる。
「ま、乗る本人に会ってみないと話は始まらない。適性というものがあるし、そもそもサルボモーターに乗って酔わないか、それが心配だ。」
「大丈夫です。主演の矢山君はそれはもう本物のスポーツマンですから、絶対です!」
「うん…。」
翌日。
「いやーハハハ、どおも、矢山雄一郎です。いやあ感激だなあ、世界のキングさん、ベンジャミンさんにお会い出来るとは。」
「ちわぁ~す。おお凄ええ、ほんものだぜ。あ、ども、「垢太郎」役の中田国和です、よろしくお願いします。いやしかし本物のキングだぜ。」
ツルニハの工場敷地にあるサルボモーター教習所にやって来た二人の若い俳優は、まあ面白い組み合わせだ。
背が高く二枚目の「若太朗」矢山は、たしかにスターのオーラをバラ撒いていて、今日練習に来ると聞いて駆けつけたツルニハの社員、特に女子社員達に愛想良く手を振る。
一方ライバル役の中田は、唇がとんがった面白い顔をしている。剽軽だが根性がありそうだ。
まんま映画の役そのものなのだが、これは仕方がない。そういう人間を連れてきて、そういう役をさせているのだから。それだけ過去のシリーズの影響が強いという事だろう。
彼らには綾子は前に打合わせで会っている。サルボモーターについて事前の心構えなどを説いて来たらしい。
と言っても、巨大人型ロボに乗ってこれを操縦する、てのは日常の感覚では想像も出来ない。他のスポーツの経験がまるで役に立たないから、さあどうしよう!
挨拶も早々に、教習に使う機体の傍に立つ。
今回用いるのはツルニハ所有の教習専用機で、完全にノーマルに調整されている。何故か赤青黄色白の派手な塗装が施してある。
綾子はヒーローである矢山の専属教官。俺は中田の専属になる。
ちなみに映画における俺の役は、そのまんまサルボモーターの教官だ。彼ら二人が所属する大学のクラブ「二足歩行同好会」で、操縦を教えるわけだな。
映画の筋はこうだ。
金持ちのボンボンが集まる白都大学「二足歩行同好会」に所属する「若太朗」は、キャンパスの人気者。金と暇を持て余して、サルボモーターなんてバカ高い玩具で遊んでいる。
天才肌の「若太朗」に嫉妬する成金の息子「垢太郎」は色々と頑張るが、女の子の人気はもちろん「若太朗」のものだな。
どうのこうのと青春グラフィティがあって、二人は日本国中からサルボ乗りが集まる「富士登山」にエントリーする。
富士の裾野に遠征して来た二人は、そこで悪漢が女の子にいたずらしようとするのを鉄拳で制裁し、悪のサルボ乗りと遭遇する。
また、別荘に滞在中であった金持ちのおねえさまでサルボ乗りの名人「あやこさん」にも出くわし、富士登山の極意を伝授される。
最後には悪の妨害をはねのけて見事登頂に成功。フライトユニットを装着した機体で空を飛び、お正月のおめでたさはいや増すばかり、という寸法だ。
「いいのか、ベン。こんな役で。」
「イェ~、ヘーイBOSS、Youブチノメスノガ、Meノビジネスデース。」
悪のサルボ乗りの役をもらったベンは、大喜びで変なガイジンの振りをし続ける。あまりにレトロで典型的な悪役ぶりがいたく気に入ったらしい。
さっそく教習に移る。
完全に電源を落として降着姿勢に固定している機体に、タラップを使って乗り込む。
この教習所は日本で唯一サルボモーターの操縦を教える所だから、日本人サルボ乗りは必ずここで第一歩を踏み出す。職員は素人扱いにも慣れている。
サルボモーターはもちろん一人しか乗れない。教習用であっても教官が隣に座ってくれない。遠隔で指導するし、機体のコントロール権も握っている。
「よおしKUNI、電源投入するぞ。始動スイッチを押せ。」
「はい、よろしくお願いします。」
ぶうん、とエンジンが始動してターボコンプレッサーが回転を始める。
最近の若い奴は、機械が振動するだけでまず驚く。内燃機関搭載の自動車に乗った事が無いからだ。
ハイブリット発電機で動くサルボモーターは、いまや遅れた動力搭載機械として知られる。輸送トラックも含めて、今日先進国の街中で見掛ける車両は電池で動くものばかりだ。
フィーンとターボコンプレッサーが回転数を上げ、腕脚の風船にエアが送り込まれる。ばりばこと膨らむ音が緊張と期待をどんどん高める。
「クッション内圧正常値へ。KUNI、立つぞ。」
「お、おうお願いします。」
遠隔操縦のパネルを操作して、機体を立ち上がらせる。斜めに傾いだ胴体が一度前に出て水平に近くなり、すぐ後ろに振り戻って、
「うわ。」
「よおし立った。そのまま安定するのを待て。」
サルボモーターは6メートルの巨体だ。これほど大きくなるとスケール感が狂う。自分では機体が落ち着いたと思っても、外から見ると大きくゆっくり揺れていたりする。
だがここまでの過程はすべてオートで行っている。パイロットは何も操作していない。サルボモーター30年の研究の賜物だ。
俺が始めた頃は、この過程までも半分マニュアルだった。こいつらには分からないだろうな。
振り返ると、綾子が指導する矢山の機体も立ち上がる。綾子が最初に乗った時は自立も無理で、クレーンで機体を吊上げ立たせていたらしい。
パネルが機体の安定直立を示す数値になる。
と言っても傍目にはやはりふーらふらしているのだが、乗ってる本人はがっしり止まっていると感じる。揺れてるのは自分の呼吸のせいだ、と思うものだ。
「よしKUNI、まずはオートパイロットでお試し運転をする。しばらく機体が勝手に歩き回るから、手のコントローラの感触を確かめろ。サルボモーター操縦の基本は、手だ。腕の振り方を覚えると、大体動かせる。」
「りょ、了解。」
俺は左右に立つツルニハの教習員と顔を見合わせて、初心者用ガイダンスソフトを起動する。誰かがくすりと笑った。
KUNIの目の前のナビゲーションパネルでは、いきなり「綾子おねえさん21才のみぎり」の映像が再生される。声が高く若々しい。
『さあ、練習だいいっぽぉ! サルボモーターで教習所内を歩いてみるよお。ぜったい転けないから、だいじょおぶ!』
転けない、てのは大嘘だ。KUNIは午前中だけで7回転んだ。自分ではなにも操作せずオートパイロットに任せていて、だから、心臓バクバクする。
「こ、これは、これはこんなに転んで、大丈夫なんすか。」
「いやわざと転けるようにプログラム組んでるから。だがこんなもんだ、サルボモーターの転倒はいきなりで初心者にはどうしようもない。転ぶのが普通だと身体に叩き込ませるんだな。」
「でも、なんだかまったく分かりません。」
「分かれば初心者卒業だ。」
「でも、『あっとびっくりぃ!』は無いでしょお。」
「アハハ。」
一度機体から降りてきて休憩するが、昼食など食わずにぐったりする。それでいて吐いたりしないから、こいつは大丈夫だ。
サルボモーターへの適性は、まずは酔わない事に尽きる。これは自動車酔いとはまったく異なる原理で起こるから、事前には判定しにくい。
つまり、サルボモーターではパイロットは不断の緊張にさらされる。自動車みたいにぼんやり乗っているなど出来ない。常に転倒の恐怖に怯えながら、一歩ずつ踏み出す衝撃を感じる。
この状態での乗り物酔いは緊張に耐えられずに神経が参ってしまうことで起き、振動で三半規管が狂うのではない。
やがて機体の歩行が自分が歩いている事の拡大と感じられると、緊張が逆転して喜びに替わる。そうなって初めて、機体操縦の教習を開始出来る。
「あ、あーあ~。」
「うん?」
振り返るとKUNIが矢山の方を見ている。こっちと同じく午前中の教習を終えて降りて来たヒーローが、ゲロを吐いていた。
訓練期間は3ヶ月とはいえ、毎日出来るとは限らない。教習と平行して撮影も行われる。
これは一種のドキュメンタリ仕掛けになっていて、役者がサルボモーターに慣れてどんどん上手くなっていく過程も、ちゃんと物語に織り込まれるわけだ。
そういうわけだから、二人ともなかなか真剣に取り組んでいる。単に操縦だけでなく、サルボモーター界についても自主的に研究していた。
「妙ですよね、キングさん。」
「ん?」
KUNIが言うのは、誰あろう綾子のことだ。
綾子はインストラクターとしては世界最高の腕前を持つ。一国の王様からインドの財閥総裁の爺ぃまで、彼女の手解きでサルボモーターに馴染んだ者は多い。
KUNIも何度か個別教習してもらって、その点については疑問を持たない。だが、
「綾子さんって、どこが優れているのかよく分からないすよ。いや、世界中のトップクラスのサルボ乗りの映像を見ましたよ。キングさんの受け身なんか、背筋がぞくぞくっとする凄味があります。でも綾子さんは。」
「どんな感じがする?」
俺がにやにや笑うので、KUNIと矢山は顔を見合わせる。どうやらこの話、矢山が最初に気付いたらしい。
スポーツ万能の触れ込みどおりに、ヒーロー矢山は初日のゲロ吐きまくりを乗り越えた後は一気に上達を見せる。彼はお手本を忠実になぞる才能があるらしい。
こういう人間の訓練には、綾子の指導は最適だ。なにせサルボモーターの運動の基準は彼女自身なのだから、彼女の真似をすれば上等。
矢山はこう言った。
「うーん違うんですよねえ、トップクラスのサルボ乗りの人達の走りは、どれもひらめきやら飛び抜けて目に入るブリリアントな運動があります。それが彼女の走りには無い。
他の凡百の、あ失礼、ですが敢えて使いますが、他の普通レベルのサルボ乗りの走りとほとんど変わらないんです。
もちろんその人達の中では、綾子さんが一番早く、一番上手く、一番滑らかなんですが。」
「そりゃあ、綾子にとっては最高の褒め言葉だな。」
俺は立ち上がり、二人を見た。
今日は綾子はこの場に居ない。彼女は相変わらず忙しく世界を飛び回り、欧州の鉄鋼業の大物と会うことになっている。
「綾子の走りが他の奴と変わらないのは当たり前だ。
サルボモーターの運動制御プログラムは最も基本的な部分を綾子が作り上げた。綾子の動きを元に、サルボモーターは動いている。
だから最適な走りを追求すれば、誰もが綾子にならなければいけない。当然、そのレースを最も上手くこなして見せるのは、綾子本人だ。」
「でも、最高レベルの人達は違うすよね。」
「ああ違う。必死で違えている。綾子の走りを越えられた者が、現在のトップの連中だ。」
「つまり、綾子さんが基準。」
「極めて高い位置にある標準だな。ほとんどの者はそこまで辿りつけない。今後もそうかは分からないがな。」
二人とも、なんとなく腑に落ちない顔をする。
俺は、今日の矢山のコーチであるベンに話を振る。綾子が居ないからではないが、午後から二人にはサルボ格闘をやってもらう。
デカい黒人は座って甘酢ナマズフライバーガーを齧りながら、彼なりの綾子評を語った。
「スピードレースでは分からないだろ、やっぱ。サーキットのアスファルトの上じゃあ、あまり変化を入れられないからな。
だが格闘になると、今でも綾子は凄いぞ。独自の世界を作っていて、誰も近づけない。真似しようにも出来るとは思えない。」
「格闘ですか。」
レースについては或る程度予習してきた二人だが、さすがにサルボ格闘にまで手が回っていない。
今回の撮影に格闘はほとんど必要無い。効率化の為には余分な方に頭を使っている時間が無いわけだ。
「格闘、いいすね。俺達にもおしえてくださいよ。」
KUNIが軽薄にも、こいつは元々が軽薄だが言い出したことはやってのける根性が有る、墓穴を掘った。午後はもちろん酷い目に遇う。
ベンは付け合わせのポテトフライをがばあと呑み込むと、立ち上がる。
「論より証拠でやってみよう。形だけだがちょっと綾子スタイルを見せてやるよ。」
未だ初心者の二人に何故サルボ格闘させねばならないか、勿論操縦技術の習熟を早める為だ。
二人のレベルは初心者第3段階、てくらいだ。足運びは未だオートのままだが、腕を弄って方向転換くらいは出来るようになる。
これから第4段階オフロードに突入する前の最終訓練として、自発的に転ぶ経験をする。
サルボモーターは走行中には丸く転んで姿勢を元に復元するよう設計されている。だが、或る程度の速度が無ければ普通にべちゃっと潰れて起き上がれない。
低速での転倒ではどうしてもそうなってしまう。実際彼らのレベルで教習所のコースを歩いていては、姿勢復元する程の速度に達しない。
こういう時は、自発的に転ぶ努力が必要だ。自ら路面に頭を突っ込んでいく勇気が要る。
歩行訓練ではそういうガッツは示せない。やはり格闘という、頭に血が昇るシチュエーションの助けを借りるべきだ。
矢山とKUNIの機体が立ち上がり、北極星を描いたベンの黒い機体が機動する。俺が二人を誘導し、ベンに立ち向かわせる。
「やり方は簡単。ベンの機体に触ってみろ。」
「触るだけですか。」
「おう、ふたり掛かりで追い込んでいけ。」
ここ1ヶ月の訓練で、二人は相当自由に動き回れるようになった。教習所内でつっかえる事はもう無い。
二人の機体がぺこりと御辞儀をする。ここまで自在に動かせるわけだ。
ベンの機体は静止したまま、まず初動が早かった矢山の機体がタッチする。が、すっとかわされた。
ベンは歩いていない。腕を少し後ろに下げただけだ。それだけで、矢山は暗いアスファルトに突っ込んで行く。
「うぉ、おい矢山、なにやってんだ。」
「うわああああああ。」
ベンは横に動いて転けた矢山の機体から十分離れ、KUNIの機体をくいくいと誘う。
KUNIは、ベンの肩や腕といった末端に触るとかわされると知って、コクピット周辺に狙いを絞る。真っ正面から右手を伸ばす。
「う! あ。」
ベンの機体が急速に前に出て、出たように見えてもただ屈伸をしただけでその場を動いて居ない、KUNIは驚き機体にブレーキを掛ける。
膝のバネが伸び上がり棒立ちになるKUNI。ベンが右手を上げて触ろうとするのに反応して腕を振り上げると、そのまま後方に転倒する。
矢山もKUNIもどちらもベンに触っていない。触られていないにも関わらず、転倒する。
「これが綾子スタイルだ。」
「す、すげー。」
「なんですかこれ、気の力ですか。」
「いや、キング、KIとかは使ってないよな?」
「合気道には似ているが違う。つまりサルボモーターの機体、ハードにしろソフトにしろ乗っている人間の反応も含めて、すべて綾子はお見通しなんだ。初心者だけでなくサルボ格闘の熟練者でも、綾子にはそんな風にあしらわれる。」
誰よりもサルボモーターを熟知するからこその、魔法。サルボクィーンと呼ばれる由縁だ。
矢山より早くKUNIの機体が起き上がって来た。
「すげー、すげーすよサルボ格闘。もっと教えて下さい。」
「言われなくても今日は午後全て、これやるぞ。」
「うおおーー。」
「こりゃあ血の雨が降るなあ。ハハハ。」
結局映画の中での俺の役は、「二足歩行同好会」の顧問を務める大学の准教授という事になった。
というわけで、講義の真似事なんかやらされる。黒板にチョークで字を書くなんて生まれて初めてだ。そもそも黒板使うってのは、どこの発展途上国の小学校だ?
綾子は俺の背広姿を見て、くくっと笑った。
「いいじゃない。あなたそのまま大学のセンセイになっちゃいなさいよ。」
「まあ一応、ロボット社会学の修士号は持ってるからな。インターネット大学の。」
撮影終了で撤収する学生役の若い女優がみんな手を振って来た。俺も綾子も世界的有名人だから、彼女達にサインなんかねだられたりもする。
「鼻の下伸ばさない。」
「おお、はい。」
これで俺の出番は終りだが、もう一つ仕事が残っている。
映画のクライマックスはサルボモーター富士登山レースで、優勝した「若太朗」矢山がフライトユニットを装着したサルボモーターで空を飛ぶ。
この飛行はさすがに素人にはまるっきり無理だ。俺がスタントをする。
「フライトユニット、なんて大袈裟な名前を付けたのは、誰だ?」
「私よ。」
「…。こんな名前付けたら、知らない人はサルボモーターが本当に空飛ぶと思ってしまうじゃないか。」
「飛ぶんだから仕方ないじゃない。」
「それよりも、あっちの方の仕込みはどうだ。」
「ううン、来るわよ。もう大急ぎで準備してる。」
実はサルボモーターによる富士登山は7年前に禁止されている。理由は簡単、誰でも登れるようになったからだ。
綾子の300回の富士登山の成果は運動・姿勢制御プログラムとして結実した。これを用いると、或る程度の技能を持つサルボ乗りなら無理なく登れてしまう。
となると、今度はサルボモーターによる環境破壊や事故が心配になった。
これは仕方ない。そもそもが富士山は一般登山客がやたらめったら多い観光地だ。
綾子のサルボモーターによる登山は新規技術開発ということで、日本政府による手厚い支援があった。金は出さぬが、規制緩和等の便宜を図ってくれたわけだな。
実験中の一般登山客の規制も、警察がちゃんとやってくれた。だが他のサルボ乗りも登るようになると、話は替わる。
現在ではツルニハでさえ、山岳運動研究はもっと人気の無い外国の山でやっている。綾子も3年前テレビ取材で登ったのが最後だ。
今回の撮影では禁を解除して、サルボモーターの集団での登山が行われる。季節は夏、長期休暇のど真ん中で日本中のサルボ乗りを動員するのに丁度良い。
これも全国民的人気沸騰「若太朗」シリーズ故の特別措置だ。エキストラも大動員して、ちょっとしたお祭り騒ぎになっていた。
「サルボモーターは50機来るわよ。登るのは30機だけど、車道の通っているところまではパレードね。」
「ううむ、ちょっとした集会しなきゃいかんな。」
「ツルニハでそっちの手配はしてる。ついでに峠下りレースしたいところだけど、流石に許可は下りなかったわ。」
何を隠そう、サルボモーターの生まれたこの日本では、公道での走行が5年前まで禁止されていた。
だから日本人サルボ乗りは僅かな例外を除いて、ロードレースは苦手な奴ばかりだ。オフロードや遊泳、格闘に偏っている。
現在は解禁されたとはいえ高速道路乗り入れ禁止だし、そもそもトンネルが多い日本の道はサルボモーター向けではない。
6メートルの巨人を低いトンネル内で走らせる特別なテクニックさえ開発された。日本人名物「モンキーウォーク」、四足歩行だ。頭上250センチの屋内駐車場でも時速30キロで入ってみせる。
映画に話を戻すと、つまり「若太朗」はこれら並み居る強豪を抑えて一番で登頂に成功する、という絵が撮りたいのだ。
とはいえ3ヶ月特訓した程度では、彼らの足元にも及ばない。ガチンコのレースをするわけではないが、見た目あまりにも劣っていては観客も興醒めしよう。
しかし、秘策は有る。
監督はやはり、多数のサルボモーターが富士山をよじ登る中に、主人公達の機体を配置したかった。
誰が考えてもそれは無理。道は一本きりしかなく、機体は1機ずつしか通れない。
熟練者が歩いている中にど素人を混ぜるのは、やはり危険と諦めるしかなかった。俺の見込みどおりだが、一応試しに自動車道でやってみたぞ。
舗装道路でさえこんな混雑になるのでは、とさすがに監督も諦めた。山上に多数の機体を駐機させるのも剣呑だ。
よって撮影は熟練者達の登山の終了後となる。
「やっぱり、3ヶ月くらいじゃ話になりませんね。」
矢山は半ば自分を突き放して、そう言った。KUNIも悔しそうだが、技量の違いは一目瞭然。あの中に混ざってはどうしても邪魔になる。
「でもいい絵ですよ。CGじゃこれは撮れない。」
再び矢山が言う。サルボモーターの列を眺める姿は、さすがはスター、ヒーローだ。実に絵になっている。
俺達は今回、映画についてちょっとは詳しく知る事が出来た。役者を見る目も多少は養えた。
冷静客観的に見ると、俳優としての才能は矢山よりもKUNIの方が上だ。誰もがそう言う。
しかし映像、それも擬似三次元映像にしてみると、途端に矢山は輝いた。妙な言い方だが、三次元映えのする男だ。
3DCG全盛の現在、俳優でさえ作り物が当たり前の世の中で、これは得難い才能だ。彼が画面に出て来ると、観客はほっとする。ほんものの人間に会った気がする。
KUNIにその要素が無いわけではない。いや、目の前でくちゃくちゃと大きな唇を動かして貝ヒモを齧ってる姿は、実にうっとおしい存在感が有る。
それが画面では伝わらない。恐らくは、彼は役者として出来過ぎているのだ。作り物として振る舞う事に慣れ過ぎた。
矢山の資質は天然のものだ。この時代、この映像表現、このハードウェア上でしか通用しないだろうが、今それが求められる。
まさに時代が呼んだ男だった。
「よし、じゃあお前達も機体に乗れ。本番行くぞ。」
ツルニハが用意した富士登山の秘策とは、まさにツルニハにしか出来ないものだ。
過去300回の綾子の登山で収集したデータを用いて、富士登山専用操縦支援ソフトを開発した。誰が乗っても問題なく登れるように、コース全域で運足から手での機体の支え方までスケジュールしている。
それでもまだ危ないから、或る程度の距離ごとにアンカーを置いてワイヤーで機体を繋ぎ、滑落を防止する。先ほどまでの熟練者の登山は、その設置作業でもあった。
そして最終安全措置として、俺とベンが付いて行く。万が一危険な転倒をした場合、俺達の機体で拾い上げブレーキを掛ける。
「じゃあキングさん、お願いします。」
監督とコーディネーターに直々に挨拶されて、俺達は歩行を開始する。
「キングさん、ちゃんと付いているすよね、いますよね。」
「心配するなカメラに映らない位置に居るだけで、ちゃんと傍で見てる。」
最後の1ヶ月は二人とも山岳走行をみっちりと経験させたが、それでもオートによる運動は恐ろしいものだ。一足ごとに自分の意志が反映するマニュアルの方が、よほど安心出来る。
これがサルボモーターの醍醐味という奴だ。
単に移動するだけならば車輪の方がよほど効率がいい。いや山登りなら飛んだ方が楽だ。
わざわざ困難かつ精神的負担の大きな二足歩行ロボットを用いるのは、まさに自分が歩く為なんだ。
一足ごとに大地に触れる感覚、これが得られるからこそ無理してロボットに乗っている。
効率は悪い、手間も時間もロスする。だが機械に乗せられているのではなく、自分の意志で歩いていると自信を持って言える。
いや逆だな。
生身での登山よりもなお裸で自然と向き合っている、魂が直に世界と接触する。それがサルボモーターに乗るという行為だ。
KUNIはその境地にほんのわずか辿りついた。矢山はオートパイロットを信じる道を選ぶ。
僅かな期間で得た二人の選択は、どちらが正しいのだろう。今後二度と乗らないのであれば、見栄えの良い矢山の方か。
映画を見る人はどう感じる?
「矢山、大丈夫か。」
「大丈夫です。しかし、このオート制御、なんか変です。不自然に揺れます。」
「KUNI、どうだ。そっちも揺れるか。」
「揺れてますが、風ですかねえ。シールド半分開けて風通してますが、吹き上げる前に揺れます。」
さすがに綾子のデータだ。風に機体を任せて姿勢安定の補助にしている。オートパイロットで動く彼らの足元は、上体が揺れるにも関わらず確実な歩みを進めている。
しかし本来人間が徒歩でのみ進む山道を、6メートルの巨人が歩くのは無理がある。
富士山は登山客が多いからまだ道は広いが、場所を選ばなければ2機がすれ違ったりは出来ない。
「やはり、矢山の方が早いか。」
オートパイロットに任せて素直に進む矢山は、かなりスムースに機体を進めていく。
対してKUNIは無駄が多い。機械の指示するコースに従わず、慎重に歩を置く場所を定めてほとんどマニュアルに近い操作をしている。
まあこれは仕方ない。主人公である矢山が中央を歩き、画面の端にKUNIが映るように監督の指示がある。最適コースを通れないKUNIに負担が掛るが、よく頑張っている。
それにKUNIは俺達のコーチの他にも自主練習を行っていた。ツルニハの技術者に頼んで、夜間の特訓を重ねた。
主人公のライバル役というのはそれなりに忙しく、また無茶な演技をやらされる。にも関わらず操縦練習に時間を割くとは、見上げたものだ。
成果は着実に表れており、道が険しくなるにつれてKUNIと矢山の機体の動きに差が無くなって来た。
『いいわ矢山クン、ここからは私が誘導する。オートプログラムをガイドモードにして、マニュアルで足の動きをトレースして。いい?』
矢山の機体が遂に止まった。オートでは登るのが難しい傾斜に到達したのだ。
いかにデータが揃っているとはいえ、山は毎日その表情を変える。最終的にオートでは間に合わなくなるのも計算の内だ。
綾子は先に山頂に登って、二人の到着を遠隔でサポートする。更には、触覚感応マウスを仕込んだツルニハのテストパイロットが二人の機体を代りに操縦する事も計画に入っている。
「大丈夫です。慎重にやれば、間違いはなく、」
さすがに優等生の矢山でも対応できなくなっていた。やはり自主的に歩く気概が無いと、サルボモーターは鈍い人形のままだ。
もう1ヶ月あればと思うが、さすがに技量が追いつかない。足を上げても踏み下ろせず、同じ場所で足踏みを繰り返す。浮き石が心配で荷重を掛けられない。
同じプログラムを使っているのだから、KUNIもここで引っ掛かる。傾斜を登れない。俺に連絡してきた。
「キングさん、オートパイロット切っちゃってもいいすかね。ここはアレでいくべきと思うんです。」
「出来るか?」
「ばっちりす。と言うかあ、ここはアレでしょう、普通。」
KUNIが言うアレとは、日本人名物「モンキーウォーク」だ。手を着いて四つんばいで歩く姿勢は、確かにここでこそ使うべきだ。
格好は良くない。また綾子のオートプログラムは、或る程度の人間が使えば二足歩行のままでも登り続けられる。遠隔操縦で肩代わりするなら問題無い。
しかし、素人に毛の生えた程度のKUNIならば、
「よし、特訓の成果を見せてみろ。」
「了解。へへ、ここは垢太郎が若太朗に勝っちまう番てことですかい。」
KUNIの機体が矢山に近付いていく。足踏みし続けるヒーローを横目に、地面に手を着きしっかりと荷重を分散させ、登り始める。
矢山が停止して見送る中、猿歩きのKUNIは急傾斜をなんなく上がる。矢山から通信が入る。
「キングさん、あれは僕には出来ない。」
「KUNIは自力で特訓してたからな。努力は人を裏切らないってとこか。」
「うんー、参ったなあ。」
監督からも通信が入る。シナリオと違う結果になってしまっては意味が無いと言うのだが。
「そうは言ってもこれが現実だ。もちろん、ツルニハのパイロットに制御を移せばちゃんと登り続けられる。どうするね。」
『うーん、普通どんなに頑張っても、中田君が矢山君を上回ることって無いんですよね。参ったな。』
「カントク、仕方ないですよ。僕にだって向いてないものはあります。」
矢山のスポーツマンらしい台詞に、監督も腹を決めた。このシーン、ライバルの垢太郎が若太朗を抑えて富士登山成功、にシナリオを書き換えた。
その代償というわけではないが、二人のチームは別に優勝などしなかった事になる。
ま、シリーズも長くなると色々目先を換えてみなくちゃいけないな。
猿のような不格好な姿で、それでもKUNIは登っていく。警察により指定されたサルボモーター許可高度まで一直線に、山肌にへばりつきながら必死で進む。
矢山は言った。
「いい絵じゃないですか。カントク。」
まったく、人の努力が報われる場面てのは、胸がじーんとしてくるものだ。
シナリオの変更は意外な所にまで及ぶ。
ろくに山を登れない矢山のサルボモーターが、空まで飛ぶのはおかしいというのだ。
監督は困惑するが、主人公とそのライバル役が主張するのだから致し方ない。
というわけで、劇中でも師匠である俺が手本に飛んで見せる事になった。
二人のヒーローは、偉大なサルボ乗りの姿を富士山麓で浴びる朝日の中で見上げる、というエンドだ。
綾子は言う。
「ほら、やっぱりこうなった。基本的に無理なシナリオは、最終的に修正されるのよ。」
「確かに、なるべくしてなったって感じだな。」
「ラストシーンに失敗は要らない。一発で決めるわよ。」
サルボモーターフライトユニット、早い話がパラグライダーだ。揚力が足りないからセールが複葉になる。背中に付けたプロベラで飛んでいく。
「ほんとに飛ぶのか、これ。」
「理論上は。ただし、着陸する際の機体制御はコンピュータによる支援が無いも同然です。特に急斜面への着陸は。」
「誰もやったことが無い、ってわけだ。」
ツルニハの技術者ってのは、皆こんな奴だ。無茶は熟練パイロットの技術でなんとかしてもらう。
小学1年生パイロット綾子が馴らした毒が、まだ回っているな。
そうは言っても、俺にだって秘策は有る。経験した事の無い機動を実現するには、俺が最も慣れた、ガキの頃からがっぷり取り組んで来た古い制御プログラムを起動する。
”AY 2.38”、ツルニハがリリースした第2版の最終バージョン。もう12年前の代物だ。
綾子の動きしか入っていない、最もプリミティブな運動制御プログラム。
「あら、またそれ使うの。」
リモートで機体パラメータをチェックしていた綾子が、呆れたように言う。そんなもの未だに使っているのはあなただけよ、なんて軽口を叩く。
「命が掛かってる場面じゃな、これが一番頼れるんだ。」
「OK。世界の受身王に口出ししない。じゃ、GOOD LUCK!」
「おう。」
山肌を吹き上げる風に乗って、初めてセールは2トンもの機体重量を宙に持ち上げる。単独の推進力では不可能だ。
ふわりと飛んだ。あまりにもあっけなく。
見上げる撮影陣、役者スタッフ協力関係、ツルニハの技術者、ベンと、綾子と。
2042年日本の正月は、富士の御山を背景に悠然と舞う、俺のサルボモーターで始まる。
第六歩 月面のサルボモーター
「月、ですか。あのウサギがぴょんぴょん餅突きしている。」
「う。 まあそれです。」
2038年、そんな台詞を綾子は吐いたらしい。
NASAアメリカ航空宇宙開発局から、”月面機動歩行ビークル”開発協力の打診を受けた際の話だ。
この提案はツルニハの手に大きく余るものだった。
なにせエア駆動のサルボモーターを真空の月面で動かそうという。無茶もここに極まれり、と誰もが絶句する。
だが当時のツルニハ会長、鶴仁波膳九郎は二つ返事でOKした。
彼が、サルボモーターなる狂気の人型機械をでっち上げた張本人だ。
死んだ人の悪口は言いたくないが、まともな商売人ではない。
100年続いたツルニハ工業を自動車・農業機械製造から、二足歩行ロボット専業に換えたのだ。そりゃあ、俺が株主なら散弾銃持って行ってやめさせるだろう。
事実、様々な内紛が頻発したと聞く。が、ここで潰れないのが狂気を冠される由縁だ。
彼が凄腕のビジネスマンであったのは間違い無い。行く道は険路でも、ずんずんと大股で進んで行く。
サルボモーター誕生前夜を知る人に聞くと、こう語ってくれた。
「膳さんはなー、あの人は自分がロボットに成りたかったんだよ。」
こんな人だから、生まれたばっかりの危険なロボットに、大事な孫娘を乗せようとか考えたのだな。
ちなみに俺は膳九郎氏には表彰台の上でしか会った事が無い。どんな爺さんだったか、もっと話しとけばよかった。
彼は月面用サルボモーター開発にGOサインを出した直後におっ死んでしまった。享年92歳。ちなみに清子さんは後妻で15も歳が離れている。
とまあそういうわけで、爺さんの置き土産が、このプロジェクトだ。
「キングさん!」
砂漠の空港で俺を出迎えたのは、日本人の技術者だ。
ツルニハ開発部に所属する剣崎駿一はNASAに出向して、月面仕様サルボモーターの試験とソフトウエア適合作業を行っている。
「おうシュンイチ、どうだい。いけそうか。」
「うーん、なんというかね。いつの間にか水中作業用サルボモーターが出来てしまったよ。」
「は?」
月面は1/6重力というのは、子供でも知っている。エア駆動という”欠点”を排除して完全クローズドサイクルで作られたサルボモーターは、水中で低重力環境下試験をされていた。
「水中ってことだと、手足のチューブには水が入ってるのか。」
「うん。いやもちろん空でないと困るんだけど、どうしても浮いちゃってねえ。まあ動きが鈍くても月面ではちゃんと対応出来るから、地球環境用はオーバースペックなんだ。」
剣崎は、ツルニハには勿体ない天才エンジニアだ。彼の才能にふさわしい仕事をツルニハは与えられない。
しかしながら巨大人型ロボットを作っている企業は他に無いので、彼はここに居る。そういう奇特な人材が結構在籍する。
「アメリカで仕事してたら、引き抜きのスカウトが来るんじゃないか。」
「来た来た。IRSPが新しく人型ロボット作ってるだろ。」
「おう、アフリカでぶっ壊して来たぞ。」
「他にも数社、手掛けているらしい。今になって風がこちらに吹いて来てる。」
あまり良い話ではない。つまりは戦争が巨大人型ロボットを必要とするようになったわけだ。
月面サルボモーターもその線上に有る。
俺達は空港から車輪に乗って、砂漠のど真ん中の実験場に行く。
水中実験とは別に、野外で操縦者の訓練をする専用サルボモーターの開発も当然行われた。さすがアメリカはカネの掛け方が違う。
「しかしなんだ。この訓練用サルボモーターは、転べないな。」
「物理シミュレーションの結果だと、サルボモーターは月面では転ばないんだ。だからそれでいいんだよ。」
「うーむ。こんなのの操縦なんて教えられないぞ。」
訓練用サルボモーターは1/6重力を体感する為に、なんと頭上に気球が付いている。上から吊るすのだ。
転ばないだけでなく、動きも緩慢になる。30年掛けて鋭い動きが可能となった開発史に逆行する存在だ。
「大丈夫。今日は風船抜きで荒地を走行する訓練してるよ。地球でがんがん転んでいたら、月面では怖いもの無しだからね。」
「うん。」
何故月面でサルボモーターを運用する事となったのか、これは物凄く説明が必要だな。
そもそも、アメリカを中心とする国際宇宙開発共同体が月面基地を作ったのが、間違いだった。
宇宙空間への進出は軌道上ステーションで留まらない。ゆくゆくは他の惑星にも人間を送り込まねばならない、と当然に月面常設基地が計画される。
長く続いた経済危機の中、宇宙進出の火を消してはならないと、関係各位は最大限の努力をした。政治力も大いに用いる。
で、めでたく月面基地が完成する。2035年の事だ。
意味が無かった。
人間が行って出来ることは、人型ロボットを投入すれば間に合う。等身大作業用人型ロボットは日本の御家芸で、何年も前から月面で活動している。
と言うよりも月面基地の建設自体、人型ロボによって成し遂げられた。
人間は出来上がった後にのこのこやって来ただけだ。
作ったものには人が住まねばならない。しかし、やることは何も無い。
この事態はあらかじめ想定されていた。他の惑星に行くとして、人間が四六時中働かねばならないようでは到底不可能だから、これでいい。
だが予算を握る各国議会は許さない。居るだけで莫大な金の掛る人間を、なぜ無理して常駐させねばならないのか。
誰も反論出来なかった。
そこで、月面に人が居る理由を無理やりこじつける作業を始める。具体的には、遊んだ。
野球サッカーテニスゴルフ、ちっとも面白くない。
極地探検は、活動限界のある宇宙服では非常に難しい。また事故を起こしても助けにいけない。
ならばとモータースポーツに目を向けるが、月面車は時速40キロ以上出してはいけない設定になっている。スピード出して事故を起こしては元も子も無い。
月面飛行機ムーンフライヤーは月面上数十メートルを自在に飛び回る小型ロケットだが、完全自動操縦で遊びようが無い。
まあ月面で怪我人が出てくれれば、宇宙医療の重要なサンプルとなって見事有意義な暇つぶしが出来るのだが、さすがに誰も口に出せない。
NASAの偉い人は頭を抱える。月面で無茶で派手な運動を行い、それでいて人間はまったくの無事。愉快で楽しく人を惹き付ける手段は無いものか。
有るわけが無い。真空の月面で無事に暴れるには、装甲車並の防御力が必要だ。
乗り物を装甲するのは可能だが、人間が見た目自由に活動出来なければ意味が無い。
そんな都合の良いものが、世の中にあるはずも。
有るんだな。何の役にも立たないが、面白く派手に動くロボットが。どんなに転んでも搭乗者が怪我をしない乗り物が。
「いやー、火星に到着した時点でなにもする事が無いとバレてしまったら、言訳のしようも無かったよ。ハハハ。」
偉い人は笑うが、納税者としては顔面が引き攣るばかりだ。俺達は、まあその共犯者となるんだがな。
さて月面仕様サルボモーターだが、かなり大幅な設計変更がされている。エア駆動の部分を完全に排し、ハイブリットエンジンではなく完全電池駆動とした。
電池はいい。月面ではさんさんと降り注ぐ強烈な太陽光で発電が叶う。長い夜の間もバッテリーで、あるいは月軌道上発電衛星から送電されてくる。問題無い。
エア駆動の排除、これが曲者だ。サルボモーターは2040年の視点からすれば、かなり遅れた技術で構成されている。
今設計すれば人工筋肉を迷わず使うところだ。これは空気を必要としない。電力だけで完全に作動する。
が、ツルニハには技術が無い。再設計するカネが無い。
特性が異なるアクチュエーターに換えれば、これまで積み重ねて来た運動制御プログラムがまるっきり使い物にならなくなる。再構築には莫大なカネが掛る。
だが今回、国家予算でカネが湯水のように使えるとなった。有り難い話だな。
NASAからの指示で、ツルニハは人工筋肉技術を持つ企業と共同開発を行う。
「ピルマル・サイエンスインダストリー」、日本語だと「ピルマル理科工業」で通る。最新理論に基づく「統則制御筋」で一躍注目される、人工筋肉技術のトップ企業だ。
無論、それだけが商材ではない。
宇宙関係で言えば「マジックポット」の方が遥かに有名だ。
ピルマル理科工業の「マジックポット」。中性子ミラー技術を用いた核融合核分裂ハイブリット反応発電炉だ。未臨界原子炉のバリエーションだな。
現在の宇宙開発は、完全に「核エネルギー時代」に突入した。
液体水素や固体燃料を用いる化学ロケットもちゃんと用いられているのだが、主役は核エネルギー利用のものに移っている。
主流は外部力型、つまり原子炉から供給されるエネルギーでレーザー光線を作り、ロケットに照射して推進剤を加熱噴射するレーザーアブレーションロケットだ。
この方式が優れている点は、ロケット本体がおそろしく安く作れるところだな。単段式で構造も単純、壊れようがない。可燃物を扱わないから空中爆発の危険も無い。
世界中のレーザー発振基地から順次ロケットに照射していく事で、安全確実に軌道に投入出来る。欠点があるとすれば、少々非力でペイロードが小さい点か。
だがそれも、複数レーザー基地から同時に照射する方法で解決する。ゆくゆくは1000トン級の宇宙船を打ち上げるプランも有るらしい。
アメリカが保有する海軍機動部隊にも、レーザー照射艦てのが必ずセットで付くようになった。ロケットのみならずミサイルの投射にも、この方式は極めて有効だ。なにより弾が安い。
原子炉搭載レーザー艦を数隻集めて照射すれば、重たいロケットでも飛んで行く寸法だ。
もちろん十分強力なレーザーを発振出来れば、原子炉でなくとも良い。EUと日本を中心とする「太陽光衛星発電プロジェクト」では、太陽光レーザーを使う。
太陽光から直接に作ったレーザー光線を海上の受信施設に照射し、水素を生成してエネルギー源とする計画だ。しかし今は、エネルギーを資材打ち上げに流用する。
太陽光レーザー衛星で、太陽光レーザー衛星の資材を打ち上げるわけだ。
軌道上の衛星が増えるほど、倍々で打ち上げも増えて行く。遠からず地球のエネルギー問題は消失するスマートな計画だ。
これとは逆に、ロケットに原子炉を搭載しようてのが「マジックポット」だ。
小型の原子炉で推進剤を加熱噴射して飛行する。原理的には原子炉発明当初から考えられていたが、当然安全上のリスクが付きまとう。
未臨界型の原子炉は連鎖反応を用いない。外部から照射される中性子により無理やり核分裂反応を起こしてエネルギーを取り出す。だから暴走事故は絶対に起きない。
「マジックポット」は恐ろしく少量の核燃料でも、巨大なロケットを打ち上げられる。事故が起きても大丈夫なほどに少ないらしい。
炉自体も強固に作られている。軌道上から落下しても地上まで炉心が崩壊せずに落ちて来る頑丈さだ。
「マジックポット」は中性子ミラーというもので構成される。文字どおり中性子を完全に跳ね返す鏡で、核燃料に焦点を合わせて集中し効率的に反応させる。
このミラーがめちゃくちゃ硬い。
そりゃそうだ、中性子は生半可な物質はするっと透過してしまう。完全反射させるには複雑怪奇な結晶構造を数百段積層した特殊な素材が必要だ。
さらに放射線漏れを防ぐ為に必要以上にミラーを重ね、サザエみたいな形になる。
「マジックポット」はこうして、大気圏突入しても壊れない頑丈さを身に付けた。
安全確認の宣伝の為、NASAでは155ミリ榴弾砲で「マジックポット」の筐体を撃つデモンストレーションまでやった。
標的とされた核燃料を入れていない殻は、爆発で遠くに飛んで行ってしまったがもちろん無傷。
そもそも中性子ミラーってのは、現在の戦車に使われる「再帰性装甲」ってのの親戚だから、強いのは当たり前だ。
米海兵隊出身のベンは徹甲弾使わないのはおかしいと言っていたが、まあそれはあれだ榴弾砲だし。
もっとも環境団体がうるさいから、一度使用した「マジックポット」を地上に回収したりはしない。軌道上には使用済み原子炉がごろごろして、再利用の機会を待っている。
「で、サルボモーター打ち上げるのはどっちだ。」
「質量は2トンと軽いから、レーザーの方だね。高度100キロくらいまでは地上から照射して、それ以降は太陽光レーザー衛星からでステーション軌道まで遷移して、推進剤補給の後に月まで行く。」
「やっぱり「マジックポット」は人間用か。」
「パワーあるからねえ。シャトルオービタ復活も、あれが無ければダメだったろう。」
スペースシャトルは一度廃止になって20年後に旅客専用として復活した。
今度のはロケットエンジンが外付けで、オービタには大気圏内移動用ジェットエンジンしか付いていない。安全かつ安上がりに仕上がった。乗員数も30名が一気に上がる。
当然このシャトルオービタは、月面常駐計画を念頭に開発されたものだ。
今は月面基地も10数名しか収容能力は無いが、ゆくゆくはホテルを開業して100人が滞在出来るようにする。らしい。
「あの噂はほんとなのかな。月面ホテルは年寄が長生きする為のものってのは。」
「ああメトセラ計画か。あれは民間の企画で月面基地の応用には挙げられるが、まあどうだろうね。重力が低ければ150才くらいまで可能かも知れないが、終生月で過ごすんだぞ。」
「自分で牢獄に入ってれば世話は無いな。」
実験場は砂漠の真ん中。月面の地形に似た場所といえば、そりゃあ砂漠だ。
ここでは月面のみならず、火星表面上での活動実験・研究も行なわれている。月は通過駅に過ぎず、あくまでも本命は火星だ。
月面基地も結局は、火星長期滞在の訓練センターとして進められた。
月で起こる事は必ず火星でも起きる。深刻なトラブルが発生しても、地球に近い場所であれば対処が容易く、本番の火星での事故に備えが出来る。
「おお、ちゃんと動いているじゃないか。」
月面仕様サルボモーターが既に歩いている。3機が稼動し、2機で高度な荒地走行訓練を行う。
色は白に赤線が随所に走り、なかなかかっこいい。「月面探検」と漢字で描いたのはツルニハの連中か。「ハラキリ」と書くバカは誰だ。
俺は剣崎に尋ねた。
「エミュレーターは十分に熟成してるじゃないか。」
「まあーキングさんが満足出来るレベルでは無いよ。レスポンスが悪くて。」
「エミュレーター噛ませてるんだから仕方ない。」
ツルニハ謹製運動姿勢制御プログラム「ツルニハAY」は、勿論エア駆動のアクチュエーターを前提に構築されている。
人工筋肉アクチュエーターを持つ月面仕様機では、直接使えない。
しかしAYシリーズの荒地での運用実績は磐石鉄板で、誰も安定性に疑念を持たない。
NASAの偉い人だって、これで動いているサルボモーターが欲しくてプロジェクトを始めたのだ。
そこで、中間にエミュレーターを噛ませる。人工筋肉にエア駆動アクチュエーターのフリをさせるわけだ。
「前に乗った時は酷いもんだった。横に曲がらないはずの脚が、ガニ股で歩いたんだぞ。」
「あれは申し訳ない、妙なテンションがどうしても取りきれずに。どうもピルマルの連中、制御信号に裏コマンドを相当隠しているんだ。」
「うーん、大丈夫なのかな。」
指令センターに行ってスタッフに挨拶する。虚名とはいえ「KING of サルボモーター」の名は色々と役に立ってくれる。
若い美人の研究員が俺の案内に付いてくれた。赤い髪の胸の大きなねーちゃんだ。
「今やってる連中が、月面でも走るんだな。」
「はい。ですが、向うで初心者を一から訓練する計画があります。低重力で七転八倒する姿というのは、研究対象としても興味深いですね。」
「悪趣味だな。」
月面仕様サルボモーター、見掛けはほとんど普通のと変らないが、一点だけ完全に違う部分が有る。
指だ。手の先にちゃんと指が付いている。しかも5本。人間と同じ配置だ。
「一応は作業が出来ます。地球上と違って向うでは怪力になるので、非力なサルボモーターでも十分使えるはずです。仕事はあまり有りませんが」
「あの部分は、ピルマル?」
「そうだ。我が社の製品だ。」
傲慢頑固って感じの初老のおっさんが、俺の前に立ち塞がる。研究員じゃないな、とぴんと感じる。この人は技術者、いや作業員上がりだ。
「おまえがローリング・キングか。人型ロボットの操縦では世界一だそうだな。」
「おかげで自己紹介の手間が省けています。」
「おう、儂はミハイル・パシミスコフ。ピルマルSIの月面機動歩行ビークル計画現場主任だ。」
なんとも時代遅れの鉄と火花が飛び散るおっさんだ。悪くない。
剣崎が俺の耳元でこっそり教えてくれる。
「このひとは、実はツルニハに居た事もあるんだ。」
「んだ、引き抜きか。」
「そうだ。最初期のサルボモーターの輸出は、全部儂が手掛けた。クレーム地獄の毎日だったぞ。」
同情する。綾子が搭乗して十分に運動研究の成果を出す前のサルボモーターは、まさしく木偶。歩くよりも、転倒してクレーンで吊上げるのに時間を浪費したと聞いている。
おっさんに尋ねる。
「あんたは、再設計にはどれだけ関わった。つまり人工筋肉のエキスパートかって意味だ。」
「ぜんぜん知らん。儂はアレを動かす為だけに雇われた。」
無責任な言葉に、剣崎に尋ねる。このおっさんは何しに来てるんだ。
「ピルマルの運動制御プログラムを用いると、凄くややこしい事が起きるんだよ。でもエミュレーター開発には統則制御理論を使わなければダメだ。」
「ぶっ壊れるのか。」
「ああ。だが人工筋肉関係には、俺達ツルニハは触れない契約になっている。」
もちろんこちらもピルマル側に手の内は明かさない。そこでこのおっさんが無理やりに人工筋肉を機体に押し込んでいるわけだ。
納得いった。
「動けば上等だ。」
「おう。斜めに傾いでも、動けばいいんだ。」
なかなか好感が持てるおっさんだ。綾子は多分知り合いだろう。彼女はこういう奴が大好きだ。
今日はこのおっさんの為に頑張ってやろう。
「で、俺を呼び出した理由ってのは、なんだ。見た限り、機体はちゃんと動いているじゃないか。」
「作業をしてもらいたい。手の指を使って、積み木遊びだな。」
「なんだ?」
話は簡単。偉い人の会議で、サルボモーターにも一応は作業能力の付加が決まる。やめとけばいいのに。
で、人工筋肉を用いた手指を装着した。これ自体は既に運用実績もあるまともなものだ。
まともでないのが、つまりは本体サルボモーターの方だな。
ベッドに固定してアームを伸ばしての作業は問題無い。限定的だが、直立静止状態でもツルニハのテストパイロットは可能にした。
そこから停滞している。運動状態での手指を用いた作業は誰がやっても出来なかった。
「綾子はどうした。そういうのは彼女が一番得意とするところだぞ。」
「綾子さんはだ、うん、試験機を動かした途端飛び降りて来た。「めちゃくちゃ気持ち悪い」って。」
「なんだそりゃ。」
どうりで本人が同行しないわけだ。
今日のスケジュールでは、綾子はテレビのインタビュー番組に出ている。話題はもちろん間近に迫った「サルボモーター月面投入」だ。
だが収録は今日で無くてもよかっただろう。おそらくこっちに来るのが嫌で、この日に押し込んだな。
「まあ、乗れば分かるか。」
「おう、死んでも今日はデータ残していってもらうぞ。」
つくづく思う。サルボモーターを作った連中ってのは、どうしようもない奴らだったんだな。
訓練3号機を使って俺の実験が始まった。
まず問題になるのが、コクピットだ。月面作業用重装備宇宙服を着用する。かなり嵩張る宇宙服を納めるコクピットは勿論新設計だ。
搭乗も一般サルボモーターとまるで違う。透明キャノピーは開閉するが、同時に機体上部前面がぱっくり開いてパイロットを受入れる。
「ふむ。」
宇宙服を着ているのに、手足の動きに不自由が無い。このあたりはツルニハの技術者が真剣に仕事してくれたのだと感謝する。
操縦グリップやペダルの感覚も、普通の機体と同じ。地球上に在る限りは特に問題無さそうだ。
「チェック終了オールグリーン。キングさん、起動するぞ。」
普通のと違って、始動シーケンスがかなりややこしい。
ツルニハが作るノーマルの機体は、コンピュータを2つ持っている。
1台は地形データ解析用、もう1台が機体制御に使われる。
スペック的にはどちらも同じオプチカルロジックの市販汎用品CPU。壊れた場合どちらででも機体制御が出来る。
月面仕様機は、さらにもう1台コンピュータを搭載した。機体制御プログラムはこのエミュレーターCPUを介して、人工筋肉を制御する。
一枚噛ませれば、それは当然レスポンスが悪い。
AYシリーズの運動姿勢制御プログラムは、そこんところを徹底的に詰めてあり、アクチュエーターを直接ぶっ叩いたかにびしっと反応する。
そこまでの反応は期待しないが、
「おおお!」
俺を見ていたスタッフや月面に行くミッションスペシャリストが歓声を上げるのが、外部音声で聞こえた。
「どうした?」
「すごい! 普通に立ち上がった。」
「おいおい。」
後で聞いたのだが、ツルニハのテストパイロットでもこの機体ではぐりぐりと全身の状態を確かめながら、ゆっくり立ち上がるしか出来ないらしい。
俺は、慣れている。乗り始めた頃のサルボモーターの反応に比べれば、この訓練機はよぽど筋がいい。
「レスポンスは、かなり改善しているな。この程度であれば通常の操縦に支障は無いはずだが、」
「歩いたり転んだりする分には、もう完成と言ってもいい。だが作業に関してはまったくダメなんだ。」
「なるほど。」
剣崎の言いたい事は良くわかる。そもそもがサルボモーターは作業を出来るように作っていない。
だからデータの蓄積が全く無い。AYシリーズも考慮していない。
器用に機体を使うパイロットは居るが、それはそいつの才能で機体性能ではない。木の棒でも色々出来るてのと変らなかった。
機体の調子を確かめる為に、ぐるんぐるんと腕を振り回す。転びそうなほど大きく前に上体を投げ出し、また反り返る。
大丈夫じゃないか。
「エミュレータの反応がどんどん良くなっている。リアルタイムで適応する機能を付けたのか?」
「知らない。ピルマル側で弄ってるから、そうかもしれない。だがテストパイロットはそんな風には報告しないぞ。」
「俺の動き、に合わせているのか…。」
作業実験の前に訓練用月面地形をちょっと走ってみる。訓練センターの責任者も許可を出す。なにしろ「セカイのキング」様の走りが見られるのだ。
丘から駆け降り、ごつごつと蟻塚みたいな岩が突き出る地形をするりと抜け、砂が溜まって滑り易い岩場、家の大きさの岩塊を飛び越え、そこら中でぐるんぐるん受け身を取る。
回転回転、逆回転。縦横斜めに自在に回る。
「キング。」
剣崎がこっそりとツルニハ専用秘匿回線で通話してくる。
「キングさん、ピルマルの連中慌てているぞ。いきなり最高の走りを見せつけられて、データ解析に大わらわだ。」
「この程度で驚いてもらっちゃ困る。」
「だが控えめにしてくれよ。あまり手の内を知られるのはマズいからな。」
障害物回避コース、ってのが有る。人工の障害がずらりと並んで対処法を覚える施設だ。
初心者用の単純なものの列だから、タイムアタックにちょうど良い。
「1分18!」
「冗談だろ。俺達は5分以上掛る。」
「キングだ、これがKINGだ。」
毎日訓練しているミッションスペシャリスト達が憧憬の眼差しでモニタ映像に食い入るのを、剣崎は自慢げに眺める。
ミハイルのおっさんは、と首を回して様子をうかがうと、岩のように厳しく立って居る。
剣崎は尋ねてみた。
「ミハイルさん。どうです、キングの走りは。」
「 大したもんだ。機体に無理が掛からず壊れないよう細心の注意を払っている。流石にプロだ。」
「お、…なるほど。」
最後に砂丘を時速60キロで突っ走って帰ると、皆バカのように口を開けて出迎えた。称讃の形容の仕方がわからないってとこだな。
一度機体から降りて検査に回す。多少無理は入れたから、どこかへたっているかもしれない。
赤毛で巨乳の案内のねーちゃんが、頬を赤くして俺の正面に立つ。なんだか目が潤んで変だぞ。
「ティムと呼んで下さい。ああ、もう濡れちゃう!」
タコのように絡みついて来る女を必死で引っ剥がして、おっさんの所に行く。3号機の左脚カバーを外して人工筋肉の点検をしていた。
「それが、統則制御筋ってやつか。」
「おう。ツルニハの連中にはあまり見せちゃいかんのだがな。」
月面仕様機はエアで保護カバーを膨らませないから、簡単に取り外しが効く。
中では冷たい青光のする真っ白な人工筋肉が蠢いていた。ひくひくと、生きてやがる。
「まるでイカだな。」
「刺し身で食ってみようとか思わんでもない。こいつら酷使されたはずなのに、喜んでやがる。」
「喜ぶ? まるで生き物みたいなことを言うんだな。」
「電気駆動の生物、と考えれば、分かりやすいんだ。宇宙人の身体の一部と言われても儂は驚かんぞ。」
おっさんはあまりこれに好意を持ってないようだ。
俺の少ない知識だと、統則制御理論というのは、同じタイプのユニットが連結してそれぞれが別の機能を自動的に分担して全体で合目的に働く、と覚えている。
人工筋肉の場合は、駆動部制御部センサー部電源関係を筋ユニットの一本ずつが持ち合わせ、それぞれが独立して演算する並列コンピュータとも看做せる。
「考える筋肉」だな。
「良ければ本題の、手指による作業ってのをやりたいんだがな。」
「15分待て。そのねーちゃんはまだ盛っているぞ。」
俺は再び赤い髪のタコに襲われた。
作業実験は、やることは簡単だ。
色とりどりの小さなブロックを持ち上げて、家を組み立てる。ただしブロック置き場から組み立て現場まで15メートル離れていた。
この間の移動も含めての作業だ。制限時間が課されると、なるほど確かに難題か。
ブロックは人間が両手で抱えるサイズ、1個10~15キログラム。サルボモーターの片手の腕力で持ち上げられる上限が100キロだから、問題無い重量だ。
「手指の強度・出力に問題はないか?」
「大丈夫、指1本でも180キログラムを引っ掛けられる。」
サルボモーターには直接マニピュレーターを制御する操作系は備わっていない。通常の腕の操作グリップの上に、手指用パネルが増設されている。
つまり、腕と手とは別々に動かさねばならない。
「要するに、オプション装備と同じ仕組みだ。」
ぐりっと機体を立ち上がらせ、ブロック置き場に行く。実験だから、周辺には大きなコンテナで曲がりくねった壁を作って、移動し難く設定してある。
「制限時間は無しか。」
「いや、他の奴にはできないから。」
「うん、そうか。」
コクピットの前に伸ばして、”手”を見る。よく出来ている。全体が人工筋肉で構成された灰色のゴムの手だ。中に骨は入っているが、感じさせない滑らかさで動く。
このマニピュレーター、現在の技術水準では考えられない設定になっている。カメラと連動していないのだ。
今の標準的なマニピュレーターは立体視が出来るカメラにより相対距離を測定し、対象の形状を把握して最善の接触をあらかじめシミュレーションで弾き出す。オペレーターはただぐいっと押し出せばいいだけだ。
対してこれは、オペレーターが距離や形状を自ら判断して、そっと接触させる仕組みになっている。実に理不尽だ。
こんな意地悪な機械を扱わせたら、それは誰も出来ないだろう。
積んでいるブロックの中から、一番手近な青を狙う。脚を緩めて姿勢を少し下げ、右腕を伸ばし、手指を接触させる。
「う!」
いきなり”手”が動いた。突然命を吹き込まれたかにブロックに躍り掛り、しがみ付き指の腹で形状を確かめるかに撫で回し、がっしりと掴む。
まるでここだけ動物を括りつけたような。そう、タコだ。手の形をしたタコが居る。
「こりゃあ、…綾子が逃げ出すわけだ。」
腕を上げて、ブロックを宙に持ち上げる。”手”は暴れた。まるで”腕”に逆らうかに、びくんびくんと跳ね回る。なんだ、これは。
「シュンイチ、どういう理屈になっている?!」
「キングさん、惑わされるな。ブロックの状態は安定している。」
言われてよく見ると、確かにブロックはスムースに上がって来る。”手”が微妙に跳ね回るのは、機体の振動がブロックに伝わって不規則な揺れを起こすのを修正するからだ。
「とんでもない代物だな、統則制御筋ってのは。」
俺は見た。”手”が一瞬ブロックを離し、宙に浮いた状態で握り直すのを。人間がやるのと同じ、いやそれ以上に巧みに指を操る。
こんなモノが末端に付いた機体では、そりゃあ並のパイロットは耐えられない。
サルボモーターの操縦は無駄と無理の集合だ。スムーズ滑らか連続線上てものがどこにも無い。でたらめの連動を、長大なバネの寛容さに呑み込ませてどうにか動く。
「いいかげん」こそが生命だ。
だが”手”は許容しない。おそらくはブロックに掛る加速を測定して、なめらかに無理なく進むよう常に修正を加えている。
「大丈夫か、キングさん。」
全然大丈夫ではない。パイロットの意図に逆らうマニピュレーターで何をしろと言うのだ。それとも、”手”の操作に専念しろと要求するのか。
「おかしい。」
これはまったくおかしい。機械として常軌を逸している。
本来まっとうな技術者であれば、手指だけが独立して動く風には作らない。統則制御筋が勝手に動くものであれば、腕や肩で反動を吸収させるべき…。
「おい、おっさんを出してくれ。」
「! ミハイルさんか。」
特別にツルニハの秘匿回線で喋ってもらう。企業の契約を越える、これはサルボモーターを扱う者としての信頼だ。
「一つ聞きたい。ピルマルの設計とは異なる改造を、こいつに施したろう。」
「おう、やはり分かるか。」
「腕を動かす人工筋肉と、この”手”はデータのやりとりをしてないな。スタンドアロンで”手”は動いている。」
「何故そんな事をする必要がある?」
「決まってる。サルボモーターの制御に人工筋肉を集中させる為だ。外部環境情報から人工筋肉を切り離したな。」
統則制御筋は、「考える筋肉」だ。一本一本の筋ユニットに付いているコンピュータとセンサーが、隣接する環境を測定し何を為すべきかを定めて、自発的に機能を変える。
だがサルボモーター本体を動かす筋肉は、機体に封じ込められ内部のみに関心を向けている。より良く機体を制御する、エミュレーターの性能を向上させる仕事だけをやっている。
対して、手指の人工筋肉は直接に外部に接触する。環境情報を自ら取り込む。
これを本体に接続すれば、機体はパイロットの意図を超えて独自に動いてしまうだろう。少なくとも、サルボモーターの動きにはならない。
それを知ったおっさんは、すっぱり”手”を切り離した。
おっさんは胸を張って言う。
「儂が請け負ったのは、まともに動く月面用サルボモーターだ。統則制御筋の変態ロボットじゃない。」
「むう。」
”手”は、独自の判断でブロックを安定して保持する作業に専念する。パイロットは、自らの操縦に抗する敵対的生物をねじ伏せねばならない。
さてどの手でじゃじゃ馬馴らしをするか。
管制室で俺の操縦を見守っていた連中が、一斉に声を上げる。
「おお!」
「何故?」
「あんなにあっさりと、キングの操縦なら大丈夫なの?」
突然機体がきびきびと動き始め、”手”も従順に操作に従う。離れた場所にブロックを積み、取って返して最短最小の手間と時間で持って来る。
ブロックを両手で1個ずつ持つのに、また人は驚いた。左右同時に”手”が暴れても、キングは制御出来る!
剣崎は必死で機体データを調べ、声を洩らす。
「”倒立振子”か。」
手の上に立てた棒を倒れないように制御する。二足歩行ロボット基本中の基本の原理だ。直立した細長い身体を転倒させずに保ち続ける、まさに技術の核心だ。
ミハイルのおっさんも、満足げにうなずく。
「”膝”だ。」
サルボモーターには”膝”は無い。長大な板バネが脚の中身だし、それが後ろに湾曲する。人間の膝に当たる部品は存在しない。
だが、乗っているのは人間だ。膝の感覚を持つヒトが、操縦する。
仮想的に存在させた”膝”を使って、暴れる”手”の動きに対応する。小刻みに”膝”を前後させ、”手”のリアクションで揺れる上体を落ち着かせた。
自分が制御されていると認識した”手”は、やがて俺の意志を読み取る。機体全体が何をすべきか、「手」が如何に振る舞うべきかを把握した。
「キングはサルボモーターに”膝”を持っていたんだな。他のサルボ乗りと違うはずだ。」
「そりゃあ追いつけないさ。機体制御の細かさが違う。」
「ああ、キングさま素敵!」
12個のブロックを積み上げて、家を作る。完成だ。
俺は、ふうと小さく息を吐いた。
「便利な指だな。」
「無理だよ、おまえの真似は。少なくとも今回のミッションには使わない。」
「そうか。」
おっさんは素直に陰謀を認める。最初からそのつもりだったのだ。
サルボモーターは万無能、なんの役にも立たない機械。だからこそ人に求められる。月面でもやはり、無能だから遊びに使おうと考える。
”手”なんか、要らないのだ。
「最高レベルのサルボ乗りならばマニピュレーターを使えると実証出来た。だが誰にでも出来る支援ソフトの開発には、時間的余裕が無い。打ち上げには間に合わない。そういうシナリオにしておいた。」
「妥当な判断だと思うよ。」
ミハイルのおっさんに誘われて、俺は単独で格納庫にやって来た。ツルニハの技術者もNASAの人間も抜きで、統則制御筋の真の姿を見せるという。
「人間が乗るにはまだ早い。熟成が出来ていないのだが、おまえならなんとか乗りこなせるだろう。」
「おい、まるで化物みたいだな。」
「ああ化物だ。こんなものを作っちゃいけないと、儂は考える。」
昼間使った3号機は、俺の操縦の後に徹底的な検査と解析が行なわれている。統則制御筋が如何なる学習をしたか、皆血眼になって調べている。
代りに2号機を起動する。昼間と同じくエミュレーターを立ち上げて、直立する。普通のサルボモーターと同様ふらふらと小さく揺れて、まともには立たない。
「よしキング、エミュレーターのCPUにピルマルSI製の運動制御プログラムをロードしろ。”TUKE
09-25JU41”、パスワードは”TURAKURAFU”だ。」
「了解。」
エミュレーターが稼働中のコンピュータに、指定のプログラムを走らせる。モニタにずるずると数百行テキストが流れて、ビジュアルナビゲーターが起動する。
真っ赤な画面にくろぐろと蛸唐草紋が描かれた。目に悪い。禍々しい、魔法的な圧迫感が襲い、モニタを直視出来ない。
ぶるん、と機体が震えた。人工筋肉のテンションが下がり、ずるりと機体が降下する。50センチほど下がったかと思うと、また元の高さに戻る。
「?、脈動か。」
腕脚の人工筋肉が独自の活動を始めた。どくんどくんと脈打ち、両腕がぶるんと震える。
サルボモーターの腕はこのように生物的には動かない。何もしていない時はただの風船手足、ゴム人形の静かさを持つ。
だが2号機は今、あきらかに生存への意志を発している。
「キング! 大丈夫か。」
「コクピットに異常は無い。動いていいか?」
いや異常は有る。サルボモーター特有の揺れが感じられない。脈動はあるが、ふらふらと揺れるのを止めた。機体が静止直立を実現している。
右手を上げる。前に突き出して。
「キング!、いきなり動くな。」
「いや、手を上げたら脚も付いて出た。自動で姿勢の安定を取ったな。」
「お、おう。そうか。キング、注意してくれ。コンピュータに機体制御を乗っ取られるな。」
「分かった。」
右手右足が前に出たから、左足を前に出す。歩むのだが、
「…左足が右を前に押し出し、重心が乗ったら、左が前に飛び出る…。摺り足をしたな?」
機体は足裏を地面に摺りながら慎重かつ大胆に動いていく。タコが触手で地形を探るかに、確実に地面の情報を読み取る。
「これが”考える筋肉”か。」
ずっずっと摺り足で進む。速度は遅いが足運びは的確で無駄が無い。だが上体は切り離されて別の生き物の感じだ。
腕を回してみる。
びしびしと的確に、俺が思い描く場所に指先が向かう。こんな素直なサルボモーターは初めてだ。
「ああ、腕の筋肉と、脚の筋肉は分離しているんだな。」
試しに、向きを換えてコンテナの角に足をぶつけさせてみる。
つま先が接触するかの瞬間、足の前後を入れ換えた。
壁に触った足を急速に引き戻し、姿勢が崩れない為に後ろ足を前に進めてバランスを取る。足裏に車輪でも付いている滑らかさだ。
腕も瞬時に開き、姿勢の安定を保つ。まるで格闘家が敵に構える姿になった。
「人間の出る幕じゃないな。これで全身の筋肉が統合されていれば、どんな機動が出来るのか、」
どくん、と心臓が一拍し、俺ははっと顔を上げた。
見られている。誰かに俺は覗かれている。
もちろんコクピット内のカメラで、ミハイルのおっさんは俺をモニタする。
だがそうじゃない。俺の全身、手足の操作を絡み付く視線で、嘗め回す触覚で、監視する奴が居る!
「機体が、いや、人工筋肉が俺の次の動作を探っている…。俺を、見ている。」
奴にとっては俺も外部環境の一つに違いない。地面の凹凸を探るのと同じく、俺の操作も見極める必要を覚えたのだ。
急に強い圧迫と緊張が押し寄せる。機体を操作するグリップとペダルからタコの触手が伸びる気配がして、息苦しく。
綾子が逃げ出した理由がよく分かる。
「OK! ミハイル、ここまでだ。降参する。」
「 、そうか。」
コクピットから這い出して逃げた俺に、おっさんはわずかに残念そうな顔をする。
一応はピルマルに雇われている身だ。得体の知れない機械でも、まともに使える人間が出て来る事を祈っているのだろう。
済まない。それは、俺じゃない。
2042年春、サルボモーターは月に向かう。
俺達「チームツルニハ」もゲストとして発射場に呼び寄せられた。全世界の注目度は高く、何社もインタビューを受ける。
まあなんだ、最初からみんな分かっていたのだ。月面で遊ぶには鋼鉄の身体が必要だ。人間生身ではろくなこと出来ないと。
地上基地から強烈なレーザー光を照射され、ロケットは推進剤の蒸気をもくもくと吐いて飛んでいく。びりびりと空気が噴射音に震える。
「ところでキングさん?」
生放送のインタビューを終えて、綾子が俺を振り返る。
怒った日本女性ってのはおっかない。能面の表情に長い艶のある黒髪がばさっと掛り、般若てのはまさにこれかと理解する。
「キングさん、そちらの赤毛の、そう貴方の左腕にタコみたいにしがみ付くその方を、ご紹介していただけませんこと?」
第七歩 追憶のサルボモーター
「…以上のデータからして、月面仕様サルボモーターを作業に用いることは現実的な課題であると証明されました。
ローリング・キング氏の卓越した技術に範を求め適切なハードウェアの追加、ソフトウエア的熟成を高めれば、必ずや作業用サルボモーターの開発は成功すると確信します。」
論より証拠。実際にサルボモーターが作業を行う映像を、ツルニハ経営陣は感慨を持って見つめていた。
万無能が売りのスポーツ用搭乗人型ロボット、サルボモーター。
だが卑しくも乗用機械を作り続けてきた彼らは、実用への模索を片時たりとも忘れていない。
ピルマル理科工業(SI)が次世代汎用作業人型ロボットの共同開発を持ちかけて、平静で居られるはずが無かった。
俺は、間違いをしでかしたのかもしれない。
サルボモーターは今のままでまったく問題は無かった。実用を目的に進化の道を違えると、やがて破綻が待っている。どうしてもそう感じてしまう。
懸念を綾子に告げると、笑って俺の背中をばしんと叩いた。
「鶴仁波の家はね、破滅の縁をぐるぐる回り続けても絶対に落っこちないの。ダイジョーブ任せてよ。」
だが何故今になって大型の人型ロボットがクローズアップされ、実用を求められるのか。
結構ややこしい理由が有るが、ざっと述べれば、金だ。
月面でも活躍した、高度な作業が可能な人間大の人型ロボットは目の玉が飛び出るほど高い。
こんな高価なものを戦場になんか投入出来ない。人間の兵隊を殺されるより、こいつを壊された方がダメージが大きかった。
しかも大量に必要だ。人間と同じ作業ができるとしても、倍10倍早くなるわけではない。数は要る。
また遠隔操作にはオペレータの人員が機数分必要になる。AIによる自律的な作業は現在も研究中で、実用の目処も立っていない。
要するにまだダメなんだな。
それでも兵器や輸送機械の無人化は進む。トラブルが起きた際にはどうしても人手が要るが、極力省きたい。
そこで、巨大で廉価な汎用作業機を投入する。力業で誤魔化してしまおうという発想だ。
応急措置が出来る程度の能力で良い。だがどんな地形でも確実に動き、支援機材無しでやってのける。そんな機械が欲しくなった。
不器用な作業機の為に兵器や輸送機械の方を設計変更して、大雑把なユニットの組み合わせで機体を構成する。
玩具の積み木を重ねたような戦車やトラックが生まれた。ユニット交換や破棄が戦場で簡単に出来る。
積み木遊びに最適な形と来れば、人型巨大ロボットと考えた。
4足歩行機も試行されたが、複数機体が連動して作業するとなれば、2足歩行機の方が適しているし、安くつく。
ヨーロッパの総合兵器メーカーIRSPが製作した「ヴァン・ダム」もそんな風に用いられる。作業だけならアレでいいのだ。
明確な用途が設定されたから、他の兵器メーカーも食指を伸ばす。
で、彼らの目の前には30年前から元気に動いている、万無能ながらもどこでも走るサルボモーターが有る、わけだ。
「全人工筋肉?」
「月面仕様機開発の経験を生かして、サルボモーターを一から再構築してみます。2040年代にふさわしい技術を投入して。」
「当然の事ながら、スポーツ用途はまったく考えない?」
「うーんどうでしょう。汎用作業機ですからスポーツに使えなくもないでしょうが、価格を考えると個人の所有はおそらくは無いと。」
「そうね…。」
ピルマルSIとの技術ミーティングから、綾子は早々に追い出されてしまった。というよりも、ついて行けずに逃げ出した。
ピルマル側の開発責任者は、ユウ・コウベン・スクって狐目の男だ。頭は切れるのだろうが、技術者というよりも政治家な感じがする。
ツルニハ側は名目上は色々偉いさんが居るが、剣先俊一ら若手技術者が中心となって携わる。サルボモーター黎明期を知る者は居ない。
ミーティング後は、顔合わせに軽くパーティを開いた。綾子の得意はむしろこちら、新型機が完成したらセールスに飛び回る事となろう。
「向うでは”サルボロイド”って名前をもう用意していたよ。より人間に近いサルボモーターってことだね。」
「出来上がったら”ピルマロイド”に置き換わっているさ。」
「ハハ、確かにそうなりかねないな。」
剣先ら技術陣の顔は明るい。サルボモーターを越えて真に意味の有る機械を最先端技術を駆使して作り上げるのだ。熱が入る。
ただ、ツルニハにとってそれは本当に良いことなのか。
「ローリング・キングさんですね。このプロジェクトはまさに貴方の卓越した操縦技術が道を拓いたのです。今後とも御力をお貸し下さい。」
ユウ・コウベン・スクは俺に握手を求めて来た。声が高く、人種も性別も年齢も分かりづらい妙な奴だ。人間じゃないかもしれない。
俺は温厚で礼儀正しい男で通っている。勘でイヤだとは思っても、手を拒んだりしない。
「ローリングです。新しい歩行機械が出来るのであれば、一介のサルボ乗りとして協力は惜しみません。ですが、一つ聞きたい。」
「はい、なんでしょうか。技術に関してなら、私よりも詳しい者に任せますが、」
「ピルマル理科工業では、サルボモーターをどのように考えている? 何の役にも立たないのが売りのロボットは、実は要らないのではないか。」
「ああ。」
吊り目が笑った。本当に笑ったのかもしれないが、意図が読み取れない。嘲笑であるのかもしれない。
「実用という意味では確かにサルボモーターに価値はありません。でも可能性を示してくれた先駆者としての評価は高いですね。人間が作った物があれほど自由に動く例は、曲芸飛行機以外無いでしょう。」
「うん。それがピルマルの技術力で実用の価値を身に付けるってわけだ。」
「さてどうでしょう。サルボモーターと我々が作り上げるサルボロイドとでは、おそらくまったく別の機械になると思いますよ。」
「ほお。」
ツルニハの連中、特に経営陣はそうは考えないと俺は知っている。サルボモーターが社会の役に立つ機械になるステップとして、このプロジェクトを推進する。
俺は、愛すべき間抜けな経営陣に代わって問うてみなければならない。綾子の為にも。
「サルボロイドが軍事に使われるのは知っている。だが武装して戦ったりは無いよな。」
「はははそれはありえません。もっと便利な機械が幾らでもあります。ただ救助用として空挺で戦場に投入される可能性は小さくありません。それは平時の民間でも役に立つ事です。」
「ハイスペック化して月や火星にも投入される。とうぜんだな。」
「宇宙での利用はまさにサルボロイドの独壇場となるでしょう。」
「その時、サルボモーターはどんな位置付けだろうか。」
吊り目がこちらを見た。やっと俺を見た実感が沸く。奴は少し考えて、言った。
「サルボモーターを私が評価していない、とお考えではありませんか? 確かに役に立つ機械ではありませんが、反面これほど人を惹き付けるものもありません。キングさんが一番よく御存知でしょう。」
「まあな。」
「月面仕様サルボモーターに着手する前、我々はあらかじめ機体を分解して細部を検証しました。どこを改良すればよいか、より良い運動の為になにを付加すればよいか。
だが試みは無駄だと知りました。サルボモーターは完成している。人工筋肉を使わなくとも立派に動き、置換すべき機構は無いとの結論に達しました。」
「うん。」
「言うなれば、日本刀と一緒です。人を殺す武器であればもっと効率の良いものが幾らでもある。銃やミサイル、レーザー等いくらでも挙げられます。
だが日本刀に代わるべきものは他に無い。改良を加えようにも、あの形以外の選択肢を見出せない。そして美しく、人を惹き付ける。」
「いや、悪かった。あんたがそれほどサルボモーターを理解してくれているとは知らなかった。許してくれ。」
「いえ誤解があればそれを解くのも私の仕事です。ピルマルSIは決してサルボモーターのコミュニティを損なおうとはしていないのです。どうかご理解ください。」
ユウ・コウベン・スクは丁寧に礼をして去っていく。俺は後ろで心配そうに見守っていた綾子とベンの傍に戻る。
綾子は、かなり険悪な目付きで責めるように言う。
「なに話してたのよ。」
「サルボモーターはかなりのピンチ、ってことだ。もうちょっとバカか、無理解な奴ならやり易い。だがあいつはサルボモーターの価値を知ってるぞ。」
「あいつ、スポーツ界にも手を出す気?!」
血相を変えるのは仕方ないが、そう簡単な話じゃない。
「乗っ取りでもたくらんでるか?」
ベンジャミンの問いに、俺はちと悩む。直感が混ざっていて確かではないが、ベンと綾子になら話しておくべきだろう。
「俺が月面仕様機にピルマル製の運動制御プログラムで乗った話はしたな。」
「え、ええ。自分で判断し進化する「考える筋肉」ね。」
「物凄く気持ち悪かったアレだろ。」
「ユウ・コウベン・スクはアレに相当な自信があると見た。サルボロイドをサルボモーターからかけ離れたものにする。最終的に行着く先は、」
「おお、何になる。」
「サイボーグ。機械の巨大な人体。操縦技術を持たなくても、自分の身体を動かすように機体が動く。そんなのが出来るはずだ。」
綾子はへんな顔をした。なにか悪いもの食べたんじゃない、て眼で俺を見る。
ベンも硬い石を呑み込んだ顔だ。だがさすがに男だから、なんとか俺の懸念を分かってくれる。
「つまり、誇大妄想狂の受け皿として使える機械だな。」
「サルボモーターのユーザーに少なからず居る連中だな。自分が偉大で並ぶ者が無いと信じる、そういう欲求がサルボモーターで満たされる。他に適当なものがあれば、おそらくは。」
「あー、もうちょっと分かりやすく説明してよ。」
男だけで納得するから、綾子が嫉いた。そうは言っても、…!
「そうだ、お前の爺さんだよ。鶴仁波膳九郎氏。あの人の夢をピルマルに取られてしまう、そういうことだ。」
1996年、世界は或る映像で目を覚ました。
二足歩行する人型ロボット。夢のまた夢と思われていたものが、ちゃんと実機として歩いている。
俺が生まれる10年も前の話だ。
当時少しでも技術に関心が有る者にとって、それは革命にも福音にも思えたらしい。同時に強烈な嫉妬と功名心にも火を点けた。
「俺達も、ロボットをやってみよう。」
鶴仁波膳九郎氏もその一人だ。同じ日本の、同業の自動車会社が成し遂げたのだ。我が社だとて、と考えて不思議はない。
膳九郎氏以外の社員はそうは考えなかった。
あちらとツルニハ工業とでは技術が違う、違い過ぎる。いやまさに月とスッポンてんとう虫、同じ○でもスケール何万倍。臍で茶が沸く大笑い。
だがツルニハは当時日本でも珍しくなっていた同族経営の会社だ。一族の総帥として膳九郎氏は絶大な権力を持つ。
当時52才の彼はこう言った。
「あちらがアトムなら、こっちは鉄人だ! いや今風に言えばゲリオンだ!!」
いい歳をして彼はアニメファンだった。それもロボットアニメのマニアだ。給料払ってるのは彼だから誰も逆らえない。
これはダメだと、鶴仁波の一族に諌めてもらおうとする。後妻の清子さんはものの分かった御仁だから、会社を滅ぼしかねない愚行を止めてくれるはず。
だが彼女は言った。
「まあ素敵。私も乗りたいわ。」
頼みの綱をぶち切られたツルニハの社員には、だがまだ救いは有る。
物理的に出来る訳ないじゃないか。なんたってウチは弱小自動車・農業機械メーカーで、ロボット技術のかけらすら有りはしない。
運の悪いことに、天才が居た。ツルニハ工業が自信を持って送り出した小型乗用車の新モデル「SARVO Ⅱ」の開発主任、桧垣 天才(たかとし)だ。
名に「天才」を持つだけあって、彼の才能は奥が知れない。掃きだめに鶴、なんでツルニハなんかに居るのか誰も知らない。
ただ彼は在るべくしてここに居た。膳九郎氏の求めに応じる唯一の人物だった。
「SARVO Ⅱ」は無茶な自動車だ。炭素繊維で補強したFRPモノコックフレームという、先進的なのか先祖返りしたのか分からない構造になっている。
なんとなれば、これは性能の追求ではなく生産性の向上、いやいや、どれだけ安っぽく高性能車を作るかの挑戦だった。
なにせ範としたのが、当時ソビエト崩壊直後の東欧の自動車だ。絶対感性狂ってる。
走りは結構良いが、しょせんエンジンOEM供給。ツルニハ工業には元々エンジン技術は無い。
故に車体の独自性特異性で顧客に訴え掛けねばならない。先進性は有る。
車内3箇所から電源12Vを取れ、ついでに車外にもコンセントが付いている。自動車への電子機器搭載にいちはやく注目していた。
見掛けは変だが、当時要求されたセールスポイントをちゃんと押えた乗用車だった。
安全性に関しても独自のアプローチで規制をクリアする。
「コクーン構想」と言って、乗員を護るキャビン部がボールのようにぽにょんと跳ねる。炭素繊維の篭が乗員を保護し、FRPがばっきり折れて衝突のエネルギーを消費する仕組みだ。
人をはねた時に、被害者を柔らかく包み込む機構も採用した。
コクーン構想には当時のツルニハ工業はかなりの自信を示し、パンフレットにはこんなイラストも描いてある。
『コクーンに車輪の代りに手足を付ければ、たちまちアニマルロボットとして歩き出す。』
桧垣が搭乗人型ロボットの開発に着手して、最初に考えたのも乗員の保護だ。
人型ロボットは宿命的に転ぶ。歩くからには、転んだ時に乗員を護る対策を講じねばならない。しかし、保護機構を設ければ動きを制限するし重量も増加する。
コクーンでも無理だ。積極的に転倒の衝撃を受け流す策を、一次構造の段階から施していなければならない。
直感が走る。手なんか要らない。
他のメーカーがロボットに期待するのは、手を使っての作業だ。人型ロボットだから当たり前。
我がツルニハが同じ道を歩んでも決して勝てない。手ではなく、足に勝機が有る。
彼は手を持たないロボットを設計する。徹底的に歩きを追求する機械を求めた。
そして到達達観する。竹馬でいいじゃないか。機械化竹馬は誰も乗った事が無いだろう。
設計図を見せられ、さすがに膳九郎氏も唸った。彼が求めるロボットの姿からかけ離れていた為だ。桧垣に尋ねる。
「これは、転んだら乗員が危ないだろう。」
「受け身を取ればいいんですよ。相撲の土俵が何故あんなに高いか知ってますか? 高ければ落下まで時間が稼げて、受け身を取り易くなるんです。」
そんな事できるか、と膳九郎氏は怒る。自動的に機械が受け身しろ。
言う方も無茶だが、実現する方はもっと無茶だ。機械化竹馬は受け身専用バンパーを備え、転倒時ぐるんと回る機能を備える。
そして気付く。脚も曲がった方が、受け身し易いんじゃないか。
手も足もバネの構造を持つロボット。サルボモーター誕生の瞬間だ。
それから10年。2011年になってようやく実機が完成する。
全高4メートル、1人用の着装するロボット。夢があった。
装甲を備え強大な力を持つ戦闘用パワードスーツの第一号、とマスコミは書き立てる。あらゆる環境で走行が可能な高機動ロボット。
だが目の前に現われたのは、クレーンで頭上から吊るされ生まれたばかりの仔馬のようにぶるぶると震え続ける風船手足のロボットだった。
しかも転ける。2度も3度も、何度やっても数歩歩いただけで転ぶ。
さすが2011年ともなれば、二足歩行ロボットに対する世間の目も肥えている。一応は世界最大の動的歩行ロボットとはいえ、ここまで情けないと笑うしかない。
ツルニハ工業とサルボモーターは嘲笑の渦に投げ込まれ、インターネットでは酷評の嵐、無様な映像を加工され世界中に恥を垂れ流す。
が、膳九郎氏は満足だった。サルボモーターはともかく歩くのだ。3歩歩けるのなら、4歩も可能なはず。4歩歩ければもっと長く。
桧垣も手応えを掴んでいた。4メートル型は小さ過ぎる。5メートル型ならば転倒までの時間が稼げ、更なる一歩に繋げられる。
直ちに5メートル型の設計開発が開始され、1年も待たずに再度記者発表にこぎつける。
今度は10歩歩いた。しかも早い。だが取材陣が驚いたのは、転倒だ。
時速20キロは出ていただろう。このスピードで転んだ機体が手を地面に着いて、ぐるんと回る。
完全には立てなかったが、回転の力を利用して姿勢を復元する姿に、開発者が何を目論んでいたかようやく理解する。
最後には坂道の上から突き落とし、見事再直立を実現する。
だがそれは、サルボモーターが手でモノを持てない事も証していた。地面との激突を防ぎ受け身をし、走行時バランスを取る為だけに存在する腕。
作業が出来ないロボットに価値は無い。
それから数年。思い出したようにツルニハ工業はサルボモーターの試験映像をマスコミとインターネットに発表した。
たまに物好きな金持ちが機体を購入したいと申し込む。実用には程遠いにも関わらず、膳九郎氏はOKする。
安請け合いの納入はクレームの嵐となって担当者の胃を何度も破壊した。
「膳爺ちゃんの夢かあ。うーん、私には分かんないなあ。」
「そりゃ分からんだろう、お前には。」
綾子がサルボモーターに乗ったのは6才の年。小学校に上がったお祝いに乗せてもらった。
当時漸くサルボモーターは自動車試験コースの1周に成功する。最高速度は時速30キロ、平均12キロと人間でも追いつく速度でちんたら走っている。
それまでの苦労がいかばかりか、涙ながらに語るテストパイロットの愚痴に付き合うほど、綾子は出来た子供ではない。
爺ちゃんが約束してくれたおっきなロボットに乗れるのが嬉しくて、ゲロを吐くほどワクワクした。
クレーンで吊るしたままの機体に、専用にあつらえてもらったピンクのパイロットスーツに身を包み、小学1年生が搭乗する。もちろん史上最年少。
彼女に愚痴ったパイロットは、その晩へべれけに潰れるまで酒を飲み、警察のトラ箱に保護された。
6才児が初めて乗ったその日にコース1周を成し遂げたのだ。そりゃあ飲まずにいられない。
次の日も綾子はロボットに乗り、昨日より早く1周した。新記録だ。3日目、最初のクラッシュをする。フェンスに激突して風船腕がもげる。
子供になにをさせるのじゃあ、と膳九郎氏は娘に殴られた。歳取ってから出来て一番可愛がった末の娘だから、これは堪える。
綾子は以後サルボモーターに乗せてもらえない。
1週間後、開発責任者の桧垣が訪れる。
お嬢様をわたくし共にお預け下さい。この子には才能があります。ツルニハ工業全体の夢を実現し、必ず世界に羽ばたいてみせます。
娘は清子さんに相談する。見識に優れた母ならば、父の愚行に孫を巻き込むのを許さないだろう。
清子さんは言った。
「綾ちゃん、よかったねえ。ロボットに乗れて。おばあちゃんも乗りたいわあ。」
こうしてサルボモーター開発は遂に人を得て、離陸する。2年後、最初の実用的な運動姿勢制御プログラム「ツルニハAY 1.0」が発表される。
ちゃんと動くロボットが、膳九郎氏20年の夢が実現した。
更に1年。綾子は6メートル型になった機体を操り、テストパイロットが操縦する機体を蹴倒して、世界に鮮烈なデビューを果たす。
綾子が俺の夢になった瞬間でもある。
この年サルボモーターは爆発的に売れた。100台に満たなかった機体数が3倍に脹れ上がる。少ない機体に何人もが群がって、映像で見たあの技を再現しようと必死に齧り付く。
いい気になった爺さんは、自動車(すでに廃業寸前)・農業機械(ぼちぼち儲かっていた)製造部門を売り払って、サルボモーター専業にツルニハ工業を転身させる。
ありとあらゆる妨害と説得を振り切って、やっちまった。7度ほど潰れ掛り、その度不死鳥の如くに甦る。
「つまり膳九郎の爺さんの夢は、巨大なロボットを作ることじゃなく、自分が巨大ロボットになるんだったんだよ。」
「え~、そんな人居るのお?信じられないー。」
「なんで分からないかな、サルボクィーンが。」
「私は生まれてこの方、サルボモーターが私のものとして自由に動き回るのが楽しいから、乗ってるのよ。ロボットに成るなんて、ねえ。」
可哀想な人を見る目で俺を見るな。
しかし俺はどうなんだろう。どちらかと言うと、綾子に近いタイプではないだろうか。逆にベンは、
「ベンはどうなの。あなたロボットに成りたい?」
「俺は、ーそうだな。」
ベーグル牛蒡サンド、などというパーティに似合わない妙な食い物を齧りながら、世界最強サルボ乗りの黒人は答える。
「俺は漫画に出て来る悪役をブチノメスには、ロボットに乗らなきゃダメだと思ったぞ。超能力は無理だろうから、やっぱロボだよ。」
「げーガキじゃない。」
「だから、男ってのはそういうもんなんだったら。」
「じゃああの、ユウさんもそうなの?」
ユウ・コウベン・スクが何を求めてサルボロイドを開発するのか。それは俺にも分からない。
サルボロイドの開発は、当然俺達にはまったく関係無いところで進む。ほとんど忘れても差支えなかった。
半年ほど経った時に、一度剣崎に会って話してみた。奴はげっそり痩せている。
「やはり難航しているのか。」
「いや、実はもう出来てるんだ。統則制御筋にも通常モードってのがあって、他社製品の人工筋肉と同じにただ縮むようにも出来る。これならまあ動くよ。」
「自分で考える筋肉、ってのはやっぱダメだろ。乗ったから分かるぞ。」
「ああ分かってる。分かっちゃいるが、やりたいんだ。」
剣崎は胃を抑える。こりゃ相当重傷だ。
「めちゃくちゃ面白いんだ。統則筋は面白過ぎる。一日だって現場から離れられないよ。」
「ポテンシャルが物凄く高い事は認めるさ。ただ人間の手に負えないものなら仕方ないだろ。」
「面白いんだ。」
悪魔の誘惑に嵌まったて感じだ。俺達パイロットは逃げ出したが、研究開発者は自らアレに突っ込んでいかなきゃならない。深入りすると、こういう風に魅入られるんだな。
「統則制御筋ってのは、元々はナメクジの運動を再現する為に作られたものだよ。もちろん本物のナメクジはあんなに頭良くないが、それが沢山集まって社会を形成して、って考えていく。」
「うん。」
「だがもともとがナメクジなんだ。複雑な可動構造物を制御する為のものじゃない。現にピルマルの応用でも、タコの触手付き戦車くらいだ。」
「あ、統則戦車って奴だろう。いま太平洋諸島戦争で大活躍してるって。」
「アレに使われているのは、ただの筋肉の棒だ。紐だ。タコ足だからね。でもそれがどれほど器用に便利に働くか。あっちの資料を見せられて度肝を抜かれたよ。」
「ただの人工筋肉としてでは、ダメなのか?」
「はは、それならエア駆動使うよ。月面仕様機のエミュレータさ、アレを統則理論抜きで構築すると酷いもんだよ。2010年代のツルニハの苦労を繰り返す。」
「じゃあどうするんだよ。」
「頑張るさ。最終的には月面仕様機に毛が生えた程度で終るかもしれないけど、製品としてならそれで上等か。ミハエルさんは偉いよ。一発で見抜いて、”手”を切り離して。」
別の時に、綾子も独自にツルニハ本社の動向を聞いて来た。開発期間が短い割にはハードウェアはさっくりできたが、ソフトウェア的に大難航して困っているそうだ。
「大丈夫なのかしらね。ピルマルSIのホームページ見たら、もう商談受け付けてるのよ。」
「戦争中だから、需要はしっかり有るわけだ。あっちの経営陣も急いでいるな。」
「でもね、人が乗る機械に致命的な欠陥は許されないわ。運動制御が出来ないようじゃ、やっぱり無理よ。」
「いや、基本遠隔操作だろ、アレは。」
「サルボモーターが遠隔でどれだけ動くってのよ。」
折角日本に戻ったのだから、ツルニハの教習所に寄ってみる。
月面でのサルボモーター運用は期待通りの成果を見せ、誰もが月から配信される映像を待ち望む。
1/6の低重力下でぽよんぽよんと跳ね回る機体は、人類が望む宇宙進出の姿をそのまま戯画的に実現した。こんな真似しなくて良いのだよ、という理性を越えて訴え掛ける力がある。
おかげで新規に機体を購入し、教習所に通う者も増えているわけだ。
ぶざまに転ぶ訓練機を見ながら、綾子は言う。
「サルボモーターって、もっと簡単に操縦出来る方がいいのかしらね。」
「簡単に動かないから、面白いんだろ。」
「私やあなたはそれでいいけど、世間一般の人は違うでしょ。誰でもが気軽に乗れる機械ってのが、ほんとうの。」
「普通の人間は、人型ロボットなんか必要としないさ。」
「そうね。それが普通よね。」
アスファルトの上で訓練機が動かなくなった。サポート車がぐるーっと回って救援に駆けつける。おそらく、中でゲロを吐いているな。
「あなたが言った意味がようやく分かったわ。私も、サルボモーターと一体化してる。魂の深いところで膳爺ちゃんと一つになってる。」
「それが新しい機械の登場に脅かされているんだ。平静で居ろというのが間違いだよ。不安を感じるのが、正しい。」
「あなたは違うでしょ、キング。あなたはそんなモノには惑わされない。何度転んでも起き上がる世界の受身王なんだから。」
しおらしくなってしまった綾子の肩を抱く。
大丈夫だ、ピルマルの人形はそう簡単には動かない。おまえの木偶を越えて人に愛されたりはしないさ。
「え、”カラスの脳”?」
次に剣崎に会った時、俺は耳を疑った。
サルボモーター操縦にカラスの脳を利用したシステムを使うのは、俺達も知っている。だが「考える筋肉」を持つサルボロイドで使うとは思わなかった。
今日の対面にはユウ・コウベン・スクも同行している。剣崎が俺に会うと聞いて、わざわざついて来たのだ。
「”カラスの脳”ほどには賢くありません。現在の技術ではオプチカルロジックに置き換えられる生体脳はせいぜいハトですね。」
「だがそれが必要になった。何故だ人間じゃ無理なのか。」
「遠隔操縦で車両と同程度の操作性を実現するには、無人で動かせるだけのAIが必要と判明しました。こう言ってはなんですが、サルボ乗りの方はよくこんなモノに乗れますね。」
「ん、まあ、たしかに。」
剣崎が捕捉説明する。
「つまり納期の問題もあって、とにかく今動く機械が必要なんだ。1年取り組んだけれど月面仕様機から一歩も踏み出せていない。そこで、」
「とにかく動く”カラスの脳”か。ピルマルもよくあんな得体の知れない人工筋肉使っているな。」
「統則制御筋はこれから世界を変えるのです。すでに実験室レベルではサイボーグ義手・義足にも使われて、全身を置換する試みも行なわれています。」
「それがあんたが目指す未来か。」
吊り目に優しくしてやる義理は無い。だが奴の夢、奴の理想からすれば、月面仕様機に留まるサルボロイドはあまりにも低い成果だろう。
「俺は、あんたが、サルボロイドを巨大なサイボーグボディにしたがっていると思ったんだがな。」
「ああ。キングさんは夢が有っていい。ですが私も企業の一員です。夢ばかりは追いかけられない。」
「でもこれじゃあ、サルボモーターには勝てないぞ。」
「それで貴方にお会いしなければならなくなりました。キングさん、どうか我々に御力をお貸しください。」
「…ああ、そうだったな。月面機で作業出来るのは俺だけだった。」
断ってもよかったが、俺もツルニハオフィシャルのチームに属する人間だ。貰うカネの分は働く義務があるし、剣崎に協力すると思えば苦にもならない。
「仕方がないな。ツルニハが潰れても困るしな。」
「なんなのよコレ! キング、これなに、なんなの? あなたこんなもの開発するのに協力したっての?!」
ジムでウエイトトレーニングしていた俺とベンは、綾子が血相変えて飛び込んで来たのにびびってしまう。この狼狽えようは、尋常ではない。
「おいどうした、ツルニハの株が暴落でもしたか。」
「株なんか、全部自社で持ってるわよ! これ見なさい。なにこのおぞましい機械は!」
A4用紙大にプリントアウトした試作サルボロイドの最新画像だ。俺が手を貸して作業が可能になった。結構可愛い、女に受ける外観だと思う。
「具体的にどこが悪いんだ?」
ベンも綾子の興奮の正体が分からない。サルボロイドは無人で格闘が出来るほどに仕上がっている。弱いが、素晴らしい進歩だ。
「これよこの胴体下部、ここに付いているコレ! これなんなのよ。」
「なにって、制振装置だろ。アクティブカウンターマスで機体に発生する揺動を打ち消し、作業を可能にする。」
「ああ、これは大した発明だと俺も思うぜ。サルボモーターにも付けた方がいい。」
「で、で、出来るかこんなもん! ま、まるでまるでまるで、」
制振装置は2つの球体の錘をアクチュエータで前後左右に動かす。或る程度のストロークが必要な為に胴体内には納められない。
重心に近い胴体下部こそが最適取り付け位置であり、外部にオプションとして装着する。今更胴体の設計変更なんてする暇は無い。
ただそれは、かなり見慣れた外観となった。2つの錘を豆の鞘状のカバーで覆うと、あらふしぎ。
「た、たんたん、たんんたぬきの、」
「キンタマにそっくりだな。」
「はは、面白いぜ。」
「きいーーーーーーーー!」
サルボロイド出荷第一号は、やはり月に飛んで行った。月面でのサルボモーターの活躍が認められ、作業にも使ってみようと考える。
だから名称はこれまでどおり「月面仕様サルボモーター(改)」だ。妙な変更をすれば、議会が予算を認めてくれない。
ピルマルSIの計算通り、なのだろう。
月という苛酷な環境下で作業が可能であれば、地球上どこにでも投入できる。宣伝効果ばっちり、納期を急ぐわけだ。
ただ、ユウ・コウベン・スクの表情は暗かった。表情が見え難い奴だが、不満に鬱屈していると俺達には分かる。
剣崎ら技術陣も不完全燃焼で燻っている。
仕方ない、今回はサルボモーターの勝ちだ。鶴仁波膳九郎と桧垣天才の、時を越えた勝利だ。
綾子が俺を突っつくので、仕方なしにユウに話し掛けた。ピルマルの偉いさんと打ち合わせしていたが俺の姿を見て正面から、二人サシで語る。
「これで終りじゃ、無いよな。」
「始まったばかりです。サルボロイドは日々進化し、今にサルボモーターを追い抜きます。」
「うん。だがもう一度教えて欲しい。あんたは、何の為に人型ロボットを作るんだ。ただ兵器のサポートをする脇役が目的じゃないだろう。」
「ほんとうに、キングさんは面白いことを尋ねてくださります。ええ、最終的にはそんなものじゃありません。」
「うん。」
「ですが、ロボットが目的でもない。私は統則制御筋の可能性をとことんまで突き詰めてみたい。人工筋肉はもちろん人体との親和性が高く、人間大の世界で大活躍します。だがそこで留まる技術ではない。大きなもの、世界を変える力を持つもの、人間の意識を宇宙全体に拡大する助けになる。そう考えますよ。」
「大き過ぎて分からんよ。」
「統則制御筋で動くサイボーグボディは、脳を身体の運動制御の負担から解放します。機械の身体を機械の脳が司り、人の脳はより価値の有る情報処理に能力を振り向ける事が許されます。」
「なんだそれは?」
「現在の情報ネットワーク技術の巨大さは、一個人に把握できるものでは無いでしょう。それが可能になるのです。同時に肉体も宇宙的規模に強化される。人がアクセスできる知能・情報・物理力を均等に拡大する。精神と肉体と双方が共に進化してこそ、次のステージに人類は羽ばたけます。」
「分からんねえ。だがまあ俺達サルボ乗りは、その世界には住めそうに無いな。」
「それはあなた方が、自らにふさわしい大きさを備えているからですよ。現代人には今の肉体は小さ過ぎる。ヤドカリが成長に合わせて貝殻を脱ぎ捨てるように、次の殻を誰かが用意しなければならない。」
こいつはいつか世界を変えるだろう。だが何人が理解してくれるのか。
世界の偉人には、死後何百年を経てようやく業績が評価される者も居る。そんな予感を奴に覚えた。
俺がユウと話している間、綾子は剣崎らツルニハ技術者の努力を労っていた。
だが戻って来た彼女の表情も、暗い。
「どうした?」
「なにか、ひどくイヤな予感がする。このプロジェクト関わるべきじゃなかったわ。」
「ん?」
剣崎に振り向くと、俺が見ていると知って彼は顔を背けた。確かにヤバい気が漂っている。
数日後、俺は不安の正体を知る。
『キングさん、済まない。』
剣崎の電話は音声のみだった。耳元で辛く悲痛な声がする。
ツルニハ開発部の若手・中核技術者の集団移籍。別れを告げる挨拶だった。
第八歩 鶴仁波○○堂のサルボモーター
ツルニハの若手・中核技術者大量移籍騒動の報は、瞬く間に世界中のサルボ乗りに広まった。
皆一様にこう思う。
「おお、やっぱそう来たか。」
「OH-Tono(大殿、膳九郎氏の愛称)の逝去から5年、思ったより長持ちしたな。」
「やはりツルニハは潰れ掛けでないと緊張感が足りないな。善き哉/\。」
俺だって他人事なら無責任にそう囃す。だがツルニハオフィシャルチームに属しているからには、冷たい顔も出来ない。
というわけで早速日本の鶴仁波本家に綾子を送り届ける。
騒動は慣れっことはいえ、前回までは会長の膳九郎氏がしっかり手綱を握っていた。より正確には、膳九郎氏逝去直後のごたごたも事前にしっかりと準備しており、なんとか無難に乗り越えた。
つまりは、現社長にとって真の危機は始めての経験となる。
鶴仁波進平社長58才。膳九郎氏の末娘の婿、綾子の父親だ。
彼の前には先妻の息子が3人居て、順繰りに社長を務めていた。現会長は三男だが、実質すでに経営からは手を引いている。
さてその進平社長だが、婿であるから当然鶴仁波の血筋ではない。ワンポイントリリーフだと一族からは見られている。
だからと言って、彼を追い落とす陰謀なんてものは無い。
衆目の一致する予想としては、サルボモーターなんてゲテモノ作っている会社は早晩潰れるに決まっている。
そもそもが膳九郎の爺さんの趣味が高じた暴走であり、今倒産してもちっとも惜しくない。
だが存続させるとすれば、継ぐべき人物はサルボモーターの申し子である鶴仁波綾子であろう。
彼女は世界中を飛び回り営業活動に勤しんでいる。各界VIPに顔が利き、銘菓「鶴仁波」もちゃんと売って来る。
いずれ綾子ちゃんが社長に納まれば、まるっきり問題無い!
綾子は金勘定にはあんまり向かないぞ、と身近に居る俺なんかは思うが、大した欠点では無いらしい。
なによりも人型ロボットの馬鹿商売を継続する情熱、これこそが重要であり、その点に関して綾子は非の一点も無いわけだ。
ただ他にやる気の有る人物が居れば、また別の展開を見せる。
俺とベンは、再び京都の鶴仁波本家を訪れた。
一族の皆さんが多数お見えになられてた。前回の鄙びた風情とは一転し、周辺の道路や駐車場には無数の自動車が停まっている。
なにより、或る車種が数多く揃っているのに驚かされる。
『SARVO Ⅱ』、ツルニハ工業が1990年代に売り出した自家用車だ。発売から既に50年、とっくの昔に廃車になっていなければならない。
だが皆ぴかぴかに光っている。中身もごっそり入れ変えられ、バッテリーやホィールインモーター、AI自動ナビシステム、センター誘導操縦サービス等々21世紀半ばにふさわしい装備に化けている。
一族の皆さんの物持ちが異様にいい、わけではない。実はツルニハの裏商売は『SARVO Ⅱ』のレストア、近代化改修なのだ。
『SARVO Ⅱ』の前のモデル、1970年代に売り出された『SARVO』は、これまた酷い自動車だったらしい。
だが売れた。経費削減の為に天井ぶった切って偽コンバーチブルに改造したところ、貧乏な若者に人気を博しそこそこ売れた。つまりは趣味だ。
当然次のモデルも趣味性を前面に打ち出して設計される。実用性なんか考えてツルニハの自動車を買うバカは居ない、と見極めた。賢いな。
故に外観には徹底的な注意が払われる。単にスタイリッシュなだけでなく、変質的執着を覚えるユーザーを対象に練りに練られた。
FRPによる造型も、それが為だ。ボディを鉄で作るのは金型代がもったいない。外見が受けなければ即取っ替える気満々だったのだ。
この戦略はもちろん極一部の変質的ファンにしか受けなかった。が、それで十分。
結構高価であったにも関わらず、ツルニハは2010年までに通算10万台を売りつける。他のメーカーに比べれば微々たる数だが、なに売る方もほとんど趣味だ。
で、くたびれてエコにも非対応になった『SARVO Ⅱ』の延命を望むコアな変質者を相手に、近代化改修サービスが行われる。
趣味だからえらくぼったくるのだが、これのおかげでツルニハはサルボモーターなんて道楽を続けられたのかもしれない。
また海外生産分『SARVO Ⅱ』というのも有る。某発展途上国で自動車産業を立ち上げるのに協力したもので、こっちの方が生産数が多い。
エンジンも違うし装備が安っぽいし、名前もその国で別に付けているから正式には違うのだが、サルボ乗りの間では「偽SARVO」として知られる。
流石に鶴仁波本家には停まっていない。
「壮観だな。クラシックカーの行列だ。」
後ろから俺達は声を掛けられて振り返る。旧知の白人のおっさんが立っていた。
「ミハイル・パシミスコフさん、か。」
「おう、キングもチャンピオンも雁首揃えてるな。だがツルニハのお家騒動にはお前達関係無いだろ。」
「そういうおっさんは、もっと関係無いはずだ。どうした?」
「どうもこうも、」
被っていたキャップを脱いで、おっさんは頭の汗を拭う。まだ春だが日差しは強く夏同然の気温になる。これも地球温暖化の影響か。
髪が有る様で無い。まっ白髪で後頭部はつるりと陽を反射する。痩身でなかなかダンディだけに、頭が冗談に見える。
「ツルニハの若い連中が入って来たもんで、俺の居場所が無くなっちまった。これ以上イカの刺し身と格闘するのも骨だから、逃げて来たんだよ。」
「おっさんは、サルボロイド開発には関わったのか。」
「月面に送る前には俺が面倒を見たが、開発は知らん。前のと外観は変りないんだが、中身は別物だったぞ。」
俺もベンも開発に協力はしたが、中身にはまったく触っていない。手で作業をする為に上半身の筋力を大幅増強したのだが、風船腕脚カバーに隠される人工筋肉は見なかった。
ベンはおっさんを知らない。俺が丁寧に礼儀正しく応対するから、なんか関係者だろうとは感付く。
デカい身体をくにっと曲げて、御辞儀した。彼もなんだか日本風になってきたもんだ。
俺は改めて尋ねる。
「で、今日は何の用なんだ。」
「招待状が送られて来たんだ。キング、知ってるか?”TURUNIHA・MEIKO”って奴。」
「芽衣子がか? そりゃどういう筋だろうな。」
前回京都入りした時に会った女子高生、今は女子大生になっている鶴仁波芽衣子はサルボモーター事業に強く興味を示す。筋金DNA入りの経営者志望だ。
後に詳しく血縁関係を尋ねてみたら、膳九郎氏の前妻の長男の孫、であった。綾子とは結構離れている。
「ふむ。だがそんな娘がどうして俺を必要とする?」
「彼女は鶴仁波直系の、例のアレ体質なんだ。何考えてるか見当もつかん。」
「膳九郎氏とおんなじか。末恐ろしいな。」
かって知ったる、て顔で迷いもせずに鶴仁波家の伝統的木造瓦葺きの門を潜っていく。
門の左右は黄色い土塀で、作り物にも関わらず人工の観が薄い。これが日本の美て奴か。ちらちらと桜の花も残りなんとも佳い風情だ。もう少し涼しければな。
典型的な日本家屋、木と瓦と土で作られた建物は鶴仁波の伝統を誇るかに広壮。
特に庭がいい。
聞いた話だと、鶴仁波の分家が日本庭園専門の造園業を営んでいて、モデル展示場として本家の庭を手入れしているらしい。
母屋の仏間が会議場となる。御先祖様の前で真剣にツルニハの行く末を語っている、はずなのだが。
「うるさい…。」
百人がとこ身内が集まって、あーでもないこーでもないと口々勝手に意見を述べる。
誰が仕切るわけでもなく、ではなくて社長の進平氏が司会をするべきだろうが、養子だから抑えが効かない。
仏間の外では子供たちがうろちょろしている。身内が勢揃いする騒動は、それぞれの子を紹介する場としても機能するのだろう。
「あ! キングだ!!」
「キングさんだ。」
「受身王だ! わーい。」
見つかってしまった。俺は世界的スターだって自覚をころっと忘れて、無警戒に踏み込んでしまう。たちまち10数名の女子供に囲まれた。
「わぁー、こっちのおおきいひと、チャンピオンだよ。」
「ベンジャミンさんだあ。」
「サイン下さい。背中に書いて!」
ベンもサルボ格闘2連覇成し遂げ、すっかり世界メジャーにのし上る。奴の巨体なら、小学生の4、5人腕にぶら下げても大丈夫。
ミハイルのおっさんもあきれて言う。
「大した人気者だなあ、キングさんよ。」
「キングさん、ベンさん。」
年配の女性の優しい声に、俺達は振り返る。
清子さんだ。和服で、渋いながらも華やいで見える模様を描いてある。歳をとっても美人は美人、という典型例だ。
仏間の騒ぎを置いて、清子さんは子供たちと遊んでいた。
鶴仁波本家を護る彼女は当然一族で最も重視される存在だが、事業に関する話し合いには口を出さない。
綾子によると、「おばあちゃんが出て来ると、一発で全部決まっちゃうから面白くないのよ」、だそうだ。
清子さんは改めておっさんに向き直り、丁寧に腰を曲げて挨拶する。
「ミハイルさん、おひさしぶりです。ようこそお出で下さいました。」
「や、どうも。これは随分とご無沙汰を。」
「17年ぶりでしょうか。」
おっさんは鶴仁波本家に来たことがあったのか。ちょっとした驚きだ。
「子供たちの居ない所でお話ししましょう。離れへどうぞ。」
「あ、これは、どうも。」
おっさんもさすがにあがっている。清子さんの柔らかい雰囲気に接すると気圧されてしまうのは、俺達だけじゃないらしい。
廊下を進もうとするが、男の子が一人俺にしがみ付いて来た。清子さんが、これから大人のお話があるのよ、と言っても聞こうとしない。
ちぇい、と清子さんが軽くチョップをし、男の子は「ぐあああっ」と額を抱えて廊下に転ぶ真似をする。
お茶目な婆さんだ。
離れの茶室で俺とおっさんは神妙に正坐している。ベンは子供たちから逃げきれず、庭で「サルボモーターごっこ」をさせられた。
清子さんが茶筅でしゃかしゃかお茶を点てている。
やはり、人が違うと趣が全然異なる。綾子も茶道の免状を持っているが年季が違う軽薄だ。
御存知のとおりに、ツルニハの本家「鶴仁波○○堂」は老舗の饅頭屋だ。茶とは切っても切れない関係を持つ。
故に家人は茶道の心得が必修となる。分家には茶道具を扱う店まで有る、どころかとある茶道の宗家まで務めていた。
「鶴仁波七堂」と呼ばれる鶴仁波家七つの生業の柱の一つだ。
書画骨董美術品、造園、服飾デザイン、宣伝広告、サルボモータ、とまあ手広くやっているな。
驚く勿れ、これらすべての事業はひたすら饅頭を売る為に始められたと伝わる。
それら七堂の連中が仏間に集まって会議しているわけだ。
ミハイルのおっさんが年長であるから、先に茶碗が回って来る。
俺はこれでもなかなかのインテリゲンチャであるから、日本文化についても造詣が深い。綾子に世界中連れ回される内にイヤでも習わされた。
おっさんはそうじゃない。苦い茶を我慢して頂く。あ、全部飲んじまった。
改めて俺の為にしゃかしゃかしてくれる。遠くからは会議の喧騒がうっすらと聞こえて来るが、まるで別世界の出来事だ。
「結構なお点前で。」
どこらへんが結構なのかは分からないが、型通りにそう言っておくのが正しいのだろう。ケチを付ける糸口など微塵も見当たらないから、そりゃそうだ。
微笑んだまま会釈する清子さんは、床の間の掛け軸をしばし見詰める。俺達もつられて眼が向かう。
車輪の絵だ。
大八車の片輪を立て掛けて蔓草が絡んでいる。
茶席にはほとんどありえない図柄だが、今日はツルニハ、元の「鶴仁波転輪堂」の会合だ。
茶室に案内される人は皆、車輪を捨てて二足歩行ロボットを取った前会長を偲ぶだろう。
清子さんはおっさんに振り向く。その表情は俺達小僧っ子に向けるものと違い深く麗しく、どうして羨ましいぞ。
「もう、17年になりますね。」
「そう、ですなあ。わたしがこちらにお邪魔したのは、そのくらいになりますか。」
「あの時も春でしたね。」
「はい。お花見でした。」
俺の知らない話だ。ミハイルのおっさんは社員慰労の花見の宴に国外から、膳九郎氏直々に呼ばれたらしい。
屋敷の庭で行われた宴会で、桜が見事に咲いていた。地球温暖化の影響をものともせずに妖しく美しく、なにより楽しい時間を過ごしたわけだ。
膳九郎の爺さんもその頃はぴんぴんしてただろう。清子さんは今よりもっと美しかったのかもしれない。
おっさんもまだまだ若かった。輸出機体のクレーム処理で死に掛けていたとしても。
「あの頃は楽しかったですね。」
「そうですなあ。毎日がおもちゃ箱をひっくり返したようなものでしたよ。」
「まあ。ホホホ。」
サルボモーター創世期、俺には理解できない苦労があっただろう。が、その時を生きた人にはかけがえの無い、誰にも譲り渡せない黄金の日々だった。
鶴仁波膳九郎、やっぱりあんたは大した人だ。
遠く仏間から聞こえる声に、覚えの有る悲鳴が混じっている。どうやら会議は順当に進展し、綾子が吊し上げにあっているみたいだ。
「サルボモーターの女王」なんだから、まあ当たり前の展開だな。
さすがにおっさんも、清子さんに心配する。
「よろしいのですか。」
「よいのですよ。細工は流々、仕上げは芽衣子がちゃんと整えています。
ミハイルさん。実はあなたに折入ってお願いがあって、お立ち寄り頂いたのです。」
その芽衣子の声が聞こえる。ぐだぐだと同じところを堂々巡りする議論にいい加減切れて、叫んだのだ。これも計画通り。
「…キンタマくっついたロボットが売れるはずあらしません!」
どうやらサルボロイドがサルボモーター市場に与える影響を、一言の下に論破したらしい。
確かに股間に振動制御装置をぶら下げたサルボモーターは、趣味では売れないだろう。
ただうら若き女子大生の口からそのような言葉が出るのは、どうにも。俺とおっさんは清子さんの前で、しばし顔を赤らめた。
清子さんはどこ吹く風で、本題に入る。
「実は芽衣子は既にピルマル理科工業の上層部とひそかに話を付けているのです。
現在開発中のサルボロイドは、しかし当分は独自の運動制御プログラムが言うことを聞かない。サルボモーターベースで実用を急ぐとなれば、当社のプログラムに頼らざるを得ない。
そこで芽衣子は向こうの開発チームの頭越しに、プログラムの供与を約束してきたのです。」
「ほお。つまりピルマルが機体を売る度に、こちらもちゃんと儲かる算段を付けて来たのですな。」
「それとは別に、サルボモーターももう30歳を越えました。基本特許の期限が切れて、誰でもが作れるようになっています。」
それは俺も懸念していた。特許期限の25年を過ぎて法的にはどこの誰でもがサルボモーターを作ってよい。
歩いて転ぶ以外何も役にも立たないロボットに挑戦する酔狂な企業が他に有るとも思えなかったが、しかし状況は変わった。
また個人で機体を組み上げようて奴は、俺の知り合いにも結構居る。その際にネックとなるのが、やはり運動姿勢制御プログラムだ。
こちらの方は著作権で縛られているから、違法コピーしか使えない。プログラム供与の前例が出来れば、なにかと都合はいいな。
「そこで芽衣子は、ツルニハ本社とは別にツルニハ・サルボメンテナンスサービスという会社を作ろうと考えたのです。
プログラムを売ると同時に、サルボモーター形式のロボットの為の部品やらメンテナンスを提供する別会社です。ピルマルさんの機体もサービスの対象となるわけですね。」
サルボモーターが世界中で愛される理由の一つに、故障したらちゃんと技術者が飛んで来るサポート体制がある。無論有料だが。
極点で擱座しても万難を排して駆けつける姿に、俺達サルボ乗りは何度勇気づけられたか。今では俺自身がその役をかって出ている。
「そのメンテナンス会社の社長に、芽衣子さんがなるわけですか。」
「いえ、それをこちらの、ミハイル・パシミスコフさんにお願いしようと。」
「ちょっとまった!」
おっさん流石に顔色を変える。この歳まで整備とクレーム処理だけで生きて来た彼に、社長に成れとは度胸が座り過ぎてる提案だ。
「生憎とわたしはこれまで経営とかいうものに携った経験が全くないので、その件はごかんべんを。」
「そのくらいはどうとでもなりますよ。大丈夫、経営の人材はどこからでも連れて来ます。芽衣子にお任せ下さい。
わたくしどもが貴方に期待するのは、サルボモーター創世期にサービス部門の顔として働いて下さった、存在感と安心です。古いお客様の間ではいまでもご要望があるのですよ。「あのわからず屋の男は来ないのか?」って。」
おっさんは苦い茶の味を思い出したかに顔をしかめて、天井を仰ぐ。
なるほど、存在感と安心か。年中行事的にふらふらと倒産危機に陥るツルニハは、爺さん亡き後拠り所を見出せずに困っている。
メンテナンスサービス部門が独立して安定するのは、これはまったく大歓迎だ。
しかし。
俺は懸念を口に出す。
「しかしツルニハ本社の方は、どうなんです。メンテナンス部門は結構収益の柱となっていたはずです。それに、サルボモーターの改良は技術者が抜けて、」
「そこで新製品です。」
清子さんがにっこり笑う。と同時に、茶室の外に大きいのと小さい複数の足音がした。
ベンがにじり口の外から声を掛けてくる。
「おいキング、なにか新型の機体のデモンストレーションが始まるみたいだぞ。」
「新型、って、そんなものどこに隠していた?」
「いや、それが、小さいんだ。人間大のサルボモーターだ。」
前回ここに来た時芽衣子が言っていた、メイドロボだ。サルボモーター形式の等身大作業ロボット、メイドロボとは名ばかりの野外高速走行警備用だ。
試作を始めていると聞いたが、もう形になったのか。
茶室を出て初夏の風情を匂わせる庭園に降りてみると、多くの鶴仁波一族の前にソレが立っていた。
メイド服に似せた白黒の外装、全高160センチほどの人型ロボット。ちゃんとアニメ顔の頭も付いている。髪はウィッグではなくプラスチック成形だろうか。
芽衣子がマイクも無しに説明をする。右手には電子ノートではなく紙にプリントアウトした技術資料。彼女は紙を愛するアナクロ趣味らしい。
「今回脱走した技術者は、メイドロボ「サルボエンジェル」の開発には携っていなかった人達です。技術集団としては常にアグレッシブな挑戦が必要であり、企業が怠ると頭脳の逃散を食らう、ごく自然の成り行きです。」
見守る一族の中に不安な顔の綾子が立っている。目で合図すると、瞬きでサインを送って来た。
『このロボットはヤバい』。
だがメイドロボはふらーりと左右に揺れながらも立っている。
30年に渡るサルボモーター研究の成果が反映され、普通に平面を動くだけなら自動でも大丈夫な水準にこぎつけた。変なことさえしなければ。
「このメイドロボは通常のAI行動選択以外に、ユーザーによる遠隔操作を受け付けます。私の右手には触覚感応マウスのチップが埋め込まれていますが、これを用いてのダイレクトコントロールを実演します。」
資料を左手に持ち替えて、芽衣子は右手を高らかに挙げる。
びしっとかっこを付けて、メイドロボを手刀で指し示した。なにも起きない。マウスの検知チップにはLED等は内蔵されていないから、動作を示す徴は無い。
ぐぎっと、ロボットが動く。右手を挙げ、ぎこちなく御辞儀をする。
そのまま急に半旋回して後ろを向く。きわめてトリッキーな手足の動きだ。今の旋回は半ば転倒しかけたがうまく誤魔化した為、素人には分からない。
ロボットは左右の手を同時に持ち上げ、振り下ろす。通常のサルボモーターが初期反動を発生させるとおりに、動き出した。
両脚のバネに与えられたテンションを解放し前のめりになったのを、姿勢制御プログラムは機体の前進で立て直そうとする。
雪崩落ちるかの勢いで、3歩の内にトップスピードに到達。いきなりマキシマムで突っ走る。
梅の木に左手を引っ掛け進路が変わり、伝統の風格を今に留める良い感じに古びた土塀に思いっきり激突した。
古いアメリカの手書きアニメみたいに、メイドロボはゆっくりと壁から離れて地面に大の字に倒れる。黄色い土塀にはそのまんま、メイドロボの型が描かれている。
デモンストレーション、しっぱい。
誰かが叫んだ。
「膳さんだ!」
「膳さんだ。膳九郎さんだ!」
「膳さんが帰って来た!!」
なんのことだと綾子の顔を見ると、目を潤ませている。まるで死んだ爺ちゃんが戻ったかに、感動が涙となって迸る。
膳九郎氏が生前に行った数々の失敗。その一つを再現したかの情景に、皆が等しくそう思ったんだ。
鶴仁波一族にとって、この程度の失敗はむしろ誇りに思うべきなのだろう。
この瞬間、鶴仁波芽衣子は次代を担う当主候補として認められた。
おそらくは、ツルニハ・サルボメンテナンスサービスの件も賛同される。きっとうまく行く。
良くわからないが、おめでたい。
清子さんも手を子供のように叩いて喜んでいる。
「何を読んでるの?」
水干烏帽子白拍子姿の綾子が、携帯電話で論文を読んでいる俺を不審に思って尋ねる。
周囲は祭の興奮に浮かれる中、待機中とはいえ画面拡張モードで細かい文章に集中する姿は、なるほど場違いだ。
が、俺は機体の操縦が有るから振舞い酒にはありつけない。白頭巾に鎧の山法師に化けたベンとは違う。
「博士論文。」
「誰の?」
「ユウ・コウベン・スク。もう17年も前に発表された奴だ。」
ピルマル理科工業でサルボロイド開発に血道を上げているだろうユウの経歴を調べていて、この論文に突き当たる。
彼は元々電脳技術を学んで博士号を取っていた。論文もそのものずばりの、脳内への電子機器挿入による能力拡張研究。
しかし案に相違して、彼は電脳技術にかなり批判的だ。この技術が進展したところで、本質的な人間の進化は決して実現しないとする。
17年前といえば電脳フィーバー真っ最中であるから、かなり変な論文だ。
まあ、電脳技術が事実上禁止されてしまった40年代の今読み返してみると、当たり前の事しか書いていないのだが。
「この論文によるとだ、人間の脳でコンピュータに直接アクセスするにはオーディオビジュアル系統の機能でなく、肉体制御系の脳領域を用いるべきて結論になる。」
「触覚とか運動神経とかね。」
「モノを扱うのだから当たり前だが、この当時はグラフィカルユーザーインターフェイスを直接脳に突っ込もうて発想のまま突き進んでいたからな。頓挫するわけだ。」
理由は至極簡単。意識がコンピュータの操作に集中して、他の事が出来なくなる。頭痛やら記憶障害、妄想の肥大、神経の異常興奮による不眠症も副作用として表れる。
セキュリティの問題や悪用によるプライバシー漏洩騒動もあって、一般人の使用は世界的に禁止されてしまう。
代りに登場したのが、触覚感応マウス等の身体感覚を利用するインターフェイスだ。電脳技術よりも生産性で2倍は確実にアップしたと言われる。
電脳業界は今では、意識の負担を下げて脳が勝手にネットワークを探索する研究や、人工知能によるサポートで能力拡張を図る方針に変更されている。
ユウの論文は今の状況を先取りし、解決策を提示するものだった。
俺の手元の画面を覗き見て、綾子も呟く。
「”…サイボーグ技術、身体の機械化と制御機能の代替によって余剰領域を脳に作り出し、ネットワーク操作機能を人体に組み込む。”」
「要するに脳がやってる余計な仕事を外部に委託して、暇になったところでコンピュータの操作をさせる寸法だ。上等な理性とか思考やらは、下調べが終った環境で働けばいい。」
「ラクチンね。」
「楽でないと高度な思索レベルには到達できない。我ら凡人には有り難いお話だよ。」
雀百まで踊り忘れず。キャリアの第一歩であるこの論文の通りに、彼は今も人工身体、拡張人体の製作に熱中する。
派手な法被を着た祭の実行委員会の人が出番を告げに来た。これでも俺は世界的有名人だから、彼はちと緊張しているかな。
「キングさん、よろしくお願いします。」
「はい。じゃあ一丁バケモノ退治に乗り出すかあ。」
「あなたは、やられる方。」
酒呑童子が俺の役だ。もちろんサルボモーターに仮装させて京の大路を練り歩く。
伝統有るお祭りに巨大ロボットを参加させるのはそれは反対も多かった。事実去年までは参加していない。転倒時の事故も危ないし。
だが月面でのサルボモーターの活躍で人の見る目も大きく変わる。人気映画『若太朗』シリーズで主人公も搭乗するなど、環境が整った。
ツルニハの人達は祭への参加の依頼を受けて、感無量に覚えたそうだ。
洛中を追放されて400年。ついに宿願の都への復帰が叶うのだから、そりゃあ嬉しかろう。
社長自ら音頭を取って、サルボモーター外装製作に熱を入れて取り組んだ。
パイロットにも決して事故を起さない最高の人材、「世界の受身王」つまり俺を当てる。万全の安全対策だ。
こうして出来上がったサルボモーター「酒呑童子スペシャル」は、性能的にはノーマルに過ぎないが外装がかなりかっこいい。
シルエットに変わりは無くとも表面処理に凝りまくり、塗装で陰翳を強調した有機的な褶曲が筋肉っぽい感触を醸す。まさに鬼!の姿を生み出した。
お祭り用には最高の怪物だから、社長もいい気になって10機ほど売り出す算段を付けている。
鬼が立ち上がると、ばちばちっとカメラのフラッシュが焚かれる。テレビ中継のレポーターのお姉ちゃんが俺を見上げる顔が白い。
観客の前に姿を見せると、一面の大歓声だ。
「大成功だな。」
俺の前には仮装した綾子とベンが、周囲には観客が飛び込まないよう警備を配して、鬼は大路をゆっくりと歩いて行く。
コクピット内部で放送中のテレビ番組を確かめてみたが、前後を時代劇の装束を付けた行列に挟まれるサルボモーターは、不自然なほどに違和感が無い。
まるで千年も昔からこんな生き物が棲んでいたと錯覚するほどに、古い街に溶け込んだ。
鬼はゆっくり歩いて行く。
陽炎のように儚く、古樹のように重厚に、過去と未来とどちらにも背を向けて、今を歩く。
(一巻之終)